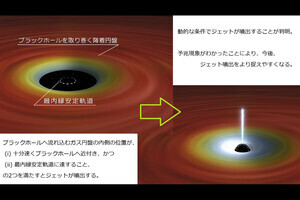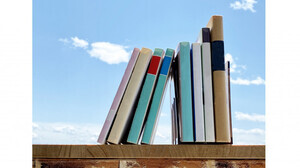かつてヒラリー・クリントンが本邦の医療制度を目にし、「日本の医療は医師の犠牲的精神で維持されている」と驚嘆した。我が国の医療態勢は国民皆保険制度下にあり、アクセスの自由度と給付内容の高さは世界最高レベルである。医師のみならず、看護師・診療技士・介護士等のコメディカル(医師以外の医療関係職)の犠牲もあって「佳良に」維持されてきた。
診療所・病院は医業収益から経常利益を生み出し、機器・薬剤の購入や従業員の給与を保証せねばならない。その医業収益は、診療報酬点数(表)によって全て一律に、社会主義経済的に安く定められている単価に、出来高を掛け算して得られる。「入り」だけを社会主義的にコントロールされ、医療機関はひたすら出来高を積むしかない。
現在、コメディカルの新規採用は著しく困難であるばかりか、他の職域へも流出している。理由は低賃金である。民間病院の利益率は、2~3%が関の山。給与アップの原資は殆ど出ない。その給与の責任者は政府に他ならない。
給与充当の前提で診療報酬点数の大幅増額を実行しない限り、本邦の医療職場は維持できない。全労働人口の13・3%を占める医療・福祉関係職は、消費者でもある。この給与を上昇させると、購買力が増大する。
医療への投資は必ずしもブラックホールではない。看護師・介護福祉士計約400万人に1人3万円の月給増と仮定しても、たかだか1兆8000億円規模の増加で、政治に意志さえあれば可能な話だ。
一方、急激な人口減少は推計学的に定着した見解である。人口の急減が若年側から進行していることは、急性期患者の減少を意味し、出来高が生命線である医療機関は急速に経営困難になっている。
ところで、本邦の病院は、中小規模病院が多く、約7割が200床以下で、その72%は民間立である。それでいて病床数は世界第1位、人口比で2位のオーストリアの2倍以上と極めて多い。医療費の大半は医科診療費で、その過半を占める入院費の由来が、これら病院である。
過剰である上に、過当競争に陥った病院(病床)という認識、これが設立者としての医師個人、そして医師会・病院連合体の指導者に求められている。医療の崩壊を回避するために必須の、病院・病床の集約が医療界に求められている。弱肉強食に委ねるのはスマートではない。
地域ごとに、ある病院には急性期を集中し、別の病院は急性期を完全に放棄して療養・慢性期病棟専門に転換したり、一部を廃院にするなど、思い切った主体的集約が必要である。
存続ないしは拡張する運命となった病院は他院の医療職の吸収を含めて定員を増し、経営を安定化させる。人口増加で右肩上がりに増設を重ねて来た本邦では初めてのことながら、不可避である。新たな政策誘導によるか、既存の「地域医療連携推進法人制度」による統合化、あるいは地域的な医療機関同士の協調再編が必要である。
どの程度に集約するか。人口減少の現状では目標値の設定は無理という指摘もあろう。病床数として、一旦OECD諸国の病床数を参考に、対人口比率の数値を打ち出し、次に人口が約1億人付近まで減少する2050年頃を目途に目標数を設定することはできるだろう。
一方、国民も、医療費の国民負担率を再検討しなければならない。政府・医療界・国民三者の決意で、世界に誇るこの医療制度を維持することは可能である。