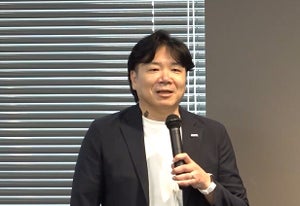パナソニック ホールディングス傘下のシステム開発事業会社、パナソニック コネクトは3月10日、同社のSCM(サプライチェーン・マネジメント)事業に関する説明会を実施した。執行役員 CTO(最高技術責任者)の榊原彰氏が、SCMの重要性と課題、そして同事業の現状などについて解説した。
そもそも「SCM」とは? 注目される3つの要因
SCMとは、一言で言えば、「供給事業者から最終消費者にモノが行きつくまでの、全体プロセスを効率的かつ最適に実現するための経営管理手法」のことだ。
具体的には、サプライヤーからメーカー、倉庫事業者、物流事業者、卸・小売事業者、そして消費者へと流れる「モノ」と、その逆方向に流れる「お金」を包括的に管理する手法のこと。榊原氏は「CRM(顧客関係管理)やERP(企業資源計画)、PLM(製品ライフサイクル)といった経営管理手法と同じレベルで、モノとお金を管理する手法がSCMだ。また、それぞれの管理手法と密接に関係しており、SCMは経営管理の土台の一つになっている」と説明した。
SCMはなぜ重要なのか。その要因として、榊原氏は「サプライチェーンのグローバル化」「環境の不確実性」「消費環境・消費者行動の変化」を挙げた。
昨今、サプライチェーンのグローバル化が顕著だ。原材料や部品、完成品の調達を通じて、企業や国、地域の相互接続が進んでいる。この相互接続により、企業は新しい市場や顧客にアクセスできるようになり、異なる地域から原材料や部品をより低コストで調達できるようになった。
その一方で、モノの流れが以前より複雑化している。「部材はさまざまな国から調達され、倉庫や工場を世界各国に置く企業も急増している。複雑化しているモノとお金を今まで以上に着実に管理しなければならない」(榊原氏)
加えて、地政学リスクの影響をダイレクトに受けることもサプライチェーンのグローバル化の負の側面で、SCMが重要視される要因の一つだという。
感染症のパンデミックや、国際的な紛争状態にある国や政治的に不安定な国との取引など、物流が停滞や生産の中断が余儀なくされる場合もある。また昨今、米国が輸入品に対して関税を引き上げていることも、世界中のSCMに甚大な影響を及ぼしている。
「コロナ禍による封じ込め政策で、中国の製造工場が停止する。ロシアのウクライナ侵攻によって、ロシア上空の空路が使えなくなる。こうした地政学リスクだけでなく、異常気象などによる影響ももろに受ける。サプライチェーンのグローバル化を進める企業は、環境の不確実性に対して適切かつ迅速に対応できる仕組みを整える必要がある」(榊原氏)
そして、消費環境や消費者行動の変化もSCMの重要性を高めている要因の一つだ。Amazonや楽天といったECの普及により、販売と配送が一体化したビジネスモデルが一般化した。消費者行動の変化に柔軟に対応できる統合的な管理が求められている。
パナソニックが目指すのは「オートノマスSCM」の実現
パナソニック コネクトが目指すのは、「オートノマス(自律的な)SCM」の実現だ。センシングやロボティクス、AIやシミュレーションといったパナソニックグループが持つさまざまな先進技術を活用して、サプライチェーンにおける状況変化をリアルタイムに分析し、その状況に基づいた適切な判断を現場にフィードバックすることでプロセスの自動化・自律化を目指す。
そのために欠かせないのが、SCMシステムを手掛ける子会社の米Blue Yonderの技術だ。パナソニック コネクトは2021年にAIによる需要予測をもとに顧客企業のサプライチェーンを改善するBlue Yonderを総額約8630億円で買収した。
Blue Yonderは、AI基盤からサプライチェーンの計画系と実行系のシステムなどを「デジタルフルフィルメントクラウドプラットフォーム」として提供しているSaaSベンダーで、2024年度の売上高は13億6000万ドル(約1999億円)で、SaaSの年間経常収益は7億6800万ドル。グローバルの顧客数は欧米を中心に3000社以上となり、2024年のSaaSによる新規顧客契約数は132社に達した。
榊原氏は「400以上の特許を持っているSCMベンダーはBlue Yonder以外にはいない。顧客の現場と仮想空間を統合することで問題を予見し解決するパナソニックのCPS(サイバーフィジカルシステム)技術と、Blue Yonderのシステムの連携を進めている。オートノマスSCM実現に向け、Blue Yonderと共に新たなソリューションを創出している」と説明した。
具体的には、「店舗」「倉庫」「物流」の3つの現場を重点領域に定め、ソリューションの開発を進めているという。在庫計画や出荷計画、S&OP(販売・操業計画)といった計画系のソリューションから、倉庫管理、輸配送管理、ECオーダー管理、ラストマイル配送といった実行系のソリューションまで、SCMの効率化を実現するさまざまなソリューションを提供している。
榊原CTO「日本事業は苦戦」 SCMの課題とは?
欧米でSCMが浸透しつつある一方で、一部の企業や業界を除いて、日本のSCMは世界と比べてかなり遅れている。同社がゴールと定める「オートノマスSCMの実現」に明確な数値的な基準はないが、榊原氏は「達成率は2割くらいだ」と苦い顔を見せた。「正直なところ、日本事業は苦戦している」(榊原氏)
では一体なぜ、日本でSCMの浸透が遅れているのだろうか。大きく分けて3つの課題があるという。
まず考えられるのが、デジタル化の遅れだろう。サプライチェーンの進化の第一歩は、データを徹底的に収集し、見える化すること。それができないことには何も始まらない。榊原氏は「多くの日本企業で共通することは、現場力が強すぎることだ。データ収集の必要性を理解できず、頓挫してしまうこともよくある。いまだに『経験と勘』で管理している現場担当者も少なくない。これでは、サプライチェーンが成り立たない」と説明した。
2つ目の課題が「部署間・企業間に存在する壁」だ。サプライチェーンの効率性を高めるには、全体最適の発想が不可欠だが、日本の大企業でよく見られる部門別・機能別の組織体制や、企業間でのデータ共有を嫌う風土は、それを妨げる一因となっているという。
「企業間だけでなく、残念ながら同じ企業の部署間でもこの壁は存在する。それぞれの部署は、自部門の業績を最大化することに意識が向きやすく、わざわざ他部門と複雑な調整を行おうとする動機が生まれにくい。この壁を取っ払っていくことが重要だ」(榊原氏)
そして3つ目の課題が、「全体最適化の意思決定者がいないこと」だ。榊原氏によると、多くの欧米企業にはCSCO(最高サプライチェーン責任者)というサプライチェーン全体に対して決定権をもつリーダーが存在するが、日本企業にはほとんどいないという。「私個人の体験談だが、日本企業との名刺交換で、CSCOと書かれた名刺は1回(某アルコール飲料メーカー)しかみたことがない」(榊原氏)。
「全体最適化を推進するリーダーが存在しなければ、サプライチェーンは部分最適になりがちで、結果として最も効率が悪いところにあわせることになり、サプライチェーン全体の効率化にはつながらない」と榊原氏は指摘した。