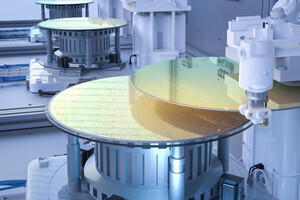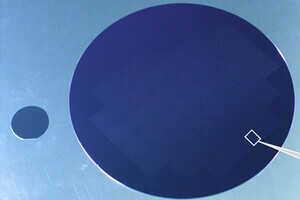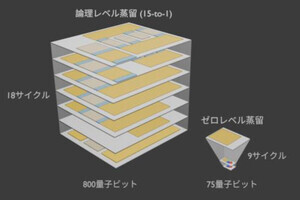危うさ伴う トランプのディール外交
自国第一主義が跋扈している─。特に米トランプ政権が1月20日に誕生して以降、トランプ大統領が打ち出す安全保障政策や高関税策は、国際秩序の根幹を大きく揺るがしかねず、各国も戸惑いを覚えながら対策に大わらわだ。
肝心のウクライナ戦争についても、昨年末の大統領選時に掲げた公約、「わたしが大統領になれば、すぐさま停戦に持ち込む」を実現すべく、当のプーチン・ロシア大統領とも電話会談し、近くサウジアラビアで米露首脳会談を開くと伝わっている。
また、グリーンランドの領有や、パナマ運河の管理権の主張はともかく、イスラエル・ガザ地区を「米国領にしたい」という提案を突如行い、中東各国の反発を受けて波乱含み。
中東の大国・サウジアラビアを巻き込んでの停戦協議は、トランプ大統領のディール外交でうまく〝落とし所〟を捉えられるのかどうかは未知数。当分の間、世界に緊張感が走り続けることは間違いない。
日本の安全保障に影響
こうしたトランプ政権の政策は、回り回って日本の安全保障や経済運営にも影響してくる。
日本は80年前の敗戦で、米国を主体としたGHQ(連合国軍総司令部)の支配を約7年間受け、1952年(昭和27年)に主権を回復した。以来、日米安全保障条約に基づく日米同盟の下で、国家を運営してきた。
歴史を紐解けば、日本は1868年に明治維新を成し遂げ、江戸幕府の鎖国体制を解き、近代化への道を急いできた。そして日清・日露両戦役を勝ち抜き、世界の5大国入りを実現し、アジアでは唯一、先進国入りを果たしてきた。
特に日露戦争では、大国ロシアと渡り合う前に、日英同盟(1902年)を築き、英国の後ろ盾ももらいながら、ロシアに勝利した。この日英同盟と、戦後の日米同盟で日本は国家運営の体裁を整えてきたということ。
そして、第2次大戦の終結から80年が経つ今、世界最強の軍事大国であり経済大国である米国は、『MAGA』(Make America Great Again=米国を今一度偉大な国に!)という旗印の下、自国第一主義を前面に掲げる。
その米国は、戦後は国連(国際連合)をつくり、併せて米ドルを基軸にしたIMF(国際通貨基金)体制を主導し、自由主義・民主主義と連結した資本主義体制を構築。その米国の姿が今、大きく変わろうとしている。
今や、中国は14億の民を背景に〝国家資本主義〟による経済成長を遂げ、米国と対峙するまでに成長。この米中関係の行方がどうなるかで、世界の秩序形成も大きく影響を受ける。
トランプ氏のディール外交は危うさも伴う。氏の戦略は一言で言えば〝脅迫〟とも受け止められる激しい言辞で相手にパンチを喰らわせ、相手の反応も見ながら落とし所を探るという戦法。
どちらも大人の対応をすれば問題ないが、お互い人間のやることである。ちょっとしたスレ違いが相手の過剰な反応を生み出し、力による紛争、ひいては戦争にまで発展しかねない。
「スレスレのところを狙って、解決策を導き出すのがトランプ氏の得意な所」という評価もあるが、実に際どい戦法である。
100余年前、セルビアを訪れていたハプスブルク家が支配するオーストリアの皇太子が1発の銃弾で暗殺された。これが引き金になり、第一次大戦が勃発した。以後、国際連盟を米国が提唱するも、米議会はこれを拒否、米国不在のまま国際連盟は漂流し、第二次大戦に突入、全世界が惨禍に見舞われたというのは記憶に新しい。
歴史は繰り返すという言葉がある。ポピュリズム(大衆迎合主義)が横行し、欧州を始め、中南米や各国で極右政党や極左と呼ばれる勢力が伸長しているという現実。各国の政治とも国民に迎合し、財政も放漫になりがち。自国第一主義で世界経済が萎縮し、インフレ要因が高まる中、さらにバラマキ政治でインフレ懸念が高まる。
『主体性』問われる日本
かつて戦後間もなく、社会主義(共産主義)対資本主義の冷戦構造が長らく続いたが、今は自由民主主義対専制主義という構図に変化。自由民主主義勢力は全体の25%に過ぎないとも言われる。その中で米中両国の動きはどうか? 「中国は『グローバルサウス(新興・途上国)のパトロン』だと言って、グローバルサウスを味方に引きつけて、国連決議で旧西側国(自由民主主義国)に反対している」(森本敏氏=元防衛大臣・元拓殖大学総長)という指摘があるように世界の動きは複雑である。
そのグローバルサウス側は、「ウクライナ人は白人だから、米欧が助けた」、「米国がイスラエルを助けるのは二重基準(ダブルスタンダード)だ」と反発。
「このような一方的な二重基準を押し付けるのが民主主義か」と森本氏は問いかけ、「この問いに我々は正面から向き合わなければ、民主主義の正義を世界に訴えることはできない」と指摘しておられる。
日本自体も、混沌の中からどう国際秩序を導き出すのか。その使命と役割が問われている。
日米同盟で自らの生存権を確保しつつ、尖閣問題や竹島問題、そして拉致問題、北方領土問題などで中国、韓国、北朝鮮、そしてロシアとどう向き合っていくか。東アジアの情勢も緊迫度を増してくる中、日本の選択自身も問われている。
こういう国と国の対立が進む中で、企業と企業、人と人をつなぐのは経済人の使命と役割。技術力を駆使し「その国の人々に付加価値の高い商品を届ける。そのことに尽きる」(某経済リーダー)を基本に、今を生き抜き、〝つなぐ役割〟を発揮する使命が経済人に求められる。