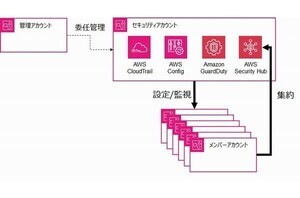アリババクラウドは3月5日、2025年の日本市場における戦略について記者説明会を開いた。同社はAIパートナーシッププログラムを開始してスタートアップ支援のためのAI開発ツールを拡充するとともに、国内でローカライズしたAIソリューションの展開を進める。
パートナーシッププログラムで国内のAI開発を支援
アリババクラウドが開始するAIパートナーシッププログラムでは、国内企業と連携して同社のLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)「Qwen」を中心とした生成AIソリューションの開発を推進する。
同社はプログラムの開始に先駆けて、AI検索エンジン「Felo」の開発などを手掛けるスタートアップSparticleとの提携を開始。日本国内でパートナーシップのエコシステムを拡大することで、Qwenシリーズを活用したAIソリューション開発を支援し日本企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)加速と成果の獲得を支援する。
新たに日本のカントリーマネージャーに就任した与謝野正宇氏は「スタートアップからエンタープライズまで、日本の幅広いエンドユーザーに最適なAIを届けたい。そのために、まずはコンサルティング企業と連携して日本のエンドユーザーの要望やAIの使用用途をヒアリングし、具体的なソリューションに落とし込んで開発を進めていく」と展望を示した。
Qwen2.5を国内向けにリリース
続いて、AI/ビッグデータソリューションアーキテクトの藤川裕一氏が、Qwenシリーズの最新版である「Qwen2.5」について紹介した。同モデルは0.5B~72Bまで複数のパラメータサイズで展開する。音声や動画の理解に対応可能なマルチモーダルなモデルに加え、プログラミングコード生成に特化した「Qwen-Coder」や数学問題の対処に特化した「Qwen-Math」など機能特化型のモデルも提供する。
Qwen2.5は大規模なデータセットで事前学習したモデルであり、最大18兆のトークンを保有。最大1M(100万)トークン長の入力までサポートしている。日本語、中国語、英語の他、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、イタリア語など、29以上の言語に対応。
藤川氏によると、Qwen2.5は前モデルのQwen2と比較し多くの知識を獲得したことに加え、プログラミングや数学の性能が向上しているという。さらに、8000トークン以上の長いテキストの生成が可能であるほか、JSONなど構造化データの入出力の能力も向上している。
機械学習アルゴリズムのデプロイと管理を支援するサービス「PAI-EAS(Platform for AI - Elastic Algorithm Service)」を活用すれば、モデルを東京リージョンにデプロイ可能。自社データを海外に持ち出すことなく国内で処理可能だ。
Qwen2.5はオープンソース版に加えて、クローズドなMoE(Mixture of Experts:混合専門家)版も展開。MoE版は最も高性能な「Qwen-Max」、小サイズながら100万トークン長まで対応可能な「Qwen-Turbo」、性能とモデルサイズのバランスを重視した「Qwen-Plus」の3モデルを提供する。
AI開発とサステナビリティの両立を強化
説明会では、アリババクラウドが実施した自主調査「テクノロジー・サステナビリティ・インデックス2024」の結果も紹介された。同調査は日本を含むアジア、ヨーロッパ、中東の13市場から計1300人の意思決定者を対象に行われた。
調査結果によると、日本の70%(世界平均75%、アジア平均75%)の回答者が、クラウドコンピューティングやAIなどのデジタル技術の導入が持続可能性目標の達成を加速させると回答した。その一方で、日本の75%(世界平均62%、アジア平均64%)がサステナビリティ目標の達成に向けてデジタル技術の導入が遅れていることを認識していることが明らかになった。
また、AIの導入に際して、日本の73%(世界平均61%、アジア平均66%)がエネルギー消費の高さがAI導入の障壁になり得ると回答したという。この結果に対し、与謝野氏は「水冷システムをはじめとするエネルギー効率の高いデータセンターの構築、エネルギーエキスパート(企業の事業活動や製品生産に伴う炭素排出量を測定し分析可能なSaaS)などのツールによる技術的なサポート、AIの学習および推論に必要なエネルギー効率の向上により、持続可能かつ環境に配慮した取り組みを進める」とコメントした。