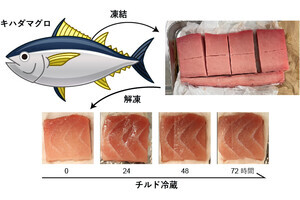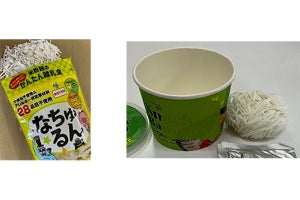北海道大学(北大)は2月7日、ミリサイズの具材を含む食品の流動物性を安定的に計測する手法を開発し、お粥に代表される流動食品の物性評価および流動予測に成功したことを発表した。
同成果は、北大大学院 工学研究院の大家広平博士研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、同・田坂裕司教授、同・村井祐一教授、北大病院 栄養管理部の熊谷聡美栄養士長らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する物質の変形と流動に関する学際的な分野を扱う学術誌「Journal of Rheology」に掲載された。
内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によれば、2023年10月1日現在の集計で、日本の総人口およそ1億2435万人に対し65歳以上の人口は約3623万人となっており(高齢化率約29.1%)、それに伴い、嚥下障害を抱える高齢者も急増中だ。そして、厚生労働省の「令和5年(2023)人口動態月報年計(概数)の概況」によれば、嚥下障害が関連する誤嚥性肺炎は前年より4000人以上増え、6万186人となっている。潜在的に嚥下障害を抱える患者数は、100万人にも達するという。
病院や介護施設の食事は、安全性を高めるために具材を細かく刻んだり、とろみを付けたりして提供されている。特に、お粥は一食のうち半分以上のカロリーを占める貴重な栄養源だ。しかし、その流動物性は食べやすくある一方で、誤嚥のリスクに直結することから、最適な流動食品を探求するため、客観的な数値として評価することが求められている。
これまで流動物性の評価に一般的に用いられてきたのが、「トルク式レオメータ」で、サンプルを幅1mmに満たない微小間隙に満たし、内部のひずみ速度(単位時間当たりのひずみの変化量)が一定であると仮定して、軸トルクと回転速度から間接的に粘度を求める手法である。しかし同手法は、サンプルが均質であることを前提としており、ミリサイズの具材を含むお粥のような流動食品を安定的に評価することを困難としている。そこで今回は、「流速分布計測支援型レオメトリ」(VPAR)を用いたという。
VPARは、二重円筒間にサンプルを満たし、外円筒を回転させることでサンプルに変形を与える。その際、内円筒に働く負荷トルクを計測し、同時に超音波を用いて円筒間の速度分布が獲得される。取得データが流体の運動方程式を介して解析され、それによって流動物性が評価される仕組みだ。具体的には、円筒間の各半径位置において変形速度と応力が数値化され、それらを組み合わせることで応力の変形速度依存性が評価可能となっている。従来のトルク式レオメータに比べて、ミリサイズの混合物を含む流体の計測が可能で、お粥や果肉入りヨーグルトなどの流動食品のみならず、気泡や液滴を含んだ各種混相流体、泥や化粧品なども適用範囲に含まれる。
今回の研究ではVPARを用いて、市販の白粥、玉子粥、小豆粥が計測された。その結果、白粥の粘度が最も高く、次いで小豆粥、玉子粥は最も低い粘度を持つことが示されたという。また、それらはどれもひずみ速度の増加に対して粘度が低下する性質の「シェアシニング性」を示し、嚥下食として優れた性質を持つことが流体力学の観点からも確認された。
さらに、得られた流動物性データを流れの予測に活用することを試み、摂食嚥下プロセスに関連して重要とされる、平板上での食塊の広がりと縮小部での流下速度を予測する、簡易的な物理モデルが提案された。そして、広がり距離と降下速度の予測は、実験データとの比較により検証され、一連の物性評価から流動予測までの妥当性が示されたとした。
今回の研究により、これまで定性的な評価に留まっていたさまざまな流動食品の計測が、VPARでなら可能になることが証明された。研究チームによると、同手法は特にミリサイズの混合物を含む不均質な流体に強みがあり、実際に病院や介護施設で提供されている嚥下食のデータベース化が可能となるため、医療現場で長年蓄積された知見と融合させることで、嚥下障害の度合いに応じた最適な流動食の選択に活用することが期待されるという。また、信頼性の高い流動物性データベースを摂食嚥下の予測シミュレーションに組み込むことで、食べやすさや誤嚥のリスクを予測し、安全性向上に貢献することも期待されるとしている。