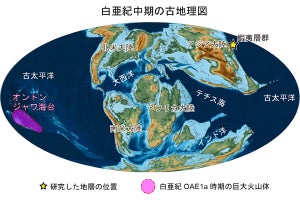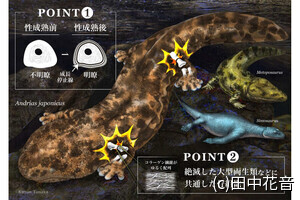京都大学(京大)は11月25日、赤潮による環境変化がラッコの捕食行動に与える影響を明らかにしたことを発表した。
同成果は、京大大学院 野生動物研究センターの三谷曜子教授、北海道大学 環境科学院のJackson Johnstone学部生、北大 北方生物圏フィールド科学センターの鈴木一平特任助教、米・テキサス A&M大学のRandall W. Davis教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米オンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。
北海道東部沿岸域(以下、道東沿岸域)はさまざまな漁業や水産業が盛んで、日本経済にとっても非常に重要な地域だ。この地域にはかつてラッコが生息しており、長い間絶滅していたが、2014年より繁殖個体が確認され、小さなグループのラッコが再定着しつつある状況となっていた。しかし、2021年10月に大規模な赤潮が発生。ウニ、軟体動物、各種二枚貝など、経済的に価値のある水産資源の大量死が赤潮の発生直後から確認されており、ラッコの主要なエサとなる生物もそうした底生生物であることから、ラッコへの影響が懸念されていた。またこの状況は、大規模な赤潮という前例のない環境撹乱にさらされた際に、ラッコがどのように反応し、今後さらなる環境撹乱に対してこの個体群がどの程度回復力を持つのかを研究するための、またとない機会となったという。
研究チームは、大規模な赤潮の発生前からラッコの捕食行動と底生生物の密度の定量化を行っており、今回の研究は2020年から2023年までの4年間の夏季に行われたそのデータがまとめられたもの。捕食行動は、双眼鏡を用いた船上目視調査が実施された(現地の漁師が操業するコンブ船を傭船して行われた)。
捕食行動の観測項目は、GPSの位置、潜水時間、餌の種類、餌の数、餌の大きさ、潜水間隔の6項目。底生生物の調査では、赤潮前(2020~2021年)、赤潮直後(2022年)、赤潮から1年後(2023年)の3つの期間における底生生物の密度が定量化された。ラッコが生息する調査海域が200m×200mのグリッドで20分割され、各グリッド内に4つの「コドラート」(正方形ないし長方形の枠を基盤の上に置き、その中の底生生物の個体数を数えたり、被度を見積もるための仕組み)が無作為に設置され、各コドラート内の餌生物の密度が計測された。
その結果、2022年の赤潮直後には、ラッコの捕食した餌生物からウニが完全に消失し(赤潮前:8%、赤潮直後:0%)、底生生物密度においてもウニの大幅な減少が確認されたという。しかしこうした影響は一時的で、ウニの捕食割合はさらに1年後の2023年には赤潮前のレベルに戻ったことが確認された(赤潮直後:0%、赤潮から1年後:14%)。そして、赤潮直後(2022年)に餌生物からウニが消失した結果として二枚貝の割合が増加し、赤潮前と比較するとほぼ倍増したとする。しかしウニの場合と同様、その1年後には二枚貝の割合も赤潮前の比率に戻ったとした(赤潮直後:67%、赤潮から1年後:38%)。
今回の研究により、主要な環境撹乱とそれがラッコの餌生物の密度に与える影響、そしてラッコが捕食する餌生物の構成との関係が明示された。また、大規模な赤潮による影響があったとしても、餌生物の構成の変化は一時的なものであることも示された。今回の赤潮では、個体群全体の健康状態への影響はほとんど観察されず、ラッコは餌生物の損失を、彼らが好む餌生物(二枚貝)をより多く捕食することに切り替えることで、十分に補完できたことが示されているとする。ただし、もし調査海域内の二枚貝がより深刻なダメージを受けていたとしたら、回復力はもっと低かった可能性もあるといい、さらなる調査によって、ラッコの採餌行動に、今後数年間にわたって続く長期的な変化があるかどうかが明らかになると考えているとしている。