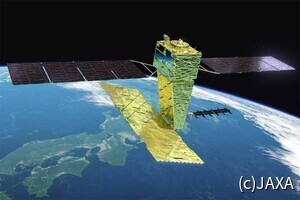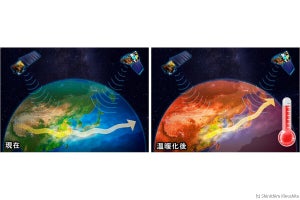九州大学(九大)は8月23日、陸域降水量観測および大気再解析データを併用し、台風本体の「コア降水」と、間接的な影響の「遠隔降水」を分離・同定する新しい客観的手法を開発して解析した結果、遠隔降水は西日本に大きなインパクトを与えていること、台風降水域で領域平均された日降水量が50mm以上の日数は今世紀に入って東アジアで2.2倍ほど急増していることなどを明らかにしたと発表した。
同成果は、九大大学院 理学府のJiwei Wu大学院生、同・大学院 理学研究院の川村隆一教授らの研究チームによるもの。詳細は、極端な気象と気候に関する全般を扱う学術誌「Weather and Climate Extremes」に掲載された。
地球規模の気候変動による災害リスクの変化を適切に評価するためには、気候システムの自然変動による変化も理解する必要がある。両者にとって台風の遠隔降水の定量的な評価が欠かせないことから、台風による豪雨災害の将来予測における不確実性の低減に貢献するだけでなく、台風がもたらす水資源の長期的予測にもつながるという。そこで研究チームは今回、台風が東アジアに最も上陸する7~9月に注目し、同地域全域にわたる台風による降水量および極端降水の長期変動傾向の実態を解明することを目指し、まずコア降水と遠隔降水を分離・同定する客観的手法を開発することにしたとする。
まずコア降水は、従来研究とも矛盾しない、台風中心から半径550km以内の降水域と定義するのが妥当と判断された。一方、遠隔降水の同定に明確な客観的基準はなかったとする。遠隔降水が顕著な事例では、コア領域と接続する非常に強い水蒸気フラックス(水蒸気の流れ)が観測される。その流れの下で局在化した強い降水域が頻繁に観測されることから、両者の密接な関係性に基づいて遠隔降水が同定された。具体的には、(1)6時間間隔の大気再解析データから見積もられる鉛直積算水蒸気フラックスが350kg m-1s-1を超える領域を抽出し、(2)同領域が台風中心から半径2500km以内にある場合を遠隔降水が生じる範囲と定義された。水蒸気フラックスの閾値は、「大気の川」の概念を活用。閾値を超えない領域では弱い降水域が散在する傾向にあり、ケーススタディでも台風の遠隔降水と判別するのはかなり困難とした。最後に、(3)遠隔降水が生じる範囲が東アジアの陸域に重なった時に、重なった領域内で降水があれば遠隔降水と同定された。その妥当性について半径2000~3000kmについての検証も行われ、今回の結論と変わらない結果を得られたという。
-

(a)東アジアに上陸した(または上陸しなかった)台風の月別個数(1979~2021年の気候平均)。(b)夏季に上陸した台風(赤線)、東アジアに上陸した台風(緑線)、上陸しなかった台風(青線)の個数の経年変動。(c)東アジアに上陸した台風(赤線)、上陸しなかった台風(水色)の経路分布。灰色の陰影は東アジア域が表されている(出所:九大プレスリリースPDF)
今回解明された主な知見は以下の3点。
- 台風による降水が、コア降水と遠隔降水に分離・同定された結果、遠隔降水は西日本と朝鮮半島に大きな影響を与えていることが判明。また、遠隔降水の変動度は日本では北海道地方が最大だった。
- 東アジアの極端降水に関しては、台風による降水が日降水量50mm以上(降水域で領域平均)の日数は、今世紀に入って東アジアで約2.2倍に急増しており、近年の台風による極端降水が増加傾向にあることが確認された。極端降水の増加にはコア降水が大きく寄与している一方、日降水量20mm以上50mm未満の大雨日数で見ると、遠隔降水は今世紀に入って60.8も増加していたという。
- 台風経路は太平洋十年規模変動と同期しながら、今世紀に入って大陸側にシフトしており、特に南西諸島や台湾付近を通過する台風が増加している。このシフトにより、結果的にコア降水が陸上の極端降水に大きく寄与したことが考えられるほか、遠隔降水の急激な増加とも密接に関連していることがわかった。
-

東アジア夏季における台風による降水(コア降水+遠隔降水)日数の経年変動。赤線は日降水量50mm以上の極端降水の日数を、青線は中程度(日降水量20mm以上50mm未満)の降水日数の変動が表されている。ここでの日降水量は、台風による降水と同定された陸域で領域平均された値。日降水量の95%パーセンタイル値(緑破線)も併せて示されている(出所:九大プレスリリースPDF)
今後は台風災害のリスクアセスメントに大きな貢献が期待できるとする。今回の研究成果から、太平洋十年規模変動などの気候システムの自然変動による台風災害リスクの長期的変化と、温暖化の進行によって予想される台風リスクの将来変化を適切に区別する必要性が再認識されたという。
-

Epoch1(1979~1996)とEpoch2(1997~2021)における台風経路の空間密度分布図。右は両期間の差(Epoch2-Epoch1)。黒い点は統計的に有意な地域を示している(出所:九大プレスリリースPDF)
また遠隔降水においては、メソスケールの線状降水帯もしばしば発生する。親システムである台風から、より小さなスケールの極端現象(子システム)への連鎖の評価の必要性、つまり豪雨災害ハザードの予測には現象の階層構造の把握と予測が必須であるとした。子システムへ連鎖することで、激甚化したような甚大な災害が多数発生している事実から、この連鎖プロセスの理解が重要な課題として残されている。今後、数年~10年スパンで地域の豪雨災害ハザードが増大(あるいは緩和)する可能性を予測するためには、近未来予測の不確実性を低減させる上での大きな障害となっている「極端現象へ連鎖していくか否か」という重要かつ喫緊の課題を克服していく必要があるとする。今回の成果は、その課題解決にも活用されることが期待されるとしている。