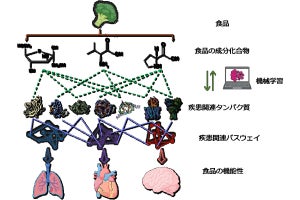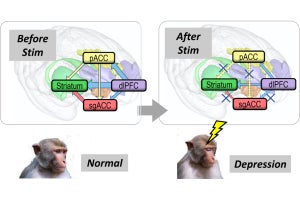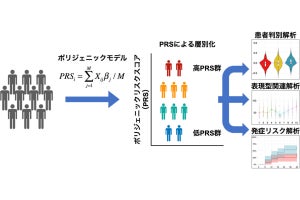東北大学は7月12日、「ロイシン」や「イソロイシン」などの必須アミノ酸を含むパターン、もしくは「グルタミン」や「セリン」などの非必須アミノ酸を含むパターンを相対的に多く有しているグループでは認知機能が低下している者の割合が低く、一方、「アセトン」などのケトン体(脂肪の合成や分解の過程で産生される、中間代謝産物)を含むパターンを相対的に多く有しているグループでは、認知機能が低下している者の割合が高いことが明らかになったと発表した。
同成果は、ToMMoの小柴生造教授、同・寳澤篤教授、東北大 学際科学フロンティア研究所の木内桜助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本液学会が刊行する健康に関する疫学と社会医学に関する全般を扱う欧文学術誌「Journal of Epidemiology」に掲載された。
認知症は要介護状態となる主な原因の1つであり、特に超高齢社会に突入している日本においては、その対策は喫緊の課題となっている。これまでに欧米などにおいて行われた研究では、血漿中の代謝物と認知機能の低下との関連が示唆されており、代謝物は認知機能の低下の予測因子となりうることが示されていた。しかし欧米人とアジア人では肥満率や食生活が異なるため、代謝物の組成が欧米人とアジア人とでは異なる可能性があった。そのため、アジア人を対象とした研究が望まれていたが、これまで研究例はほとんどなかったという。そこで研究チームは今回、ToMMoが2013~2016年に実施した地域住民を対象としたコホート調査のうち、宮城県在住の60歳以上のデータを用いた横断研究を行うことにしたとする。
今回の研究では、核磁気共鳴分光法を用いて代謝物の測定が行われ、43種類の代謝物を説明変数とし、代謝物に対してデータの特徴をまとめる解析手法として主成分分析を用い、パターンの特定が行われた。従属変数は、ミニメンタルステート検査で評価された認知機能低下(23点以下)の有無とされた。統計解析を用いて関連する要因(性別、年齢、教育歴、BodyMassIndex、糖尿病、高血圧、身体活動(歩行時間))の影響が除外され、代謝物のパターンごとの、パターンの得点1点あたりの認知機能低下のオッズ比と95%信頼区間が算出された。
合計2940人の参加者(男性:49.0%、平均年齢:67.6歳)のうち、1.9%に認知機能低下が見られた。多変量解析の結果、必須アミノ酸を含むパターンは、得点が高いほど認知機能の低下者の割合が低く、ケトン体を含むパターンは、得点が高いほど認知機能の低下者の割合が高いことが判明。一方、非必須アミノ酸を含むパターンは、得点が高いほど認知機能が低下者の割合が低いことが明らかにされた。これらの結果は、欧米の先行研究の結果を裏付けるものだったという。
今回の研究により、日本人(アジア人)においても血漿中の代謝物と認知機能の関連が示された。今回の研究は横断研究のため、代謝物の特徴が認知機能の低下の原因なのか結果なのかは不明だが、原因であるとすればバランスの取れた食事などから、必須アミノ酸を維持することが認知機能の維持に効果的である可能性が考えられるとした。
また研究チームは今後、長期の追跡調査により、ある時点の代謝物のデータがその後の認知機能の変化を予測できる可能性について検討を行っていく予定とする。将来的には代謝物を指標とした介入研究の実施も必要と考えられるとした。血液サンプルを用いた認知機能低下の予測は、侵襲性の低い認知機能評価ツールの開発に発展する可能性があるとしている。