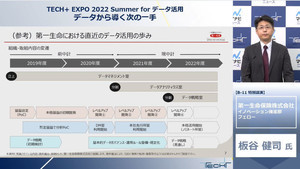近年、日本のプロ野球界でデータ活用の波が加速している。球場に設置された数々のデバイスから打球速度、回転数などのデータが取得できるようになり、選手のパフォーマンスが可視化された。一方で、データをどのように現場に活かしていくのか。その答えを見出すのは容易ではない。
そんな中、今季から埼玉西武ライオンズに新設された「データ戦略室」のチーフに就任したのが、国内外のプロ球団で分析官を歴任した西秀幸氏だ。米国の大学でデータをもとにした野球チームの経営や戦略について学び、帰国後は国内大手メーカーに勤務。その後、横浜DeNAベイスターズでのデータ分析者の公募を見つけたことを機に、2018年からデータ分析官として野球界へ。データのプロフェッショナルとして、野球界におけるデータ活用を推し進めている。
組織全体で一貫性のあるデータ活用を目指す
ライオンズには、データの扱いに長けたスタッフが各部署に在籍している。例えばスコアラーは、相手選手の細かなデータを収集・分析し、バイオメカニクス担当者は選手の動作を解析する。ただ、彼らがそれぞれ独自の観点からデータを集めて現場に提示しても、断片的な情報になりがちだ。そこで西氏は、組織全体として一貫性のあるデータ活用を行っていくための土台作りに注力している。
西氏のミッションは、球団内に存在するあらゆるデータを一元化し、誰もがアクセスできる基盤を整備すること。球場内に設置された各センサーやInBodyと呼ばれる体成分分析装置、ウェアラブル端末など、データソースは多岐にわたる。それらを1カ所に集約し、選手はもちろん、コーチから分析担当、フロント職員までが、同じデータにアクセスできる環境の構築を目指している。
具体的には、クラウド・データプラットフォーム「Snowflake」を使ったデータ基盤を構築中だ。各測定ツールから取得されたデータは一旦各システムのクラウドストレージ上にアップされ、そこからAPI経由でSnowflakeに取り込まれる仕組みになっている。
「まずはスモールスタートで、スコアラーやバイオメカニクス担当者などデータに関わるスタッフに展開していますが、将来的には、現場レベルで仮説を立て、それを検証できるようにしていきたいです。例えば、コーチが『この選手は、こういう球種だと打ちにくいのでは?』と感じたら、その場で過去のデータをさかのぼって傾向を確認する。もしくは、分析担当者が新しい指標やツールを開発したら、すぐにチームで共有して現場からフィードバックをもらう。そんな風に、データを介して組織内でナレッジが循環する状態をつくりたいですね」(西氏)
データ活用の「切り口」が他球団との差別化につながる
ライオンズが2016年に導入した「トラックマン」は、投打におけるボールの回転数や変化量を計測する装置だ。2020年導入の「ラプソード」は、球の縫い目の動きをもとに回転軸を分析し、3次元で動きを確認できる。2024年導入の「ホークアイ」は、8台の専用カメラでグラウンドにいるすべての選手や球の動きを捉えるものだ。
現在、ライオンズに限らず、トラックマンやホークアイなどの測定機器を導入している球団は多い。ホークアイを導入済みの日本野球機構(NPB)所属球団には、全球場全試合の測定結果がシェアされる仕組みだ。すなわち、インプットはほぼ横一線なものの、それらをいかに分析して活用するかが、他球団との差別化要因となる。
「野球の分析においては、どのような手法を用いるにしても大前提となる情報があるので、少なくともそれらの基本的なデータはすべて構築中の基盤に取り込もうとしています。こうしたデータを利用すると、例えば、ピッチャーのピッチングの価値を定量化する、選手のスタッツデータをもとにどれくらいの成績を残せるか“期待値”という形で求めるなどの分析ができるようになります」(西氏)
現在は、「フレーミング」と呼ばれる捕手の技術の定量化にチャレンジしているところだという。ストライクゾーンギリギリの投球をいかにストライクに見せるか。その巧拙がゲームの流れを左右する。西氏は「ストライクゾーンのデータと実際の投球位置が数値化されたデータを使えば、どの捕手がどのゾーンでストライク/ボールと判定されたかがわかる。これにより、その捕手の捕球技術のレベルが見えるようになる」と説明する。
また、ライオンズが独自に取り組んでいるのが、打者の視線データの分析だ。VRデバイスと3D映像を使ってシミュレーションを行い、打席での選手の目の動きを可視化。その知見をもとに、打者ごとの特徴に応じたトレーニングメニューの考案につなげていきたい考えだ。
次のステップとして、選手の獲得やスカウトを行う編成部門でのデータ活用も視野に入れているという。特に選手の評価手段としてデータは有用だ。例えば、選手の除脂肪体重と打率には因果関係があるとの傾向も見えてきている。脂肪を除いた体重は、筋肉量の多さを表す。筋肉量が多いとバットを振る力が強くなるため、打球速度が速くなり、ヒットが出やすくなる。西氏は「私たちが提示するデータのメリットをわかりやすい形で伝えることで、編成部門の意思決定の役に立てていきたい」と意気込む。
西氏はファーストアプローチとして、月に一度開催されている編成関連のミーティングに出席して、データ活用の提言をしているという。スポーツの世界では、勘や経験が重視される文化も根強く残るが、ライオンズでは球団全体としてデータ活用に前向きで、快く受け入れてもらえているそうだ。
「データ戦略室はデータを活用していきたいという球団全体の意識のもとに設立された部署なので、スタッフ陣への説明のハードルはそこまで感じていません。編成部門からは『自球団の選手のデータと比較して他球団の選手を評価してほしい』といったリクエストをもらうこともあります」(西氏)
実際の試合や練習でデータを応用するには?
データ基盤の整備やスタッフ陣のデータ活用への理解は進む一方で、データやその分析結果を実際の試合や練習でどう使ってもらうかは引き続き大きな課題となる。現場でデータを活用していくための風土づくりも西氏のミッションだ。
例えばプロの世界では、自分のパフォーマンスを数字で表されることに抵抗感を持つ選手も少なくないという。良くない数字を見て苦手意識が生まれたり、型にはまった判断に陥ったりと、プレーに支障をきたす選手もいるからだ。西氏によると、データを開示するにも配慮は必要という考えから、データの提供の仕方は個人に合わせて変えているという。
「データを扱うリテラシーの高い選手に対しては、コーチに『この選手にデータを提示してみてはどうか』と提案することもあります。特に、個人でデータサイエンティストを契約しているような選手には、より高度なデータを提供してもおもしろいかもしれません」(西氏)
また、野球においては、表面上の数値だけを見て判断しないようにすることも大切だという。
「点差、相手ピッチャー、ランナー、カウントなど、その時々の状況が勝敗を大きく左右する野球は、コンテキストが複雑なスポーツといえます。データ上では差があるように見えるものの、深堀りして分析すると、実はそこまで差はなかったということも十分ありえます。野球を分析する際には、表面上の数値だけを見て『差がある/効果がある』と判断するのではなく、コンテキストを理解したうえで、隠れた事象までもしっかり見ていくことが重要です」(西氏)
データ駆動型野球のカギは、現場発の仮説検証と専門人材の確保
「将来的には、選手やコーチなど、現場の人々が自分で仮説を立てて分析できる環境を整備していきたい」と語る西氏。「現場は、『こういうケースにはこういう対応が有効なのでは』『この選手は実はこういう動きをしているのでは』といった仮説を思いつきやすい状況にあります。そういう方々がアイデアを持ったときに、すぐに簡単に分析できるような環境が理想」と展望する。
そうした環境を実現するには、統計的手法の知識・技術を持つ専門人材の確保も重要な取り組みのひとつだ。西氏は今後、「編成、戦略、育成など分野に特化したデータサイエンティストを各組織に置くことを目指していきたい」と語る。
西氏の視線の先には、データを起点とした組織変革の姿がある。データ基盤の構築を土台に、現場発の仮説検証を促進し、部署間の垣根を越えた議論から新たな発想を引き出していく。そして、経験と勘に加え、客観的なデータを根拠に戦略を立てることを当たり前にしていく。そんなデータ駆動型野球の到来に向けて、西氏のチャレンジはこれからも続く。