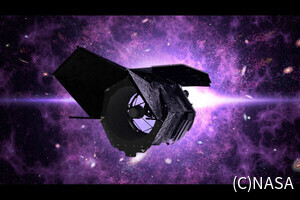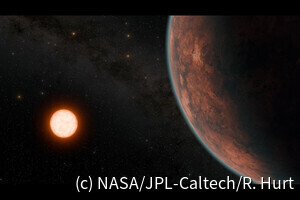千葉工業大学(千葉工大)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、国立天文台(NAOJ)の3者は6月26日、現在、海王星の外側に広がる「エッジワース・カイパーベルト(カイパーベルト)天体」を探査中のNASAの探査機「ニュー・ホライズンズ」の探査天体候補を探すため、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam」(HSC)で撮影されたカイパーベルト天体の探査画像に独自の解析手法を適用した結果、カイパーベルト領域を広げる可能性のある天体を発見したと発表した。
同成果は、千葉工大 惑星探査研究センター 非常勤研究員の吉田二美博士(産業医科大学 医学部 准教授兼任)、NAOJ 天文シミュレーションプロジェクトの伊藤孝士講師らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する欧文学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。
-

今回発見された2天体の軌道を示す模式図(赤色:2020 KJ60、紫色:2020 KK60)。+は太陽の位置、黄緑は内側から木星、土星、天王星、海王星の軌道。縦軸と横軸の数字は太陽からの距離(天文単位)。黒点は太陽系初期にその場で形成された氷微惑星群と考えられている古典的なカイパーベルト天体を表し、それらは黄道面付近に分布している。灰色の点は軌道長半径が30天文単位以上の太陽系外縁天体を表す。これらは海王星に散乱された天体も含まれるため、遠くまで広がっており、多くは黄道面から離れた軌道を持つ。図の丸や点は2024年6月1日時点での位置が表されている(c)JAXA(出所:すばる望遠鏡Webサイト)
海王星(太陽からの距離は約30天文単位)からさらに外側の50天文単位ぐらいまでは、小惑星などの小天体がリング状に分布した第2の小惑星帯ともいうべきカイパーベルトがある。この海王星軌道から、カイパーベルトを含め、「オールトの雲」(巨大惑星が弾き飛ばした微惑星が太陽を中心として球殻状に分布していると推測されている)の最外縁部のおよそ10万天文単位(=約1.6光年)ぐらいまでは、「太陽系外縁部」と呼ばれている。
現在の観測からはカイパーベルトの外端は50天文単位ほどで突然途切れているように見え、もし本当に太陽系がそこまでだとすると、これまでに観測されている多くの原始惑星系円盤の半径が100天文単位ほどあることから、太陽系はとてもコンパクトな状態で生まれたことになる。しかし観測できていないだけで、原始太陽系円盤は、ほかの原始惑星系円盤同様にもっと外側まで続いていた可能性もあるという。
またカイパーベルトの外端は、その外側の天体(惑星)の影響を受け、進化の過程で切り取られてしまった可能性もあるという。もしそれが本当なら、カイパーベルトのさらに遠方を観測すれば円盤を切り取った天体や、第2のカイパーベルトが見つかる可能性もある。このように太陽系外縁部にある天体を見つけ、その分布を調べることは、太陽系の進化を知る上で重要だ。
ニュー・ホライズンズは2015年に冥王星系をフライバイ観測して大きな成果を挙げた後、現在はカイパーベルト天体の観測を実施中。2019年には「アロコス」をフライバイ観測し、史上初となる太陽系外縁天体の表層の撮影を行った。その後もミッションは延長され、ニュー・ホライズンズが今後調査可能なカイパーベルト天体の候補を探すため、すばる望遠鏡も協力することにしたという。
すばる望遠鏡のHSCを用いたカイパーベルト天体探しは、ニュー・ホライズンズが飛行する方向の2視野分(満月のおよそ18個分の広さに相当する領域)に絞って行われている。これまでに行われた約30半夜の観測で、ニュー・ホライズンズのサイエンスチームは、240個以上の太陽系外縁天体を発見したとする。
そして今回の研究では、上述の観測により取得された画像を、吉田博士らを中心とする研究チームが、サイエンスチームとは異なる手法で解析し、新たに7個の太陽系外縁天体を発見したとした。決まった視野を一定期間撮り続けたHSCの観測データに対し、普段は近地球小惑星やスペースデブリの検出に使われている、JAXAが開発した「移動天体検出システム」を適用できることがわかったという。
-

JAXAの移動天体検出システムでの検出例。一定の時間間隔で同一視野を撮像した32枚の画像(オレンジの枠内の画像)から移動天体を探していく。カイパーベルト天体の移動速度範囲を仮定して、1枚1枚の画像をいくつもの方向に少しずつずらしながら重ね、うまく32枚重なったものを候補天体とする。図中の緑枠、水色枠、黒枠の画像はそれぞれ、2枚ずつ、8枚ずつ、そして32枚を重ねた画像。1枚の画像でも、どの重ね合わせでも、中心に天体らしき光源があった場合は本物の天体と判断される(c)JAXA(出所:すばる望遠鏡Webサイト)
同システムは、32枚の連続した画像をいくつもの方向にずらして重ね合わせることにより、特定の速度で移動する天体を検出するというもので、高速処理のために独自の工夫がなされているとする。新発見の7天体のうちの2天体については大まかな軌道が求められ、すでに国際天文学連合の小惑星センターから仮符号が付与されているとした。
上述したように、従来の研究ではカイパーベルト天体の数が50天文単位辺りから急減するため、カイパーベルトの外縁がその辺りにあると想像されていた。しかし、今回の仮符号を与えられた2天体の軌道長半径は、どちらも50天文単位以上だという(ただしこれらの天体の軌道要素は、将来的に観測が蓄積するにつれて多少変動する可能性がある)。今後も似たような軌道を持つ天体の発見が続けば、カイパーベルトはさらに先まで続いていることがわかるかもしれないとした。
すばる望遠鏡とニュー・ホライズンズの連携により、まだ人類が観測できていない太陽系深縁部の探査が進むことが期待されるとしている。