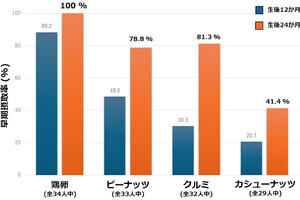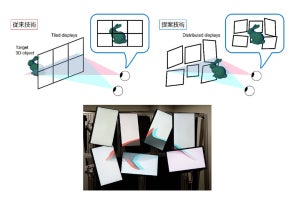高知大学は6月24日、しあわせ推進会議(高知市)および高知県下3市町教育委員会の協力を得て、小中学生511人を対象に「好奇心からの問いかけ」、「年少者や自然環境への労わり(改訂版の将来世代への関心度)」、そして「主観的幸福度」の関係についてタブレット端末を利用したWEBアンケート調査を実施し、併せて子どもと大人の世代間交流の重要性に注目して子どもが「好奇心からの問いかけ」をした際の大人の対応態度に関するデータを収集して分析した結果、子どもからの「問いかけ」に対し、「大人からポジティブな対応を受けた経験」を認識する子どもからは「好奇心からの問いかけ」および「主観的幸福度」が高い傾向があることが確認されたと発表した。
さらに、大人のポジティブな対応は子どもの「好奇心からの問いかけ」の傾向を促進し、さらにそのことが子どもの「主観的幸福度」の高さと関係することもわかったと併せて発表された。
同成果は、高知大 教育研究部 総合科学系 地域協働教育学部門の廣瀬淳一准教授(高知大 安全・安心機構 男女共同参画推進室 室長兼任)によるもの。詳細は、米オンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。
近年、子どもの幸福度が注目されている。2022年に実施された日本の成人を対象とした研究において、“好奇心からの問いかけ”の傾向と「将来世代への関心度」および「主観的幸福度」の高さとの関連性についての報告がなされていた。しかし、子どもの好奇心からの問いかけ・将来世代への関心度および主観的幸福度と世代間交流との関係については、あまり知られていなかったという。
そこで廣瀬准教授は今回、小中学生を対象に「年少者や自然環境への労わり(改訂版の将来世代への関心度)」、そして主観的幸福度の関係について、タブレット端末を利用したWEBアンケート調査を行ったとのこと。また、子どもと大人の世代間交流の重要性にも注目し、子どもが好奇心からの問いかけをした際の大人の対応態度に関するデータ収集された。
そのデータ分析の結果、子どもからの問いかけに対し、「大人からポジティブな対応を受けた経験」を認識する子どもからは、好奇心からの問いかけおよび主観的幸福度が高い傾向があることが確認されたとする。さらに、大人のポジティブな対応は子どもの好奇心からの問いかけの傾向を促進し、さらにそのことが子どもの主観的幸福度の高さと関係することも判明したという。
この結果は、2022年の大人を対象とした研究と同様に、好奇心からの問いかけの傾向が、小さな子どもや自然環境への労わりにおいても強く関係することが確認された形だ。ただし大人の場合は、将来世代への関心度と主観的幸福度の間に強い関係があることが報告されていたが、子どもの場合は主観的幸福度と将来世代への関心度の改訂版の間には“芽生え”といえる程度の小さな関係性のみ確認できたとする。つまり子どもの時点においては、次世代への関心度よりも大人からのポジティブな対応や好奇心からの問いかけのサイクルの方が重要であることが示唆されているという。
廣瀬准教授は今回の研究結果から、子どもの幸福度を考える時は、子どもの好奇心からの問いかけに対して大人が面倒くさがらずに対応することで、世代間問答の良いループを作ることが大切である可能性を指摘できるとする。また過去の研究では、将来世代への関心度が高い大人の側にも主観的幸福度が高い傾向が報告されていたことから、世代間問答の良いループは、大人への問いかけに対してちゃんと答えてもらった子ども、子どもからの問いにしっかりと応えようとした大人の双方の主観的幸福度を高める可能性があるとしている。