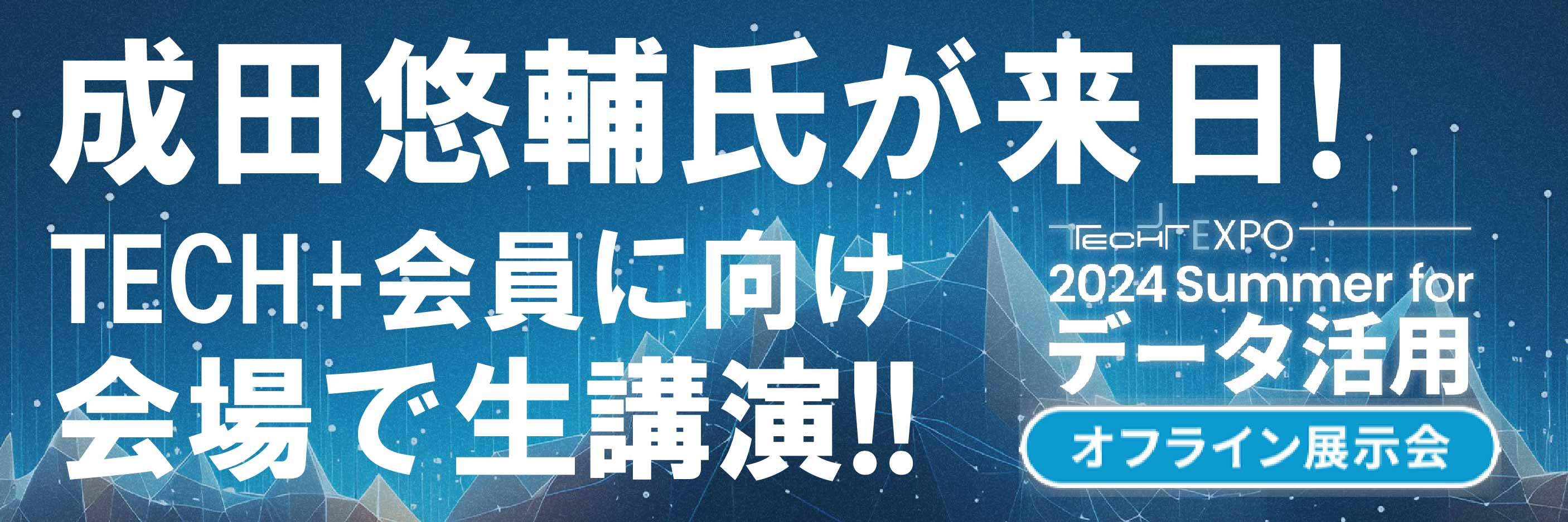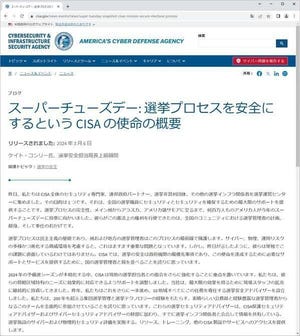Amazon(アマゾン)では2017年から、BtoB事業として「アマゾンビジネス」を展開している。購入方法などが一般向けのアマゾンとほぼ同様で使いやすい点や、一般向け同様に、豊富な商品ジャンルを取りそろえている点が、需要拡大につながっているようだ。通常のプライム会員であれば、アマゾンビジネスで同様のサービスを受けられるプランもある。そのため、大企業だけでなく、中小企業や個人事業主からも、高い需要を獲得しているようだ。アマゾンビジネスのサービスと、今後の展望について、Amazonビジネス事業本部の事業本部長を務める石橋憲人氏に話を聞いた。
――BtoB事業の始まりは?
当社のBtoB事業「Amazonビジネス」は、日本では2017年に始まった。
もともと、企業や個人事業主が、業務用にアマゾンを使っているというニーズがあった中、できたサービスだったこともあり、立ち上げ当初から受け入れてもらえたと感じている。
日本の企業は、海外とは違い、1回1回代金を支払うのではなく、月末などにまとめて支払うケースがほとんどだ。日本独自の「月末締め翌月払い」といったシステムへの対応には、当社も注力している。
企業によって締め日が異なるケースがある。そのため、月末以外にも、5、10、15、20日といった締め日にも対応できるようにしている。
請求書の宛先についても、サービス開始当初は、1社に対して1本しか出せなかった。現在は部門ごとに出せるような仕組みとなっている。
<地道な情報収集を>
――企業の要望に応える細かいサービスはどうやって生まれるのか?
顧客が何を求めているかは、顧客の声を聴くのが一番だ。だからこそ当社も、情報収集には力を入れている。
担当者が顧客を訪問して、直接声を聴くというのは、サービス開始当初から徹底している。私自身が、声を聴きに行くこともある。
SNSでの情報収集も行っている。Xで、「アマゾンビジネス」で検索して出てくる投稿を全てチェックしている。「会社が導入してくれて便利になった」といったポジティブな意見もあれば、もちろんネガティブな意見もある。そういった意見を集計して、毎週、顧客の声と共に共有し、改善を進めている。
<国立大学の90%が登録>
――どういった企業がアマゾンビジネスを活用しているのか?
アマゾンビジネスでは、複数のビジネスプライム会員プランを用意している。一番安いプランである「DUO(デュオ)」は、個人アカウントでプライム会員に登録している人であれば、誰でも無料で使える。中小企業や、個人事業主向けのプランだ。お急ぎ便や、お届け日時指定便といったサービスも利用可能だ。
「デュオ」の利用は1ユーザーのみだが、企業のユーザー数に合わせ、段階ごとのプランを用意している。一番大きいプランである「UNLIMITED(アンリミテッド)」は、ユーザー数無制限となっている。
多様なプランがあるため、個人事業主から、中小企業、大企業に至るまで、幅広い規模の会社に利用いただいている。
例えば、日本にある国立大学の90%が登録をしている。主に、大学教授が、アマゾンビジネスで商品を購入している。国立大学での購入は、国家予算になるため、経費の〝見える化〟がとても重要だ。
アマゾンビジネスでは、「どの教授が」「いつ」「何を買った」をすぐ把握することができる。購買の方法も、通常のアマゾンと変わらないため、「使いやすい」との声を数多くいただいている。
<意外な売れ筋商品>
――BtoBでは、どのような商品が売れるのか?
最も売れているのは、文房具やPC周りの商品。休憩室で使用する商品や、来客時に使用する水など、いわゆるオフィス用品だ。
それ以外にも、工場で使用する、安全靴や手袋、センサー、スイッチなど、個人ではなかなか買わないようなものも取りそろえている。
国立大学からは、大型書店に行かないと買えないような、洋書の注文が入ることもある。
アマゾンビジネスを利用している地方の介護施設からは、「笹」が買えて助かったとの声もいただいた。
その施設では毎年、七夕の時期になると、2人で30分かけて、ホームセンターまで笹を買いに行っていたそうだ。延べ2時間かかっていたという。それがアマゾンビジネスで笹が売っていたことで、作業時間を大幅に削減できたと言っていた。
介護施設以外にも、実店舗のディスプレイなどで、あまり売られていない商品を必要になるときはあるだろう。そういった細かい需要にも対応できるのも、アマゾンビジネスの強みだと思っている。
飲食店では、バックヤードのスペースがなく、消耗品などの在庫を置いておくのが難しいケースがある。アマゾンビジネスであれば、翌日に商品が届くので、消耗品などの在庫を持つ必要がない。バックヤードのスペース削減にもつなげることができる。店舗の小口現金をなくしたり、減らしたりすることもできるので、リスクヘッジにもなる。特に多店舗展開している企業からは、高い需要がある。
<多角的な選びやすさを>
――今後のサービス展開で考えていることは?
グローバルでは、企業が物を購入する際の「社会的責任」が重要視されている。例えば、CO2の削減だ。購入する商品に、環境ラベルを表示する取り組みは、米国などですでに始まっている。
商品の購入を通じて、「1年間でどれくらいのCO2を削減できたのか」が分かるようになれば、企業としても商品を選びやすくなるだろう。
2022年からは、購入先の企業の所在地を、ソートする機能を追加した。
地方の企業であれば、「同じ地方の企業から購入したい」「地域に貢献したい」という思いを抱く企業が多い。これも「地元企業のものを買いたい」という顧客の声から生まれたサービスだ。
幅広い需要に対応する商品数を取りそろえるのはもちろん大事だが、その幅広い商品から、買いたいものを選んでもらいやすくすることが、今後は重要になってくる。
今後も顧客の声を地道に集め、「誰もが使いやすいアマゾンビジネス」にしていけたらと思う。