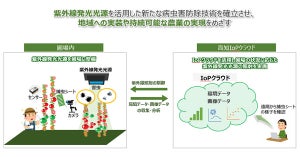農業従事者の高齢化や減少、栽培面積の減少、食料自給率の低下など、悲観的なトピックが多い日本の農業は昨今、根本的な変革を迫られている。そんな中、日本は国家として「農業DX構想」を掲げ、農水省を中心にAIなどを活用した「データ駆動型農業」の普及を急いでいる。
データ駆動型農業を推進する民間企業の先駆けとして知られるのが、宮崎市に本社を置くテラスマイルだ。「すべての営農者を豊かにし、国家を守ることを創造する」をミッションに掲げ、2014年の創業以来、農業分野におけるデータ分析を行ってきた。
2017年には農業データ情報基盤「RightARM(ライトアーム)」を開発し、2024年5月時点で、国内23都道府県で農業データ活用基盤を提供する。さらに、2022年には営農指導員、農業普及員向けサービス「RightARM for Ex」の提供を開始。農業情報基盤を通じて、営農者・産地形成者を支援している。
「約10年後、日本は大きな危機を迎えます。高齢化社会がさらに進み、日本人の10%が認知症になるという予測はよく知られています。これは農業の高齢化に直撃します。加えて労働人口が国民全体の3分の1に減少する社会がやってきます。食料自給を支えられる農業現場の効率化・自動化は喫緊の課題で、私たちが取り組むことで未来を変えていきたいです」
そう語るのは、テラスマイル 代表取締役の生駒祐一さん。2023年9月にはヤンマーグループのヤンマーベンチャーズなどから3億3000万円の資金調達を実施し、RightARMのさらなる普及を進めている。ここまでの歩みとこれからのことを聞いた。
データを元に農業経営を加速させる
前出のRightARMは農業を取り巻くあらゆるデータをクラウド上で一元化・分析し、収穫量の増加や市場評価の高い出荷時期など、経営判断に活用できる情報のアウトプットを行う、農業経営者向けの経営管理クラウドサービスだ。
農業経営者が栽培記録を入力すると、各種生産管理システムや気象データなどの外部データが自動で連動し、RightARMの分析基盤で処理されると、データは活用できる形へと変換される。経営判断に用いる情報の切り口は、同社の行った過去のコンサル実績に基づく独自ノウハウを用いて導き出される。
分析結果は簡単な操作で出力でき、洗練された見やすいデザインとグラフとなり、農業経営者はデータを使って「売り上げや利益を上げるための農業」を考えることに、より多くの時間を割くことができるようになる。
しかし、デジタルとの親和性が低かった農業業界で、デジタルツールの導入を進めるには、良いプロダクトを作って提供するだけでは十分とはいえない。RightARMを契約・提供後、農業経営者の課題の顕在化から目標設定、仮説・検証を繰り返して成功体験へ持っていくところまでテラスマイルが伴走する体制を整えている。
「RightARMを活用すると、データですべてが見える化されます。何をどの時期に作ると収穫量が増えて一番儲かるのか、逆にどの時期に作ると無駄になるのかなどが一目瞭然です。データを元に動けば結果が出て、コストも減らせて、売り上げも利益も増える。それを実感いただけた農業経営者の方は成果を上げています」(生駒さん、以下同)
稼げるポイントを月次で把握する一般企業では当たり前の経営の見える化。経験と勘が主流だった農業業界にそれを持ち込むことで、本来1年1作分の経験だった農業を、データをもとに仮説と検証を行って、期中も含めた改善・目標達成をサポートしているのだ。
「利益を出す方法が分からない」現実に課題意識
ここでテラスマイルを率いる生駒さんのバックボーンについて触れたい。データ活用領域に強みを持つ生駒さんは大学卒業後、ITやロボットなどの新規事業に携わっていた。2010年にMBA取得後、2011年からはITから農業へと活躍の舞台を大きく変え、3年に渡って宮崎の大規模農園の運営に携わった後、テラスマイルを創業している。
RightARMの開発に至るきっかけとなる出来事があった。2011年、当時勤めていた東京のIT企業が宮崎の農業支援プロジェクト運営に携わることとなり、生駒さんは年間200トンのミニトマトを生産する農園にマネージャーとして派遣された。そこで驚いたのは問題が起きたとき、農業経営者に何を質問しても「分かりません」と返されることだった。
「これまでは組織の中で問題が起きると、関係者同士で『~が理由で~だった』『だから、~をして問題解決しよう』とロジカルなやり取りをしていました。仕事をする上で、それは当たり前の作法だと認識していたのです。しかし、農業の現場では『分かりません』という言葉が普通に出てきてしまい、そこで終わってしまう状況に戸惑いました」
その経験が、農業のPDCAサイクルを高速で回し、出てきたデータを蓄積し、分析していく行動へとつながり、さらにRightARMのアイデアへと発展していく。
もう1つ、驚いた文化があった。「農業=作物を栽培すること」と捉えているのか、ある程度うまく作っていれば、一定の収入を得られるからなのか、作ったものを売っていく過程で、販路や売上・利益を増やす方法を考えない農業経営者が多かったことだ。
そんな状況を間近で見ていて、農業経営者自身が利益を出す方法を分かっていないこと、ひいては追い求めようとしないことに、生駒さんは大きな課題意識を抱いた。
RightARM開発前、そういったネガティブ面に触れる機会もあったが、一方でポジティブな出来事もあった。ある農業経営者から打ち明けられた「自分の考えやノウハウをデータで見える化して次の世代に伝えたい」との想いは、より良いシステムを生み出そうとする起爆剤になった。
「創業者が課題感として持っているのは、自身が経験してきたことを同じ目線で人に伝えること、言い換えると経験の見える化をすることが難しい点です。家業は三代で潰れることを言い表した『売り家と唐様で書く三代目』という諺がありますが、初代がやってきたことがうまく伝わらずに衰退してしまうのが、人間のメカニズムなのだと思います」
そこを補完するのがRightARMであり、テラスマイルが持つデジタルと現場とを融合させた“農業情報基盤”といえる。
データを活用したスマート農業の成功事例
ここで、RightARMを導入し、データを活用したスマート農業を進め、現場の改善に成功した3つの事例を紹介しよう。
1つ目は東海大学の卒業生が3人で立ち上げた農業法人(鹿児島)だ。近年、大根の生産地において、西日本最大級となった。3人の力で東京ドーム40個分くらいの耕作地にまで拡大したが、経験の見える化ができていないことに課題を抱えていた。
2018年からRightARMを活用した取り組みを始めて現在6年目。経営層の想いが可視化され、中間管理職はもちろん社員への情報共有も円滑になった。結果的に、残業時間を減らすこともでき、チーム力も強化された事例だという。
2つ目はお茶農家の事例だ。その年に摘み取る最初のお茶を「一番茶」、以降、摘み取った順番で「二番茶」「三番茶」というが、一番茶の売り上げを上げることが重要になる。その場合、乾燥工程をいかに効率化するかがカギを握る。
かつては、お茶の収穫時期は徹夜が当たり前だった。工場に泊まり込んで、3週間休むことなく乾燥させるのが日本の文化だったという。しかし、働き方改革が浸透した現在、当時と同じ働き方を実践するのは現実的ではない。
そうなると、工場稼働を均一化させ、分散させることが重要となる。RightARMでは工場稼働を均一化する計算が可能だ。結果的に、残業が減って社員の満足度も上がり、会社としても残業代を減らせて利益増につなげることもできている。
3つ目は企業が買収した農業法人の事例だ。生駒さんは、今後企業が農業に参入する際は、自ら立ち上げるのではなく、農業法人を買い上げるM&Aが増えていくと予想している。RightARMを活用すると、その農業法人の経営状態が見える化され、マイナスポイントが可視化される。それにより買収元の企業の経営者は安心して決断できる。
「農業業界には情報の非対称性が発生しやすい傾向があります。新たに農業に参入する企業がとても高い買い物をするケースは少なくありません。一方で、農業経営者の中には高齢のため、農業を引退したいと考える方もいます。そこを居抜きで借りたいといったケースは成り立ちやすいです。私たちは自社サービスを通じて、この非対称性を解消していきたいと考えています」
効率化、自動化で国内の食料自給を支えたい
最後に、今後の展望を聞いた。大きくは、産地支援への注力だ。RightARM for Exを開発したきっかけでもあるが、これまでテラスマイルでは新規就農者が離農しないよう、できるだけ早期に黒字化するための、産地に根差したマニュアルづくりを行ってきた。
その過程で現場に入り込んで支援する中で、ベテランの農業経営者は産地の発展に寄与できると分かれば、とても協力的な態度でデータを共有してくれる傾向があると分かった。生駒さんは産地が持つパワーに可能性を感じている。
生駒さんは「昔は農業を大規模化していかない限り、ブランディングするのは難しかったと思います。しかし、今はそのハードルが低くなってきているのを感じます。労働生産性で見ても10年前と比べて2~3倍に上がっていますし、小規模農業経営者が数人集まれば、無理なくブランドを作れることも分かってきました」と説明する。
また、「そんな下地がある中で、意欲を持った農業経営者たちのグループに、これから農業を真剣にやっていきたい意欲を持った若手が入ると、産地発のブランドとして持続的に展開できるでしょう。はじめのうちは新規就農者が周りの農家さんに巻き込んでもらいながら、個人としても産地としても成長していくことは、1つのモデルとして成立すると考えています」とも話している。
現在、北は北海道から南は鹿児島に至るまで、全国23の都道府県において、30産地ほどを支援しているテラスマイル。直近では各自治体の産地支援を行う目的で自治体連携強化も図っており、夏には某都市と事業連携協定を締結予定だという。
「会社は宮崎にありますが、東北地方にも思い入れがあります。私や一部のメンバーのルーツがある地域で、身近な人たちが震災を経験したこともあり、最終的に東北にも大きく還元したい想いがあります。また、フェアトレードを大事にする食品メーカーさまとのつながりも積極的に作っていきたいと考えています」
国内農業の発展にほとんどのリソースを注ぎ込むが、グローバルでの活動にも触れておきたい。2022年からは農業特性が日本と近いインドネシアでの実証にも取り組み、売り上げや利益を上げることのできる次世代若手農業者と産地の創造に挑戦してきた。「すべての営農者を豊かに、国を守る社会インフラとなる」ミッションは国境を越える。今後も、テラスマイルの挑戦は続いていく。