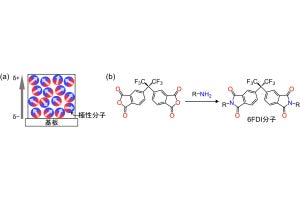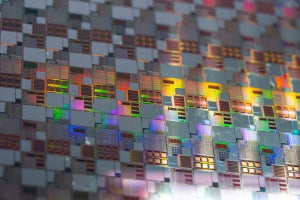米デル・テクノロジーズは4月24日(現地時間)、「Innovation Catalyst」調査の結果を発表した。調査は、世界40カ国のITおよびビジネスの意思決定者6600人を対象に実施した。
調査の結果、回答者の81%(日本:70%)が、生成AIとAIが将来的に幅広い業界を変革すると考えていることが明らかになった。この割合は2023年と比較すると、売上伸び率が高かった企業(+25%)では91%(日本:90%)に増え、成長率が低かった企業(1~5%)、横ばいだった企業、低下した企業では75%(日本:69%)に減少するという。
また、「自社は十分に競争力を持ち、確固とした戦略を有している」と考えている回答者は82%(日本:52%)だったという。その一方で、およそ半数(世界:48%、日本:56%)の回答者は「自社業界の3~5年後がどうなっているか不明確である」と考えており、回答者の57%(日本:65%)が、変化のスピードに合わせていくことに苦慮していると回答した。
イノベーションを進める上で直面している上位3つの課題として、世界では35%が「適切な人材の不足」、31%が「データ プライバシーとサイバーセキュリティに関する懸念」、29%が「予算不足」を挙げた。日本では、52%が「適切な人材の不足」、31%が「従業員が変化を受け入れられない」、30%が「データ プライバシーとサイバーセキュリティに関する懸念」を挙げた。
生成AIの活用は構想から実装へ
回答者の52%(日本:24%)は、生成AIが持つ変革的な力や大きなポテンシャルとして、「ITセキュリティ体制の強化」と回答。また、52%(日本:30%)が「生産性の向上」、51%(日本:26%)が「顧客体験の向上」と回答した。
克服しなければならない課題として、回答者の68%(日本:60%)が生成AIの導入によって生じる新たなセキュリティとプライバシーの問題を挙げ、73%(日本:58%)が、第三者によるアクセスの可能性がある生成AIツールに自社のデータと知的財産を置くことはできないと考えていることが明らかになった。
58%(日本:58%)が生成AIの導入に着手していると回答しており、生成AIの導入増加に伴い、どこにリスクがあるのかを把握することや、誰が責任を負うのかといった部分が主な懸念点だとしているという。AIの誤動作や望ましくない挙動について、77%(日本:62%)がツールやユーザー、一般の人々ではなく組織に責任があると回答した。
サイバーセキュリティに関する企業の取組み
過去12カ月の間にサイバー攻撃による影響を受けたという回答者は、83%(日本:75%)に上る。世界では89%(日本:77%)がゼロトラスト展開戦略を進めており、78%(日本:58%)がサイバー攻撃やデータ漏えいから回復するためのインシデント対応策を実装しているとのことだ。
懸念されるセキュリティ上の課題としては、マルウェア、フィッシング、データへの不正アクセス(日本:ランサムウェア攻撃、フィッシング、マルウェア)が挙げられた。また、調査結果から、脅威を取り巻く環境で従業員が果たす重要な役割が浮き彫りになっているそうだ。
例えば、回答者の67%(日本:48%)が効率と生産性が低下するという理由で、ITセキュリティのガイドラインと慣行に従わない従業員がいると考えており、65%(日本:57%)が内部の人間による脅威が大きな懸念であると回答した。この結果は、セキュリティにおける最初の防衛線となる従業員の教育・研修に注力する必要性を示している。
最適なITインフラが企業の成功を後押し
企業がイノベーションを加速させる際に改善すべき最も重要な分野として、拡張性に優れたモダンインフラストラクチャへの投資が挙げられた。大部分のIT意思決定者(世界:82%、日本:82%)は、生成AIの導入に際して考えられる課題に対応する上で、オンプレミスかハイブリッドを優先すると回答している。
全社規模でデータを共有できる環境も、イノベーションにおいては重要だ。イノベーションへの取り組みを支援するために、今すぐにデータをリアルタイムのインサイトに変えられるとした回答者は、3分の1(世界:33%、日本:28%)にとどまる。
ただし、82%(日本:67%)の回答者がデータは差別化要因であり、生成AI戦略にデータの活用と保護を組み込む必要があると回答しており、各企業がこの課題に取り組んでいることがうかがえる。また、回答者の42%(日本:30%)が、今後5年間でデータの大部分はエッジからもたらされるようになると予想しているとのことだ。