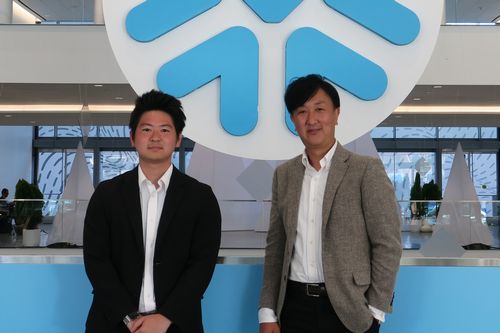日本では、社会インフラ業界をはじめ、多くのエンタープライズ企業でいまだオンプレミスのレガシーな資産が残っている。中でも、航空業界は国内と国外で異なる競争環境、4年前のコロナの打撃からの回復、コストと安全性のバランスなど、特有の要件が多い業界だ。それらの課題解決の一助となるのがデータ活用だ。
日本航空(以下、JAL)とJALカードはデータプラットフォームにSnowflakeを導入して、データ活用基盤を整えた。今回、Snowflake Data Cloud SUMMIT2024に参加したJALの平野広大氏(デジタルテクノロジー本部 運営企画部 デジタル活用推進グループ)、JALカードの尾﨑学文氏(DX推進部 プロジェクト推進グループ)に、どのようにクラウドシフトを検討して決定に至り、効果が得られているのかについて伺った。
コスト、柔軟なリソースの拡張、データシェアリングが魅力
JALがSnowflakeを導入したきっかけは、それまでデータ基盤としてきたオンプレミスのデータウェアハウス(DWH)で感じていた課題の解決策を求めていたことだ。
平野氏はDWHが抱えていた課題について、次のように語る。
「オンプレ環境では、リソースを追加するためにサーバラックを追加するとなると時間も費用もかかるため、ユーザーの要望に柔軟に対応できない。また、年間6000万円という運用コストも大きな負担だった」
JALカードの尾崎氏は、さらなるSnowflakeの魅力について、「社内でデータを利活用するだけでなく、データシェアリングを活用した新たな施策展開などに将来性を(Snowflakeに)感じた。これが最大のポイントだった」と語る。
「JALカードは“データビジネスカンパニー”を掲げている」と話す尾﨑氏。その実現に向けて、JALと足並みをそろえることも、JALカードのみ従来のDWHを使い続けることもできたが、「社内でデータを利活用するだけでなく、データのマネタイズのような将来性を(Snowflakeに)感じた。これが最大のポイントだった」と、同氏は振り返る。
全社データ活用基盤の整備で、データの一元管理を実現
そして、JALとJALカードは共にSnowflakeに移行した。JALでは2023年11月に導入し、2カ月の並行稼働を実施したのち、2024年1月にサービスインした。JALカードも少し遅れて、同じ道を経た。データ移行はSnowflakeのマイグレーションツールと一部スクラッチプログラムを活用した。データの移行そのものに要した期間は1カ月程度で、特に大きなトラブルはなかったという。
JALはSnowflakeに顧客属性、予約情報、運航情報、整備情報、ツアー情報などを格納している。一方JALカードは、顧客属性、カードの利用履歴、コールセンターの問い合わせ履歴、マイル提携企業管理情報などを格納している。
データの可視化とBIツールは、両社ともにTableau、SPSS、SAS、JALカードはさらにMicroStrategyも利用している。Snowflakeを全社的なデータ活用基盤として整備することで、散在していたExcelファイルなどのデータを集約し、一元管理できるようになったという。JALでは3000人程度がこれらのツール経由でSnowflakeにあるデータにアクセスしているそうだ。
導入効果は「コスト半減」「保守・運用における課題解決」
完全にSnowflakeに置き換わってから半年弱だが、想定通りの効果が出ている。
まず、コストは単月の旧来比で52%低減できた。性能は「オンプレのデータ基盤よりも小さなサイズで、同等以上のパフォーマンスを実現できている」と尾﨑氏は話す。「正直なところ、Snowflake側が強調していた高速化とコストダウンは半信半疑だったが、コストは想定を下回り、速度はサイズを上げるほど速くなる実感がある」と付け加えた。
移行前に感じていた課題を解決できたことに加え、メリットとして、両氏の口から出てきたのは保守・運用面での便利な機能だ。中でも、過去のデータに簡単にアクセスできる「Time Travel」、データベース、スキーマ、テーブルなどのコピー機能「Zero-copy Clone」などを重宝しているという。
「新しいパッチを増やすなど項目が増えた時に活用している。便利、スマート、かつ高速。これまでになかった機能なので感動している。コピーは数十秒で完了するし、(クラウドなので)物理的な容量を気にしてコピーができないという状態から解放された」(尾﨑氏)
リリース後に発生した軽微な障害時も、特定日時の状態に戻してパッチを再実行するだけで済んだという。IT部門の活用としては、本番データをコピーしてテストするといったことが容量を気にすることなく、「クローンしてテストして問題なければスワップして本番。本当に便利」と尾﨑氏。
なお、リソースの拡張については「これから」と平野氏。「リソースを追加するとなった時にやるべきこと手順を洗い出すと、明らかにオンプレのデータウェアハウスよりハードルが低い。そのため、案件をスタートしやすい」と期待を語る。
オートスケーリングについては、他のデータクラウド製品ではリソース補強の単位が大きく、すぐに費用が跳ね上がるが「Snowflakeは細かい調整が可能。本当に必要なリソースのみを使うことができる」と平野氏は語った。
次のステップは高度なデータ活用や「Streamlit」の導入
データ活用の基盤が整ってきたところで、「今後は運航実績データの高度な分析などに取り組みたい」と、平野氏は語る。それまでは空港ごとなど個別にExcelを使って集計していたが、膨大なデータをSnowflakeに一元化し、これを分析することで「定時性などで価値が得られそう」と踏む。
またJALカードでは、まずは「顧客のLTV(ライフタイムバリュー)を把握し、強化のための策につなげていく」(尾﨑氏)という。このように、データ基盤を活用して既存のクレジットカード業を進化させるとともに、今後やっていきたいこととして、「ホワイトスペースを見つけて新たなビジネス価値や事業を醸成していきたい」と尾﨑氏は話す。
具体的には、今までにないターゲットに絞った新たなビジネスなどを考えており、「社内でデータを利活用していくというマインドが高まっている」とのことだ。なお、JALカードはデータ戦略部をハブとし、ほぼ全ての部署に“DATA ASSOCIATE(データアソシエイト)”というデータ担当をアサインし、活用を奨励しているそうだ。
今後の計画の一つに、Pythonで容易に分析アプリを構築できるSnowflakeの「Streamlit」の活用も考えているという。「われわれが管理しきれていない使われ方をしている抽出ツールがある。Streamlitでユーザーの要望を即実現することで、どのようなアプリがどのようなデータを抽出しているのか管理できるようになる」と、平野氏は狙いを明かした。
保存していただけのデータを価値あるものに変えていく
このように、JAL、JALカードのSnowflakeプロジェクトは順調に進んでいるが、その土台にあるのが、Snowflakeの技術面での特徴に加え、「熱い思いを感じている」というSnowflake担当者との信頼関係だ。
それに加え、Snowflakeが開催する同業他社を集めたラウンドテーブルなどから得られるものも多いという。Snowflakeが6月にサンフランシスコで開催した「Snowflake SUMMIT」では、国内外の航空会社のデータ担当者と情報交換ができたと両者は喜んでいる。
Snowflakeに対する要望を聞いてみたところ、尾﨑氏からは「マーケットプレイスのUIをもう少し使いやすくしてほしい。AIを活用して、思いがけないデータセットとの出会いを演出してくれるような機能があるとうれしい」との声。平野氏は、「まだSnowflakeの機能を使いきれていない。豊富な機能をいかに活用するかが目下の課題」と述べた。
JALの平野氏は最後に、「データ活用がもたらす変革を通じて価値を生み出すというビジョンがある。その実現の手段の一つがSnowflakeであり、ただ保存していただけのデータを価値あるものに変えてきたい」と述べる。JALカードの尾﨑氏も、データビジネスカンパニーの実現に向け、Snowflake導入により基盤ができたとし、今後に期待を寄せた。