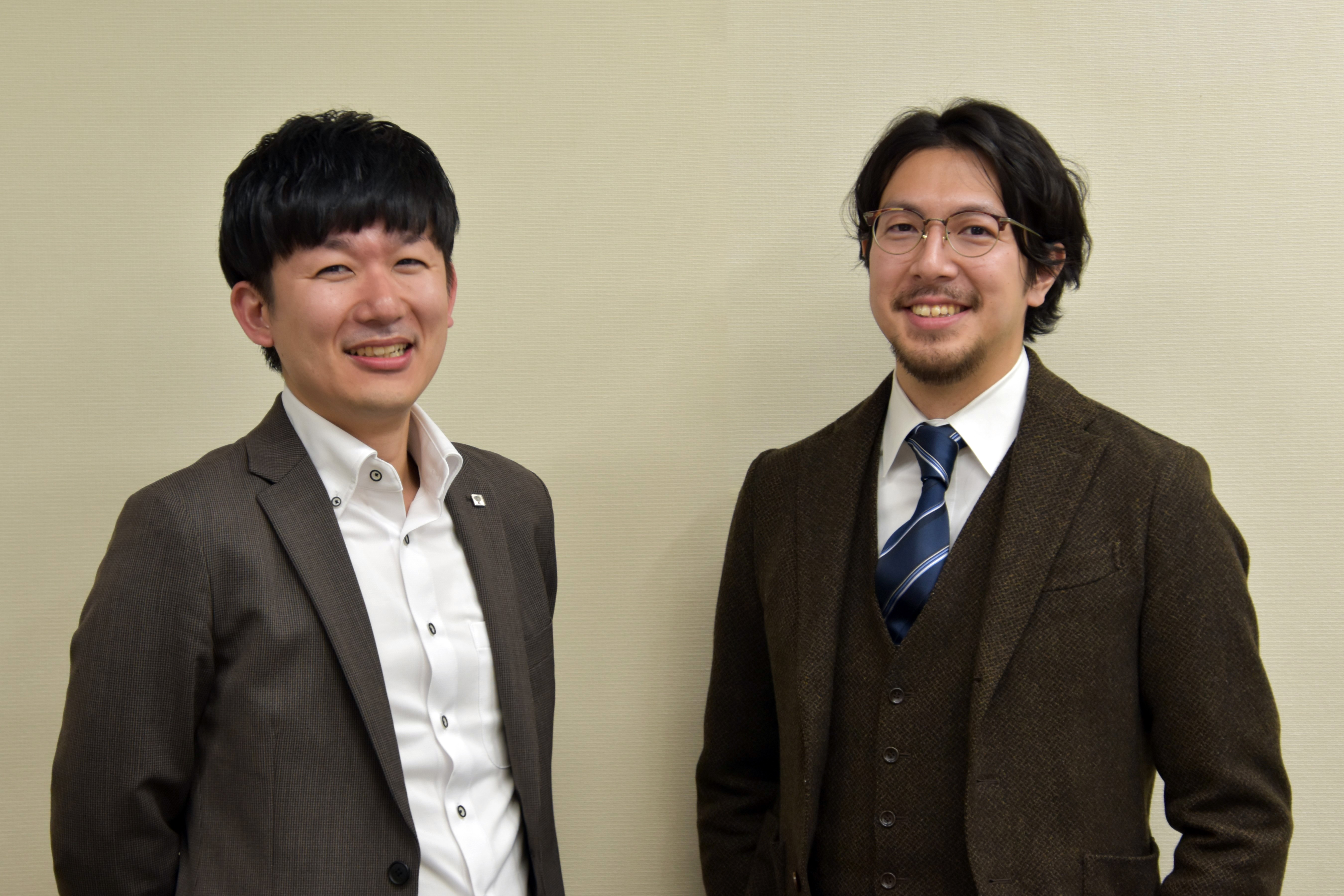医薬品だけではなく、「ポカリスエット」や「オロナミンCドリンク」など、多数の健康飲料・栄養食品を手掛ける大塚製薬が、食育活動にも長年注力していることをご存じだろうか。
「魚は最初から切身の形をしていると思い込んでいたり、肉や魚に骨があることを知らなかったり、野菜の形が分からなかったりする子どもも少なくありません。共働き世帯が増えていることもあって、食事やその準備にかけられる時間がなかなか取れないなど、食育ができているか不安に感じているという声も聞きます」
そう語るのは、大塚製薬 ニュートラシューティカルズ事業部で食育事業を担当する武藤太郎氏だ。こうした現状を踏まえ、同社では2024年2月に新たに食育ゲームアプリ「もぐもぐタウン」の配信を開始した。
「食育」と「ゲームアプリ」、一見直接的に紐付かないように思えるが、なぜ大塚製薬は食育の課題をゲームアプリで解決しようと考えたのだろうか。もぐもぐタウンの開発を担当した武藤氏と電通 第16ビジネスプロデュース局アカウントリード6部 清水徹也氏に、同アプリ開発の経緯と、プロジェクト進行の裏側について伺った。
そもそも「正しい食生活や栄養の知識を身に付けづらい環境」
大塚製薬では健康飲料や栄養製品を多数販売していることから、「『健康の維持・増進につながる』活動を行っている」(武藤氏)という。中でも、子どもたちが正しい食生活や栄養の知識を身につけづらい環境にあるという課題に着目し、小学生などの子どもたちが栄養への正しい理解を深め、自身の健康増進に努めてほしいという思いで行われてきたのが食育活動だ。
2018年には、食育アプリの第1弾として「おいしいおえかきSketchCook」をローンチ。子どもが描いた食材の絵をスマホのカメラで読み取ると、料理のメニューを判別し実物の料理に近い画像へと変身させるとともに、その“料理のレシピ”と適切な栄養バランスを補完する“食べ合わせメニューのレシピ”を提案するというものだ。AIを活用した同アプリは、体験会やワークショップでは親子ともに高い評価を得た。
このように進められてきた大塚製薬のアプリコンテンツを通した食育活動だが、その中で気づいた大きな課題の1つとして挙げられていたのが、子どもたちに「食の知識」が育まれていないことだ。
「実際に小学校に勤務する栄養士さんに話を伺った時、今の子どもには我々の想像以上に食や栄養に関する知識が身に付いていないことがわかりました。家庭において親御さんの献立づくりのサポートも我々は解決すべき課題と捉えています」(武藤氏)
そこで同社が着目したのは「子どもとデジタルデバイスの接触機会の増加」だ。
現在、文部科学省がデジタル教科書の配布を推奨していることもあり、学校ではスマートフォンやタブレット端末が貸与されているケースが増えつつある。家庭内でもデジタルデバイスへの接触数は上がっていることから、新たなアプリとして「もぐもぐタウン」の開発を進めることになったという。
ゲーミフィケーションの採用で継続的な利用を狙う
家庭における課題やこれまでの経験を踏まえ、もぐもぐタウンでは「より継続して日常的に利用してもらえること」を前提に置いた。そこで、ゲーミフィケーションのアイデアを取り入れて、ゲームを介して子どもが食育を学べるような仕組みを開発したという。
「ゲーミフィケーションは教育現場ではポピュラーになっている手法です。大塚製薬さんとしてはおいしいおえかきSketchCookから続く、楽しみながら学んでもらいたいという想いを継承するにあたって、子供たちが楽しめるような仕組みづくりとしてゲーミフィケーションを採用した経緯があります」(清水氏)
もぐもぐタウンは、食卓に並んだ食事を写真に撮ると、アプリが食材を認識。それぞれの食材にちなんだキャラクター「もぐみん」が登場し、彼らを仲間にしてもぐもぐタウンを発展させていくゲームだ。
もぐみんを仲間にするためには食に関するクイズに回答する必要があり、食材に含まれる栄養素や旬などについて学べる機会となる。最大100食材25万種類のもぐみんたちがおり、1食材あたり50種ずつの目、口のパターンが用意されていて、ランダムで登場する仕様だ。集める楽しさにより、構想していた継続的なアプリ利用の促進を狙う。
「ユーザーが感じる『達成感』にはこだわって開発をしました。毎日継続していくにあたって、小さくてもステップを踏んでいる様子が可視化できることはとても大事だと考えています。もぐみんを集めてもぐもぐタウンを発展させることが最大のポイントですね」(武藤氏)
食育ならではの課題を「ワンチーム」で解決
子どもたちが楽しめるアプリ開発を進めるにあたり、「食育」というテーマを扱うが故の悩みや苦労もあったと武藤氏、清水氏は振り返る。
一言に食育と言っても、食生活における知識からマナー等に至るまで、その概念は幅広い。「幅広い概念をもつ食育に対して、もぐもぐタウンを通じて何を目指し、どうアプローチしていくのかがまず最初にあたった大きな壁だった」と武藤氏は語る。しかし、さまざまなヒアリングやすり合わせを経て、「食を学ぶことは楽しいと思える入り口を作る」ことを指針としたという。
「アプリ開発の中で、どこを目指していくかがブレてしまわないように目指す地点を定めました。小中学校の栄養士さんや栄養学を専門とする大学教授などいろいろな方にヒアリングをしたところ、各所から『食を学ぶことは楽しいと思える入り口を作ってくれるだけでも、十分食育に貢献している』とのコメントをたくさんいただきました。我々も肩の荷が下りたような感覚で、そこからはブレずに進められましたね」(武藤氏)
一方、清水氏は「正しい情報をわかりやすく発信をする」ことに最も注力したと語る。
「当たり前のことですが、世の中にリリースする以上は正しい情報を伝えなくてはいけません。大塚製薬さんは人々の健康に寄与するために事業展開している企業でもあるので、その点に関しては様々な学術資料を事前に読み込むなど、厳格に情報精査をしました。アプリ内の説明一つをとっても、正しいか誤りかはもちろん、だれが見てもわかりやすい表現なのかどうかも含めて一緒に追及していきました」(清水氏)
確認量や制作物の量は膨大だったというが、武藤氏は「制作の協力をいただいた電通や、アプリ監修の日本スポーツ栄養協会の皆さんには大塚製薬の思いを汲みながら多くのお力添えをいただいた」と謝意を示す。開発過程においても、両社で連携を取りながらスムーズに進められた手応えを感じているそうだ。
「ディスカッションする場面も多く、時間を忘れ取り組みました。でも、こうしたディスカッションや確認といったやり取りはミスをなくすことを目的にした“校閲”ではなく、『こうすれば面白いのではないか』を追求したポジティブなものでした。もぐもぐタウンは電通さんとのディスカッションの賜物だと思います」(武藤氏)
クライアントである大塚製薬と代理店の立場である電通が「ワンチーム」となって進められたからこそ、求める形を体現できた「もぐもぐタウン」。武藤氏、清水氏は「クライアントと代理店の垣根を超えたチームだった」と話す。
コンテンツの普及と深化で目指すのは「全国民の健康」
2月のローンチから早1カ月以上が経ち、ユーザーからは「子供が朝起きるたびに『もぐもぐタウンがやりたい』と言って食卓についてくれる」「食材の話題が増えたので、一緒にスーパーに行く機会も多くなった」など開発冥利に尽きるコメントが多く寄せられているという。武藤氏と清水氏はじめ開発チームは、もぐもぐタウンを通じて、家庭内のコミュニケーションが活発になっていることを実感しているそうだ。
今後は、さらに「食卓に子どもが座りたくなるコンテンツ」を追求していく。3月19日には食事の準備をしている間の時間を想定して、食卓で子どもが待ちながら見られる短編アニメ「もぐもぐタウンレディオ」を制作、YouTubeで配信を開始した。このように、食卓の課題にも向き合っていくのがもぐもぐタウンの方針だという。
「“生の声”をたくさん聴いて、より良いアプリを目指したいですね。ローンチしたばかりなので、今出てきている改善点はまだ一部に過ぎないと考えています。技術的な問題はあるかと思いますが、適宜、必要に応じて改善を検討していく予定です」(武藤氏)
一方、普及に関しては、展示会への出展のほか、教育団体や自治体や関係官庁との連携も強化していく計画だ。
武藤氏は「もぐもぐタウンを全国の家庭で使ってもらいたい」と思いを語る。
「もぐもぐタウンは『食を通じて家庭内のコミュニケーションが深まるもの』だと自信を持って送り出しています。もぐもぐタウンが普及することで、食への意識が高まって健康をサポートできればと思います。ただ、時代が変われば食育促進への最適解も変わってくるはずなので、もぐもぐタウンに関わらずその時最適なサービスを提供していきたいですね」(武藤氏)