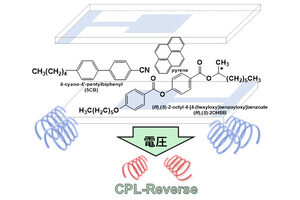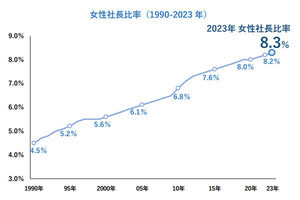多くの人にとって「助産師」という職業は、看護師より遠い存在ではないだろうか。妊婦とその家族が関わる医療専門職といったイメージを持っている方も多いかもしれない。しかし、かつて助産師は「産婆」と呼ばれ、女性の身体や育児、夫婦関係などを相談でき、家族の健康を見守る身近な「伴走者」として地域で幅広く活躍する存在だった。
「保健師助産師看護師法」において、助産師は「厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と定義されている。
ただ、この定義は助産師の一面しか示していない。というのも、助産師として働くには看護師免許が必須となるため、すべての助産師は看護師免許も持っている。さらに、助産師の半数は保健師資格も持つ、非常に専門性の高い医療職なのだ。
出産に限らず、性教育や妊娠、育児、更年期など、女性の生涯に寄り添えるのはもちろん、その豊富な知見は性別を問わず、人々の生涯をサポートできるともいえる。
現在、約9割の助産師が病院やクリニックに勤めているが、患者が助産師によるケアを受けられるのは入院中の5~7日程度だという。
「病院で出産のときだけ関わる現代の助産師の一般的なイメージは実は最近のものです。戦後GHQ(連合国最高司令官総司令部)による出生数管理や出産=医療という価値観の変化、出産施設を病院へ集約したことにより、地域での仕事を失った助産師が病院に勤務する流れができ、現在の形態に変わっていきました」
こう話すのは、With Midwife 代表取締役の岸畑聖月さんだ。Midwife=助産師で、社名は「助産師とともに」の意味を持ち、役員を含む従業員の7割が助産師資格を有している。
そんな同社が提供するのは、企業専属の女性医療専門家による健康支援プログラム「The CARE」や助産師向けリスキリングサービス「License says」など「助産師の活動の活性化」を軸にした複数のサービスだ。岸畑さんにWith Midwifeのこれまでとこれから、実現したいことを伺った。
「助産師の力で社会課題にアプローチしたい」と起業
岸畑さんが京都大学大学院時代の仲間とともに、With Midwifeを創業したのは2019年のこと。大学院卒業後は、年間約2000件のお産を支える大阪市内の総合病院で助産師として勤務していた(現在もパートタイムで勤務)。その過程で、虐待や中絶、産後うつなどの社会課題の深刻さを肌で感じ、病院外での課題解決を目指し起業するに至った。
「寄り添う(care)」力で、目の前の命はもちろん、流産や死産など目に見えない命も取り残さない社会の実現、妊活や出産・育児と仕事との両立に悩む女性を支援したい。そんな強い想いを抱えてのスタートだった。
しかし、創業直後、コロナ下に突入して大きな試練に見舞われる。社会の停滞に伴い、事業も停滞したと岸畑さんは振り返るが、立ち止まることはなかった。
2020年5月には、全国の助産師を検索できるプラットフォームサービス「Meets the Midwife」をローンチ。コロナ下で人とつながる・集まる機会がなくなって孤立し、出産や育児などに悩む女性が自分に合う助産師と出会えることを目的に開発した。
Meets the Midwifeは、女性と助産師をつなぐ全国初の取り組みだったことで注目され、テレビ番組で取り上げられ、助産師が設立した会社としても話題になった。
その勢いは止まらず、翌年の2021年7月には、「令和3年度 フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」の実証事業者として、助産師によるオンライン相談サービスの実証事業を2つ開始。
1つ目は「大企業および中小企業の従業員を対象としたライフステージを支える企業内助産師の有用性検証事業」として、助産師によるヘルスケア/メンタル/子育てなどのオンライン相談、健康やキャリアに関するセミナーなどを行うというもの。
2つ目は「潜在助産師を活用した、地方における育児期の女性の職場復帰を支援するオンライン相談事業「The CARE for Community」の実証実験である。長野県内在住の育児休業中の女性および家族を対象に、24時間365日オンラインシステムを用いた健康と子育て個別相談を行った。
どちらの実証事業も、その後に提供する主要サービスの原型となった。やると決断したら1~2カ月で形にし、スモールスタートするのが同社の特徴でもある。
企業専属の助産師として、寄り添うケアを届ける
現在、同社を代表する法人向けサービスの1つであるThe CAREは、伴走型従業員健康支援プログラムとして、専属の助産師(※)に健康や子育て、メンタルなどの相談が24時間365日、匿名で相談できる。
※編集部注:1社につき助産師・看護師・保健師などの国家資格を併有するスタッフ3人以上がつく
彼女たちは、女性の月経をはじめ、性別を問わずメンタルヘルス、各種体調管理、妊活、育児、介護など、従業員の公私における多様な悩みに専門知識を持って寄り添い、相談が寄せられると24時間以内に回答する。
流産や中絶の経験で傷ついた人、更年期が辛くてキャリアを断念しようか迷っている人、生きるのが苦しくなった人……。サービスを開始して4年ほど経つ中で、心身に辛さや不調を抱えた従業員からさまざまな相談が届いてきたという。
「私たちが提供しているのは、いわば社外相談窓口のようなものです。ただ、辛さや苦しさを抱えたときに、私たちを思い出して連絡をくださる方が大勢います。助産師が寄り添うことへの価値が、従業員の方々に確かに届いている手応えを感じています。
ただ、こうして頼っていただけるかどうかは、個々の助産師の力量にかかっています。従業員の方と向き合う助産師一人ひとりが、皆さまをエンパワーメントして、最高のケアを届けようと努めています。利用される方が心を解放できるサードプレイスとして、より活用いただけるよう、サービスの質を高めていきたいです」(岸畑さん、以下同)
企業が専属の助産師を抱える利点は多い。従業員は具体的な問題を持ったとき、すでに接点のある助産師に素早く相談できる仕組みがある。問題の根が深くなる前に従業員から相談を受けると、助産師は迅速に介入できる。
さまざまな背景から少子化に歯止めのかからない現代社会で、岸畑さんはThe CAREを通じて、出産意欲があるものの踏み切れない女性も支援したいと考えている。
「産みたくてもハードルがあって産む決断ができない女性たちのほかにも、孤独な育児や産後うつなど孤独感を抱える妊産婦も大勢います。経済発展を遂げて豊かになり、人口増が落ち着いた国では孤独が社会問題となり、日本はその最先端をいっています。自分が望まない孤独は生きる上で大きな痛みになります。私たちのサービスを通じて、孤独のない社会を作りたいと考えています」
サービス利用者のコアとなる育児中の人々やメンタル不調を抱える人々を中心に、ゆくゆくはその周辺にいる人々にも支援を波及させていくことを目指す。
「育児出向制度」で個人・会社・事業を成長させる
With Midwifeが運営するサービスには数百人規模の助産師が登録している。これは言い換えると「数百人規模の助産師コミュニティを持っている」ことにほかならない。社内外で助産師人材を豊富に抱える点が同社の強みの1つであるが、人材の成長、ひいては会社の成長につながる取り組みをしていることにも着目したい。個々のスキルを上げることが、サービスの価値最大化に結びつくからだ。
その一例が福利厚生制度の1つである「育児出向制度」である。育児休業制度ならぬ育児出向制度を使うと、昇給の確約や陣痛中の支援、訪問ケア(産後ケア)、出向中の情報共有、子育て・メンタル・体調面のフォローアップなど手厚いサポートが受けられる。
同制度を利用した初のメンバーが2023年9月に無事出産を迎えたことを10月に発表し、ユニークな福利厚生制度であると注目を集めた。出産や育児の経験は従業員個人・組織ともにメリットが多く、休業というより多様性を身につける出向に近いのではないかといった考えで2023年5月、よりポジティブな表現に変更したのが同制度誕生の背景である。
育児出向中は、出産や育児のリアルな知見を獲得でき、助産師としてだけではなく養育者としての目線も持つようにもなると岸畑さんは考えている。職場に復帰したとき、働く人の健康や子育て支援を行うWith Midwifeの事業にその経験は大いに生き、より良いサービスを提供できるようになるとも確信している。
なお、創業当初から育児出向制度と同様の取り組みを行っていたところ、戻ってきた社員はスキルアップしており、会社や事業発展に貢献したという。自社事業とリンクする個人的な経験をポジティブに捉え、環境を用意し、個人と組織が成長するステップだ。この在り方から学べることは多いだろう。
助産師の活性化で社会課題に寄り添いたい
最後に、With Midwifeとしての今後の展望を聞いた。いずれはグローバルへの進出も視野に入れているが、目下の目標として掲げるのは、同社が抱える助産師コミュニティを拡大していくことだ。2030年には約3700人の助産師コミュニティへと成長させることを目指している。
現在、病院やクリニック、助産院で働く助産師は約3万7000人いる(※厚生労働省 令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況による)一方で、ほぼ同数の助産師が資格を持ちながらも就業していないとの試算もある。特に地方においては、就職先がなかったり、助産師としての専門性を生かせる仕事につけなかったりする人も少なくない。
2023年に行ったフィンランド視察をはじめ、海外視察の機会も多い岸畑さんは、日本の助産師の専門性やケアレベルの高さを多くの人に届けたいと考えている。おもてなしやケアの精神、寄り添う姿勢は日本特有で、とても高い価値を持つものだと、多くの現場を見て感じてきた。
不妊や産後うつなど、出産や育児に関する悩みを抱える人々は年々増えている。助産師が解決できるはずの、いのちにまつわる社会課題が深刻化の一途を辿る中、社会で助産師の活動を活性化させていくことが必要だと岸畑さんは確信している。
定量的な目標としては、2030年に600億円の売り上げを達成することを掲げている。そのときの理想の状態は「『助けてほしい』と思った人が、ボタン1つで助産師という専門家にアクセスできる社会」。
スマホに標準でインストールされているヘルスケアアプリのように、心身の不安を助産師に直接相談できるアプリが入っていたら、どれだけ助かる人が多いだろうかと想像する。人々にとって身近な場所に助産師を配置し、助産師と出会う接点を増やすことで、誰も取り残されない未来をWith Midwifeはこれからも作っていく。