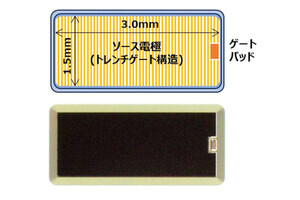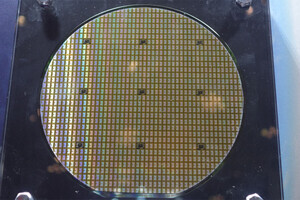AWSユーザーのコミュニティであるJAWS-UGで昨年立ち上げられた「Storage-JAWS」をご存知だろうか。実は、Storage-JAWSが立ち上がるまでJAWS-UGにストレージの専門支部がなかったというから驚きだ。今回、立ち上げメンバーの1人でもある、ネットアップ AWS SE Support シニアクラウド ソリューション アーキテクトの藤原善基氏に、立ち上げの経緯や今後の活動について話を伺った。
「ストレージの支部がない」状況にヤキモキ
すでに、Storage-JAWSはJAWS-UG横浜支部との共催も含めるとIT勉強会プラットフォームの「connpass」で計3回開催している。藤原氏は「これまで、ストレージに関する支部はありませんでした。AWSのパートナーで特定の領域に強みがある人を表彰する『Japan AWS Top Engineers』でもデータベースやアナリティクス、機械学習などの項目はありますが、意外とストレージのカテゴリーはありません」と話す。
こうした経緯もあり、2021年にネットアップに入社して以降、AWSと関わる中でJAWS-UGのさまざまなイベント・支部に参加する中で、ストレージの支部があればと考えるようになったという。
藤原氏はストレージベンダーとしてネットアップに所属しているため、他支部を運営するメンバーからベンダー側の宣伝目的やサービスを紹介することが目的ではないことから、運営メンバーを複数人集めるように助言を受けた。
このような状況において、仲間探しのためJAWS-UGの人たちと話すと「あれストレージのコミュニティないんだっけ?」と藤原氏と同じような感想が多かったものの、賛否両論があったという。
その当時について、同氏は「絶対にあった方がいいとう意見もあれば、存在しないなりの理由があるのでは?と言う意見もありました(笑)。ただ、年次カンファレンスの『AWS re:Invent 2022』に参加してからは、周りの方により声を掛けるようになっていきました。動きを強めっていたのは2022年末から2023年にかけてです」と述懐する。
「AWS コミュニティビルダープログラム」に認定
こうした動き活発化させたこともあり、藤原氏に転機が訪れる。2023年5月に複数のプログラム言語でAWS CloudFormationテンプレートを生成するAWS CDKのコミュニティである、JAWS-UG CDK支部が開催した「AWS CDK Conference Japan」の運営メンバーと懇親会で話した際に「やりますか!」という一言がきっかけとなった。AWS CDK Conference Japanの運営メンバーが協力する形で動き出しというわけだ。
藤原氏は「あとで分かったことなんですが、新しい支部を設立する際は他支部の運営メンバーに推薦人あるいはコントリビューターとして携わってもらうということ、が前提条件に入っています。懇親会で話したJAWS-UG CDK支部の運営メンバーと仲間を集めるために、Slack上でメンバーの募集をスタートしました」と話す。
続けて、同氏は「最終的なメンバーは6人となりました。初めてコミュニティの運営に携わるメンバーもいれば、他支部の運営メンバーもいることから、上手くミックスされてバランスが取れた形になりました。また、AWS-UG横浜支部が心強いバックアップをしてくれました」とのことだ。
結果的に2023年後半には、AWSのコミュニティに認定してもらうプログラム「AWS コミュニティビルダープログラム」に申し込み、選ばれている。
藤原氏は「選ばれるためには貢献度が求められるため、具体的にどのような発信をしているのか、他支部のリーダー、AWSヒーローなどの推薦も必須項目ではありませんが、ポイントとしてあります。これらをクリアして、審査を通過すれば選ばれるようになっています」と説明する。
「顔が見えるメンバーでざっくばらんに」
こうして設立されたStorage-JAWSでは、データを利用するためのストレージは土台のため、さまざまな使い方についてのディスカッションに加え、他支部が扱うテーマと密接に関わっている領域でもあることから、支部間におけるシナジーの発揮を目指している。
藤原氏は活動開始からを振り返り「いざスタートしてみたら、良いことが重なっていますね。例えば、登壇枠についてはAWSが開始した若手を表彰する『AWS Jr. Champions』の受賞者枠を設けたことで、競争が良い形で生まれました。そこからStorage-JAWSに入ってくれた方もいます」と語った。
AWSは圧倒的にサービス数が多く、個人の勉強だけではキャッチアップが追い付かないということがある。そのため、コミュニティで情報を共有すれば課題解決の一助になるといのも頷ける。
過去にオンラインで開催(いずれもconnpassで開催)したStorage-JAWSのイベント参加者は、運営メンバー6人を含めると「#0」(実質上の第1回)が155人、「#1」(第2回)が150人、「#2」(第3回)が133人となっており、アーカイブの動画も閲覧されているという。
藤原氏は「顔が見えるメンバーでざっくばらんに現場の井戸端会議ができるようになっています。今後はオフライン、オンラインのハイブリッドで開催してければと考えています。本来であれば、お金を払って受講するようなものをコミュニティだからこそ、無償で情報が共有できるのは素晴らしいことです。私自身がJAWS UGに参加して受け取ってきたものが大きいため、自分から発信し、支えることができればと思います」と、その意義を説く。
持続性のある運営体制を目指す「Storage-JAWS」
ただ、こうした知見を自社のみならず広く還元していくことも重要だ。その点について、同氏は「もちろん、コミュニティ自体に還元していますし、自身の仕事にも活用していただきたいという想いです。どのようにコミュニティが役立ち課題が解決できたなど、参加者同士で楽しく話したいから実施しています」と力を込める。
そして、同氏は「テーマによっては、AWSとの共同開発している製品や自社製品の話になってしまいますが、その点は課題に対して、さまざまなサービスを利用した結果として、役立つ情報を提供するように忖度のないディスカッションにしようと努めています。コミュニティでリアルな声を聞いているからこそ、リクエストがネットアップ、AWSどちらにも積まれており、開発のループが回るようになっています」と述べている。
最後に、今後のStorage-JAWSにおける展望について藤原氏に尋ねたところ、以下のように回答が返ってきた。
「運営メンバー6人でテーマ決めて実施しており、ファシリテーターは開催ごとに変えています。存在感のある支部になっていきたいと考えています。まずは、運営体制をしっかりと整えつつ、参加者の規模も増やし、場合によっては分科会や特定のテーマに絞ったイベント開催、他支部のようにレポートを出せればと思います。広く運営メンバーは募集していますし、持続性のある運営体制を目指したいです。今後もストレージに関する重要なことを発信していきます」(藤原氏)