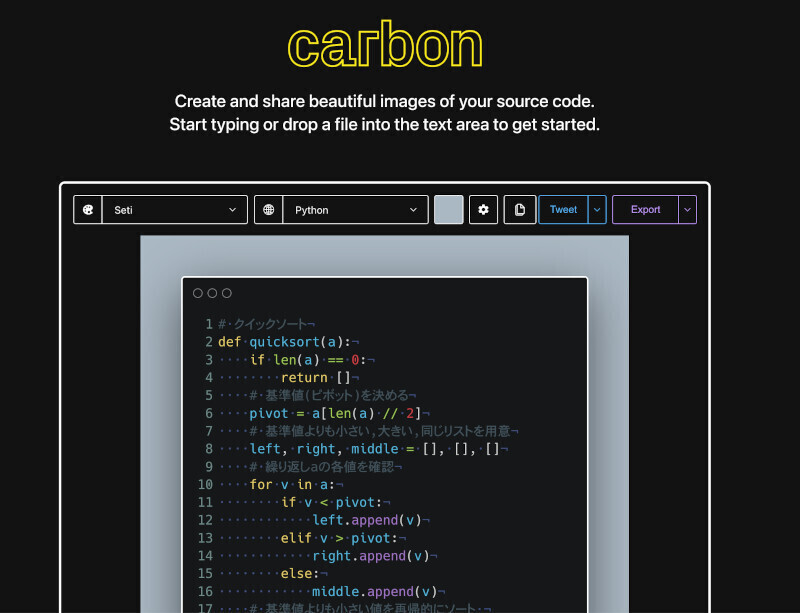GMOインターネットグループは1月26日、自社イベント「GMO 渋谷 FUTURE 2024 - GMO SONIC Warm Up」を開催した。同イベントは1月27日、28日に開催された音楽フェスティバル「GMO SONIC 2024」の前夜祭に位置付けられたもので、飲食ブースの設置や、DJのスティーヴ・アオキ氏を招いたクラブセッションなど多数の催しが行われた。
その中から本稿では、東京大学 大学院 工学系研究科 人工物工学研究センター 技術経営戦略学専攻 教授の松尾豊氏が登壇した特別講演の模様をお伝えする。
2023年のAI旋風を振り返って「時代が何倍速にもなって進んでいる」
冒頭から松尾氏は、ChatGPTに代表される2023年のAIブームを振り返った。OpenAIら海外ベンダーの大規模言語モデルのパラメータ数は1兆以上にまで拡大し、巨大化の一途をたどっている。国内ベンダーにおいても大規模言語モデルの開発は進みつつあるが、松尾氏は「100億パラメータくらいのモデルが多く、もっと大きくなるはこれから」と見通しを述べる。
「ChatGPTの台頭以降、複数の企業がものすごい勢いで新しい大規模言語モデルを開発しています。国内外でもいろいろな動きがあり、時代が何倍速もの早回しになって進んでいると感じます」(松尾氏)