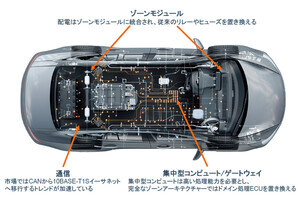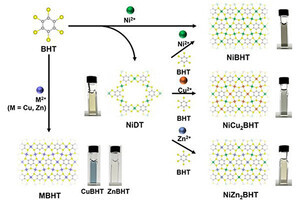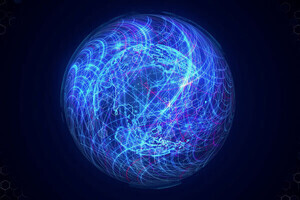スポーツ番組の中継を見ていると、大きなカメラを持ったカメラマンがたくさん現場にいる。しかし、テクノロジーが進化した今、スポーツ中継も遠隔操作により、これまでよりも効率よく最低限の現場スタッフで中継することが可能になりつつある。
そうした中、TBSテレビとWOWOWはクラウドサービスとしてAmazon Web Services(以下、AWS)を活用して、現場のカメラをリモート操作する「クラウドプロダクション」により、中継番組を制作している。
今回、TBSテレビ メディアテクノロジー局 未来技術設計部 原拓氏とWOWOW 技術センター技術推進ユニット 馬詰真実氏に、クラウドプロダクションの仕組みやメリットについて聞いた。
コロナ禍の密回避で注目が高まる
両社がクラウドプロダクションに本腰を入れたのはコロナ禍だったという。コロナ禍では「密の回避」が叫ばれていたが、多くのスタッフが膝を突き合わせる番組制作の現場はかなり密度が高い状態だった。そのため、それ以前から番組制作の効率化のために進めてきた、遠隔操作による番組制作への注目が一気に高まった。
また、昨今は地上波放送に加えて、オンデマンド放送、動画配信など、中継コンテンツの提供形態は多様化しており、配信先に適した形でなるべく多くのコンテンツを制作したいという狙いもあった。
そこで、「番組制作の効率を上げながら、省力化も図るため、クラウドプロダクションに取り組むことにしました」と、原氏は語る。
効率化を実現できても、番組のクオリティが落ちたり、スタッフの負荷が高くなったりしては意味がない。
上述したように、スポーツ中継の現場は、複数の選手を同時に撮る場合、選手の顔にズームする場合、試合の流れをまとめて放送する場合など、さまざまなシーンの放送に対応するため、多くのカメラがあり、それらを切り替える必要がある。
加えて、スポーツは土日など日時が集中するため、リソースの増減を自由に行えるクラウドサービスは適しているそうだ。
独自開発のプロトコルでネットワークの遅延を回避
両社のクラウドプロダクションは、AWSを介して、リモート拠点から現場のカメラを操作し、番組制作を行う。リモート拠点では、制作担当、スイッチング・リプレイ・CGなどの担当、カメラ担当など、複数の役割のスタッフが働いている。
原氏によると、クラウドプロダクションにおいては、現場スタッフとはインカムで会話をしながら連携し、また、リモート拠点の人はゲームコントローラのようなデバイスでカメラなどを操作するそうだ。
馬詰氏は、クラウドプロダクションの最大の課題として、「ネットワークの遅延」を挙げる。「これまでのクラウドプロダクションは現場とベースの間に大きな遅延がありました。中継番組ならではの難しさです」(同氏)
ネットワーク帯域の遅延を最小限にするため「Live Multi Studio」を応用することにした。これは、両社が独自で開発した双方向型超低遅延プロトコルだ。
原氏に、クラウド基盤としてAWSを選択した理由を尋ねたところ、「クラウドプロダクションにおける実績があり、クラウドサービスプロバイダーとしての信頼感があるからです」という答えが返ってきた。
コンテンツの質向上、職人技の最大活用を実現
クラウドプロダクションですべて制作した初めての番組が、今年3月に開催された全国選抜高校テニス大会だ。同番組は、WOWOW YouTubeチャンネルで配信が行われた。
馬詰氏は、テニス大会の映像について、「視聴者は選手の表情が見たいと思っており、視聴者に共感してもらえるように表情を映すことは重要です。そのような細やかなカメラワークも、クラウドプロダクションでは変わらず実現できます」と語る。
つまり、クラウドプロダクションは、現場に配置する機材も削減しながら、視聴者が欲している映像を撮影することができるというわけだ。
また通常、現場には7、8人のスタッフがいるところ、この時、現場にいたスタッフは2、3人だったという。明らかに省力化が図られている。
原氏は省力化の効果だけでなく、制作者の作業効率の向上も実現していると話す。
「現場に出向く従来のやり方では、スタッフは1カ所でしか働くことができませんでした。しかし、クラウドプロダクションがあれば、1人のスタッフが複数の現場の作業をこなすことができ、職人技を最大限に生かすことができます」
さらに、馬詰氏は、「これまでだったらコストを考えると中継できなかった映像も、クラウドプロダクションを利用すれば中継できるケースがあります。映像の特性に応じて、クラウドプロダクションを活用していきたいです」と話す。
これまでになかった新たな映像の世界に向けて
そして、原氏と馬詰氏は「クラウドプロダクションは今がスタートです」と話す。例えば、カメラでボールをトラッキングして追うことは現在の課題だという。そこで、AIを活用して球を追う動きについてカメラを制御することを検討しているという。
前述したように、コストの問題で中継できなかったコンテンツを放映できるようになると、スポーツ選手やチーム、ファンにとって喜ばしいだけでなく、新たにコマーシャルを流されるようになり、マネタイズの面でも貢献が期待できるかもしれない。
クラウドプロダクションは、クリエイト、デリバリー、マネタイズの3つの側面において、新たなチャンスを切り開いてくれるというわけだ。実際、「Live Multi Studio」は来年に一般提供が予定されている。
原氏は、今後の展望について、「AIが大きなムーブメントとなっているので、よりよい演出や効率化に活用していきたいです。また、クラウドプロダクションによって、これまで届けられなかった(カメラの)アングルワークにもチャレンジしたいです」と語る。
馬詰氏は、「まだ知名度の低いスポーツや学生のスポ―ツなど、そのようなジャンルに、もっとクラウドプロダクションを広げていきたいです」と語る。
コンテンツを作る側だけでなく、見る側にもメリットをもたらすクラウドプロダクション。新たなクリエイティブな世界を広げるテクノロジーとなりそうだ。