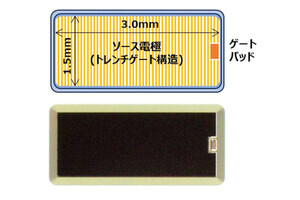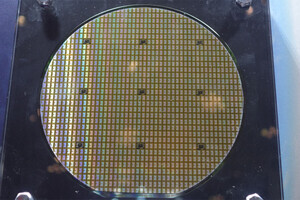米Teradataの日本法人、日本テラデータ(以下、テラデータ)は12月8日、特に生成AIに着目して今後の展望を語る説明会をオンラインで実施した。本稿では、本国でCTO(Chief Technology Officer)を務めるStephen Brobst(スティーブン ブロブスト)氏と、日本法人の代表取締役社長である高橋倫二氏の2人が予測する、2024年の動きについて取り上げたい。
Teradata CTOが予測する2024年のAI - 人間と機械のインテリジェンスを融合すべき
2023年を振り返ると、ChatGPTが一般公開されるなど一気に生成AIの波が押し寄せた年であった。まさに「生成AI元年」と呼んでも差し支えはないだろう。特にChatGPTがこれほど広く世間に受け入れられた要因は、自然言語(私たちが普段使っている日本語や英語などの言語)を用いたチャット形式のインタフェースと、0円から使える使用コストの低さにもある。
そうした中、11月にOpenAIのCEO サム・アルトマン氏の退社が報じられたかと思えば、Microsoftが同氏の受け入れを表明し、最終的にはOpenAIに復帰した。生成AIを取り巻く業界は激動の1年を迎えた。
Stephen氏は生成AIに関する調査結果を引用して、その実態について以下のように説明した。
「現在ナレッジワーカーの8割以上が日常業務にChatGPTを使っているようだ。しかし、そのうち68%の人は上司にChatGPTを使っていることを明らかにせず、多くの人が隠れて使っている。組織内で生成AIを利用するポリシーを徹底できていないのだろう」
こうした2023年の動向を受けて、同氏は「2024年はあらゆるところで今年以上に生成AIが使われるようになるだろう」と予測している。単にブラウザ上でプロンプトを入力するのではなく、さまざまな業務アプリケーションの中にAPI経由で組み込まれていくというのが、同氏の見立て。
また、生成AIに限らずAIやML(Machine Learning:機械学習)は、その質や信頼性がこれまで以上に求められるようになるという。アウトプットの理由を説明可能なAIや、AIにバイアスが入らないような配慮も進むはずだ。
さらに、2024年は実証実験のフェーズから産業化、そして社会実装へ大きく舵が切られる。汎用的なAIではなく各業界に特化したAIが使われるようになり、ROI(Return On Investment:投資利益率)が重視される。
AIの活用の拡大に伴って、AIの学習のためにも生成AIは有効に使われるそうだ。それは、AIの学習データセットを生成AIで生み出せるようになるからである。
「外れ値の扱いやリスクへの対応など配慮すべき点はあるが、生成AIで学習データを生み出すメリットの享受は2024年のトレンドとなるだろう」とStephen氏は語った。
これまで、データ量の多さが企業価値を生み出すとの考えに基づき、data as an asset(資産としてのデータ)の戦略を進めるてきた企業もあるだろう。しかし、そうしたデータの扱い方に対してStephen氏は警鐘を鳴らす。
「データウェアハウスにデータをためていくことが重要なのではなく、意思決定のためにデータを使うべき。どれだけの量のデータを保有しているかではなく、どれだけ良い意思決定がデータによってもたらされたかの方が大事だ」(Stephen氏)
同氏は"AI"という略語に関して、さまざまな解釈を紹介してみせた。一般的にAIといては「Artificial Intelligence(=人工知能)」だが、これを「Automated Intelligence(=自動化されたインテリジェンス)」ととらえると、人間が行う処理を自動化してコスト削減や業務効率化が図れる。
「Augmented Intelligence(=拡張されたインテリジェンス)」ととらえると、人間のインテリジェンスと組み合わせたより良い意思決定も可能となる。人間は計算機械よりも想像力やクリエイティビティが優れている反面、計算機械は人間よりもデータの処理や統計的な処理に優れている。
人間のインテリジェンスと人工的な機械のインテリジェンスをうまく組み合わせて、インテリジェンスの範囲を拡張していくことで、単に自動化されたインテリジェンスよりも優れた成果を出せるようになるという。
Stephen氏は今後のAIの役割について、以下のように述べて説明を結んだ。
「これまでは予測的なAI、つまり過去のデータから将来のデータを予測するようなAIが主流だった。しかし来年以降は、人間がこれから取るべきアクションを提案する、処方的なAIが現れるだろう」
日本は他国より生成AI活用が5年は遅れている
続けて、高橋倫二氏が国内でのAIの動向について紹介した。同氏によると、2023年は多くの業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)に関するAIプロジェクトが立ち上がったようだ。その多くはPoC(Proof of Concept:概念実証)や単発のプロジェクトが多く、組織全体ではなく一部の組織のみでの取り組みだったようだ。
これに対し、2024年は日本でもより具体的な生成AIの活用が進みそうだ。特に、取引先や顧客との連絡、受発注の自動化、マーケティングの自動化、不具合の検知などの業務で進むようだ。全社員が使えるような生成AIの共通プラットフォームの整備も始まるという。 2023年の「生成AIを使っています」から、2024年は「生成AIでビジネス成果が出ています」へと、多くの企業が変化を遂げるだろう。
高橋氏は日本固有の課題として、データサイエンティストの不足を挙げた。72%の企業が自社にデータサイエンティストが不足していると感じており、73%がデータサイエンティストの質に満足していないと感じているという調査結果もあるようだ。
「欧米では社内にデータサイエンティストが数千人いる場合も多いが、日本ではまだ数十人といった状況だ。日本はデータやAIの活用が遅れていることは明らかで、欧米よりも5年は遅れているとの指摘もある。日本は人材育成ももちろん進めるべきではあるが、それ以上に1人当たりの生産性を高めるイノベーションが求められる」(高橋氏)