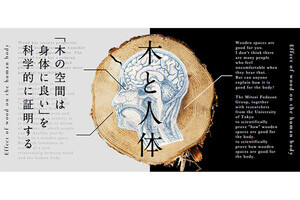フローラルやオリエンタル、フルーティ、ウッディー、スパイシーなどさまざまな香りが世の中にはある中で、なんとなくこんな香りが好きだと感じてはいるものの、自分の好みの香りをはっきりと認識し、それを言語化までできる人は少ないのではないだろうか。筆者も、自分好みの香りを見つけるためにさまざまな種類を試し、結局のところ自分がどの香りが好きかわらないままになってしまったことがある。
そうした人間の感情を揺さぶる重要な要素でありながらあいまいな五感の1つである嗅覚と密接に関わりのある「香り」を言語化するサービスを提供しているセントマティック。香りを言語化するということはどういうことなのか? 同社の代表取締役社長 CEOを務める栗栖俊治氏にその取り組み内容についてお話を伺い、実際に言葉によって香りの印象を視覚化してくれる「KAORIUM(カオリウム)」を通じて得られる超感覚を体験してみた。
香りを言語化することで得られる体験の拡張
セントマティックが提供している「KAORIUM」は、香りのデジタルカウンセリングから香りを言語化してくれるサービスで、香りと言葉の融合体験により自分好みの香り商品に出会うきっかけを創出することを目指したものとなっている。
このKAORIUM開発につながる着眼点として、「言葉は五感で得た体験をさらに拡張してくれる効果がある」ことに目を向けていたという栗栖氏。
例えば、食べ物を食べることによって得る美味しいという感覚はあいまいなものである一方で、食べ物と言葉を組み合わせた食レポによりその食べ物の美味しさが言語化されると、同じ感動でも具体性がより増して美味しさが想像しやすくなる。このように、言葉を加えることで体験の豊かさが増したように感じる感覚は誰もが理解できるはずだ。
そうしたところに着眼点をおいた同社は、「世界にあふれる香りを日々の豊かさとして感じられる未来づくり」をテーマに、香りがもたらす情動的な価値についてリサーチを進めていく中で、香りをよりわかりやすく体験できるデバイスの開発を決意。香りはあいまいで捉えどころがなく、いい匂いということは分かるものの、微妙な違いが分かりづらい、そもそも選び方もわからなければ、好みの香りをどう表現すればいいのかもわからないといった課題がある中で、AIを活用した分析を進めていくことで、個々人がもつ香りの感じ方をあらゆる表現幅でデジタル化していったとする。
この香りの言語化で1番難しい点は、表現軸の幅広さだと栗栖氏は語る。香りを表現する際に、雰囲気で表現する人もいれば、食べ物で表現する人、色で表現する人など表現方法そのものが異なるほか、その感覚の認識は人それぞれであり、そうしたギャップに対してうまく整合性をもたせることが重要となるものの、その精度向上には多くのサンプルを集める必要があり、そのための時間と労力が必要だったという。
香りを表現している言葉の中には、多く選ばれやすいものもあれば、あまり選ばれないものもあるとしており、そうした評価結果をもとにした改善を進め、AIの精度を向上させていくことで、より個々人の感覚で香りを言語化できるように試行錯誤していると栗栖氏は語っていた。
香りと言葉の融合「KAORIUM」をいざ体験
KAORIUMは1人がけのテーブルほどのサイズのデバイス(卓上サイズのコンパクトタイプもある)で、ベースとなる16種類の香りを閉じ込めたビンが置かれている。実際にKAORIUMを体験するべく前に立ちテーブル表面に映し出されている画面をタップすると、ベースとなる香りのビンがおいてある部分に印が点灯し、その印がついた数種類の香りを嗅いでみるところから自分の好みの香り探索が始まる。
そして1番好きな香りのビンを所定の場所に置くと、その香りの印象がAIによって解析され、「すっきり」「みずみずしい」「清楚」などさまざまな表現幅の言葉で可視化されていく。この段階で捉えにくかった香りをよりクリアに感じることができる仕組みになっている。
そして、1番しっくりくる香りの表現を画面上で選択すると、次はその表現に合った複数の香りのビンに新たな印が点灯する。そこで改めて、上記で行った工程を、何度か繰り返して行っていく。この繰り返し行っていく作業を行うことで、それまでは同じカテゴリと済まされてしまいそうな香りであっても、さまざまな表現の言葉でより具体的で的確な好みに絞っていくことができる。
それらの選別を経て最後に、AIが総合的に分析を行い好みの傾向を判断。選んだ好みの香りにタイトルをつけ言語化してくれると共におすすめの香りも3種類ほど紹介してくれる。
筆者は「青空に泳ぐ鯉のぼり」のような香りが好きだという診断結果であった。今まですっきりした香りが好きだと思っていたがその表現の幅が広がったと共に、具体的なラインナップをおすすめしてもらえることであらゆる香りを試さずとも自分の好みに直結し、香り選びが簡単で楽しくなると感じた。
この香りのタイトルはAIの言語処理によって行われるため、パターンがあるわけではなく、個々人が選んだ表現によって生成されるのだという。
セントマティックが考える香りが生み出す可能性
同社は、香りの持つ効能や香りと言葉が結びつくことで起こる化学反応について東京大学(東大)農学生命科学研究科の東原和成 教授と共同で研究を行っており、どのような香りが左脳や右脳をはじめとする脳にどのように作用するのかなどあらゆる視点から調査しているという。
香水やお酒などの香りが重要視される商品の一部にはソムリエという存在もいるが、すべての店舗にそうしたソムリエ資格を持つ店員を配置するのは現実的には難しく、かつインターネットで購入する人も増えたことで新たな香りに挑戦する人も減っているとのこと。
そうした中で、好みの香りの軸を教えてくれるKAORIUMは、ほかの香りへの挑戦心が芽生えるきっかけとなるとともに、新たな自分の好みを知るきっかけにもなるだろう。
実際に行われたフレグランス専門店「NOSE SHOP」での実証実験では、自分の好きな香りに出会えることはもちろん、言語化されることで他人との比較ができて楽しかったといった、香りと言葉の融合体験がもたらす真の意味での香りの持つ豊かさを感じる人が多かったという。
また、米国フロリダ州で開催された「World Perfumary Congress」や資生堂とのコラボ、日本酒のおすすめを診断する「日本酒ソムリエ」などさまざまな実証が行われており、どの取り組みでも集客効果や売り上げが向上することが確認されているとのこと。
企業側にとっても今までは万人受けするであろう商品をまずはおすすめしていたものが、顕在化されていなかったニーズとなる言葉を導出できるようになるため、商品開発に役立てたり、個々人に合わせておすすめを提供できたりと、消費者側からも企業側からもポジティブな声があがっているという。
「的確に香りを選ぶことが可能となり、期待を超える香りづくりを実現できるよう今後も精度を上げていき、日本にとどまらず世界に香りと言葉の融合体験を届けたい」と栗栖氏は将来展望を語っていた。