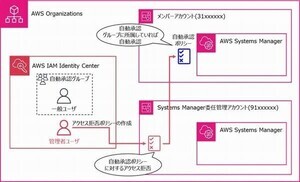今日、ITベンダーが注力しているテクノロジーに「AI」「クラウド」がある。AIに関しては、OpenAIと提携するMicrosoftが話題作りで先行しているが、Amazon Web ServicesやGoogleも独自技術の開発に余念がない。
では、クラウド市場はどうなっているのか。企業向けクラウドベンダーを自負するOracleが9月に開催した年次イベント「Oracle CloudWorld(OCW)2023」で、米Oracle バイスプレジデント OCI担当プロダクトマーケティングのLeo Leung氏、日本オラクル 取締役 執行役 社長の三澤智光氏が語っていた、同社のクラウド戦略についてお届けしたい。
Oralcleの重点戦略の一つ「分散クラウド」
Leung氏はOracle Cloud Infrastructure(OCI)の方向性として、「Oracleはハイパースケーラーであり、あらゆるワークロードを支えたいと思っている」と語っていた。
そこで戦略上、重要となるのが分散クラウドだ。それを実現する仕組みとして、Oracleは1年前のOCWで、パートナー企業がOCIを提供できる「Oracle Alloy」を発表した。分散クラウドにより、「汎用のサービスをさらに効率よく提供できる」とLeung氏。「これまで規制などの制限によりクラウドに移行できなかった顧客もクラウドを活用できるようになる」と、同氏は続けた。
Oracle Alloyの事例として、Oracleが誇るのが野村総合研究所(NRI)だ。基調講演でLarry Ellison氏が触れるなど、重要な事例になっている。
三澤氏によるとNRIはOCI専用リージョン「Oracle Dedicated Region Cloud@Customer(DRCC)」を東・西に、そしてAlloyを東・西に導入するという。これにより、「日本企業がマネージする本格的なクラウドというニーズに応える」と説明する。なお、DRCCがOracleが設計と運用管理を行うのに対し、Alloyは設計はOracle、運用管理はNRIが行う。
NRI以外にも、Alloyの事例として欧州の通信企業が政府向けに導入する例などが出てきているという。さらに、Alloyを評価中の企業は複数あり、「業界に特化してサービスを提供する、あるいは地域を特化してサービスを提供するという2つのタイプがある」とLeung氏は述べた。
競合のMicrosoftおよびRed Hatと提携
分散クラウドに関するニュースとしては、今年のOWC直前に発表したMicrosoftとの提携もある。この提携は、Microsoft Azureのデータセンター内でOCIをデプロイする「Oracle Database@Azure」を展開するというもので、Leung氏は性能、管理、商業の3つの面でメリットがあると話した。
「Oracle Database@Azureでは、Oracle DatabaseがAzureのリソースのように振る舞うことから、性能でのメリットが得られる。また、AzureにOracle Databaseが統合されるため、運用と管理の点でもAzureのサービスのように扱うことができる。そして、既存のAzureの契約でOracleのBring Your Own License(所有するライセンスの持ち込み)やOracle Support RewardsプログラムなどのOracle Databaseのメリットを享受できる」(Leung氏)
分散クラウドの狙いは、顧客をクラウドに移行すること。「Goldman Sachsの調査では、エンタープライズワークロードの31%しかクラウドに移行していない」とLeung氏。「信頼するプロバイダーを使ってクラウドに移行する、Oracleのテクノロジーを必要とするMicrosoftの顧客がクラウドに移行するという2つのアプローチでこの問題の解決できる」と、同氏は説明した。
OWCではMicrosoft以外にも、Red Hatとの提携を発表。Red HatとはOCI上でRed Hat Enterprise Linux(RHEL)を動かす「Red Hat Enterprise Linux on OCI」を年初に発表、そして、OWCではOpenShiftにも拡大した。「Red Hatとの提携により、顧客に選択肢を提供する」とLeung氏。
OCIを選ぶメリットとして、先述の分散クラウドへのアクセスを挙げた。「パブリッククラウド、政府クラウド、専用リージョンで動かすことができる。また、メモリや処理能力を具体的に指定して動かすという柔軟性もある」とLeung氏は述べた。
両社との提携について、Leung氏は「MicrosoftとOracleが提携するなんて、少し前なら考えられなかったこと。競合関係に変わりはないが、今回は協業する」と述べた後、「Oracleは顧客の需要がある領域で、その需要を満たすために取り組む」と続けた。
OCIに新たなコンピュートインスタンスを3種投入
さらに、OWCのOCI関連の発表事項として、Leung氏は新しいコンピュートインスタンスを3種類導入することを紹介した。
1つ目は、高性能、ハイエンドの位置付けとしてNVIDIA H100 GPUを搭載した新しいアクセラレーテッドコンピューティングインスタンスだ。OCI Superclusterとプラグインで接続できるのも特徴で、LLMのトレーニングなどに適しているという。
2つ目はNVIDIA L40S GPUを搭載したインスタンスで、小さめのモデルや推論向けと位置付ける。まずは限定的に提供を開始し、2024年に一般提供にする。
3つ目はARM/Ampereを搭載したインスタンスで、消費電力とコスト性能比に優れる。位置付けとしては汎用向けで、まずは限定提供となる。
「この6~9カ月でx86ファミリーのリフレッシュを進めるとともに、新しいAMDベースのインスタンスも発表した。今回新たにアクセラレーテッドとARMベースのリフレッシュも行う」と、Leung氏はOracleのコンピュートインスタンスに対する積極的な投資を強調した。
AIやクラウドの開発で、進化するOracle
日本企業のクラウドについては、三澤氏が次のように語っていた。
「データがすぐに使えるようにモダナイゼーションをすすめようという動きは、北米に劣っていない。生成AIの対応に追われる中、データの整備の重要性はさらに増すだろう」
OracleはAIスタートアップのCohereと提携しているが、これにより、「(顧客は)データの整備をきちんとやっておけば、Cohereのような賢い生成AIがあり、ベクターデータベースに企業データを入れることでAIを活用できるようになる」と三澤氏。データを整備し、高速に読み込んだり、検索できたりするようにしておくことが、AI活用では重要になるという。
OracleはOWCで、「Oracle Database 23c」の新機能として、AIベクトルを活用したセマンティック検索機能、Retrieval Augmented Generation(RAG)のサポートなどを発表した。
「Oracle自身が変わりつつある。もはやデータベースだけの企業ではない」と三澤氏、そのような進化ができる背景として、「3000億ドルレベルの高い時価総額であるからこそ技術投資が可能。Oracleが莫大な資金を投じて開発したAIやクラウドを、顧客が使わない手はない」とアピールしていた。