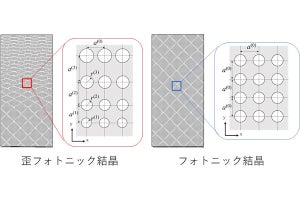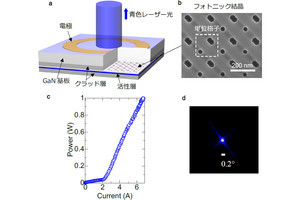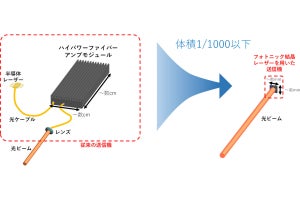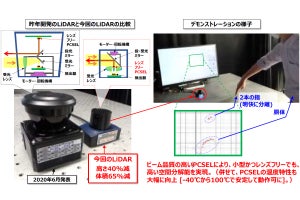信州大学(信大)、科学技術振興機構(JST)、理化学研究所(理研)の3者は10月24日、2次元物質の「無機ナノシート」が水中で周期的に配列した機能性液体に対し、磁場中で「温度グラジエント」(今回の研究では、容器の上部と下部でそれぞれ異なる温度で加熱すること)を与えることでシートの配列を制御でき、色が重ね合わさった複雑な構造色を実現可能であることを見出したと発表した。
同成果は、信大 学術研究院 繊維学系の佐野航季助教(JSTさきがけ研究者)、信大大学院 総合理工学研究科繊維学専攻の小川大輔大学院生、理研 創発物性科学研究センター 創発生体関連ソフトマター研究チームの石田康博チームリーダー、同・詹軼陽特別研究員(研究当時)らの共同研究チームによるもの。詳細は、ドイツ化学会刊行の機関学術誌の国際版「Angewandte Chemie International Edition」に掲載された。
可視光の波長(約380~約780nm)程度の周期を有する微細構造である「フォトニック結晶」は、特定の波長の光を選択的に反射することで構造色を示すことが知られており、その発色原理は特定の波長の光を吸収する色素や顔料とは異なるため、耐褪色性・耐久性、環境調和性、色調の制御可能性などに優れるとされ、ディスプレイやセンサ、偽造対策、構造色インクなど、さまざまな応用が期待されている。
しかし、1種類のナノユニットにより1ステップで作製されたフォトニック結晶の構造色は単一の反射ピークを示すため、構造色の反射スペクトルを自在に設計・制御することは困難だとされている。これまで、構造色の反射ピークのシャープ化やワイド化、ピーク位置の制御などは実現されてきたが、色の複雑性・拡張性を付与できる「ピーク数の制御」は実現できていなかったことから、研究チームは今回、ピーク数の制御を試みることにしたとする。
今回の研究では、厚さ0.75nm、横幅が数μmの二次元物質の酸化チタンナノシートを利用したという。同シートは、水中では、静電斥力とファンデルワールス力が長距離で競合する結果、一定間隔を保った周期構造を自発的に形成するほか、余剰イオンの除去や水分散液の加熱などにより、シートの間隔を伸縮させることができ、構造色の反射ピークを短波長側にも長波長側にもシフトさせられるという。また強磁場を加えることでシートの向きを一方向に揃えることも可能だともしている。
具体的には酸化チタンナノシートの水分散液(0.5wt%)を容器に入れて、強磁場中で容器上部が55℃、部が75℃になるような温度グラジエントを30分間与え、室温まで冷却して磁場から取り出す作業を実施。その結果、約1057nmにあった幅広い単一の反射ピークが1000nmと1164nmの2つに分裂したとするが、強磁場中の容器内全体で75℃となるような均一温度での処理では、シートの向きが一方向に揃うために、元の反射ピークがよりシャープになったともしている。
また、温度グラジエントで処理されたシートの配列構造に対し、シート間隔に対応する2つの波長のレーザーを利用した共焦点レーザー顕微鏡の反射モード測定が行われたところ、異なるシート間隔を有する2つの領域を三次元的に可視化することに成功。一方、均一温度で処理されたシートの配列構造に対して同様の測定を行ったところ、領域全体に渡って2つの波長のレーザーが均一に反射されることがわかり、単一のシート間隔を有することが示唆されたとする。
さらに電子顕微鏡観察により、温度グラジエントで処理されたシートの配列構造では、高温域のシート間隔は低温域のそれよりも小さいことも確認されたという。
-

(a)酸化チタンナノシートと(b)ナノシートが形成する周期構造の温度応答性の概念図。(c)酸化チタンナノシートの水分散液に対して、磁場中で均一温度(上)と温度グラジエント(下)を与えた際に生じるナノシートの配列変化の概念図 (出所:理研Webサイト)
研究チームでは、これらの測定によって得られたパラメータを利用して理論的な反射スペクトルの予想を実施したところ、実験で得られたものとよく一致することも確認。反射ピークが分裂するメカニズムに関しては、加熱によって約60℃を超えるとシート間隔は急激に減少するが、高温領域と低温領域の境界に水だけからなる空間が生成されるのを避けるため、低温領域のシート間隔が拡大される結果、元の間隔よりも収縮した領域と拡大した領域が同時に出現すると考察されたとするほか、実際に反射ピークの分裂現象は、温度グラジエントがしきい温度である約60℃をまたぐ場合にのみ発生したとしている。
このほか、酸化チタンナノシートの濃度を変化させて温度グラジエントで処理を施したところ、どの場合においても反射ピークの分裂が引き起こされ、2つの色が重ね合わさった複雑な構造色が実現されたとするほか、温度グラジエントおよび均一温度で繰り返し処理することによって、構造色を可逆的に変化させることにも成功したとする。
-

(a~d)酸化チタンナノシートの水分散液に対して、磁場中で均一温度(a・c)と温度グラジエント(b・d)で処理した際の構造色のスペクトル(a・b)と共焦点レーザー顕微鏡の画像(c・d) (出所:理研Webサイト)
なお、研究チームでは、今回の研究成果について構造色を自在にデザインし、次世代色材の創成につながる新たな指針となることが期待されるものだと説明している。