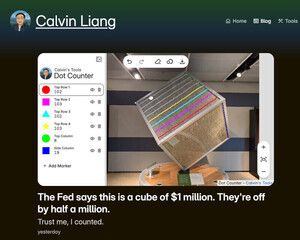興味本位だった生成AIを仕事に活用するという動きが広がっている。AIに仕事を奪われるという危惧もあるが、まずは自分の仕事を楽にしてくれるという点でその便利さを実感している人もいるだろう。だが注意は必要だ。
生成AIは生産性を向上してくれるが……
コンサルファームのBoston Consulting Group(BCG)とWharton Business Schoolの調査では、BCGのコンサルにChatGPT-4を使ってもらうグループ、使わないグループと分け、文書作成、マーケティング、分析、創造性、説得力などが問われるタスク18種を割り当て、成績を見た。結果は、生成AIを利用したコンサルは利用していないコンサルと比較すると、平均12.2%多く、25.1%速く、40%高い品質でタスクをできた。
この調査では、単に業務が改善するだけではなく、もう1つの発見があった。AIがスキルレベルの差異をある程度緩和してくれるのだ。実験を開始するときにスコアが最も低かったコンサルは、AIを使用することで成績が43%も改善したという。
スコアが高いトップコンサルもAIを使用することで成績が向上したものの、その率はそれほどでもなかったことから、スコアが低い(パフォーマンスが低い)コンサルを、スコアが高いトップパフォーマーに近づけるという点で、AIは期待できるという結論を導き出している。
スタンフォード大学とマサチューセッツ工科大学が行った研究でも同じような結果が出ている。この研究では、Fortune 500の業務ソフトウェア企業のカスタマーサービス担当者5000人を対象に1年間、AI導入時のパフォーマンスを調べた。AIを利用する担当者は、そうではない担当者と比べて生産性は14%高かったという。また、スキルの低い担当者はAIを使うことで35%速く仕事を完了できるようになったという。
この2つの調査から、記事では「従業員の数を増やすことなく成果をさらに改善でき、収益を高めることができるかもしれない」としている。高度なスキルを持つスタッフはAIではできないような専門性の高い業務に集中することもできる。
人間の能力を低下させず導入する方法を探るべき
一方で、より高いパフォーマンスが要求されるようになり、スタッフの中にはストレスを感じる人が出てくるかもしれない。
AIが労働市場にどのような影響を与えるのかを調べたIndeedの調査も紹介する。調査では5500万件の求人情報と2600件の職種スキルを調べたところ、20%近くの仕事が「かなり強く」生成AIの影響を受けると考えられることがわかった。
“かなり強い”レベルとは、その仕事に必要なスキルの80%以上をAIがこなす可能性があるというもの。また、45%の求人情報は「中程度」の影響を受けるーー。つまり、AIがその仕事に必要なスキルの50~80%をこなすことができるという。
AIが複雑な仕事ができるか否かの検証では、ビジネスでのAI活用についての教育を提供するSection Schoolが、取締役会の前にチャットボットにスライドについてのフィードバックをもらうという実験を行った。
チャットボットによりバラつきはあったようだが、AnthropicのClaudeのアウトプットは「人間の取締役会とほぼ同じレベル」とのこと。マクロの経済環境を理解し、適度に野心的で、大きな図で見た時の機会を示すことができたという。
これが意味することとして「いつの日か、複雑な意思決定、戦略、計画を評価するにあたって、AIアドバイザーが人間の専門家やアドバイザーの役割を果たしたり、部分的に置き換わる可能性がある」とのことだ。
AIが生産性アップに寄与する一方で、課題も指摘する。リクルーターのパフォーマンスにフォーカスした調査では、高度なAIを利用する担当者は怠惰になり、不注意によるミスが増えたり、判断力が劣るような場面が増えたというのだ。
「AIの質が高まるにつれ、人間は努力したり注意を維持するインセンティブが低下し、AIが人のパフォーマンスを補強するのではなく、代用するようになる」とこの調査はまとめている。人がAIに依存しすぎるようになると判断力を発揮できなくなる可能性がある、と警笛を鳴らす。
このような諸刃の剣としてのAIの側面は、AIが業務に組み込まれるにつれて今後さらに明らかになっていくと予想されている。「AIを適切に利用すれば生産性を向上できるが、人間の能力を低下させるような方法で導入しないように慎重になるべきだ」とバランスの重要性を強調している。
VentureBeatが「AI assistants boost productivity but paradoxically risk human deskilling」という記事で、AIと生産性についてさまざまな調査を紹介している。