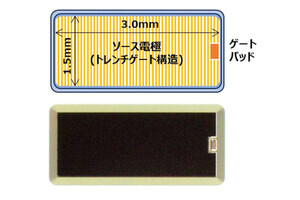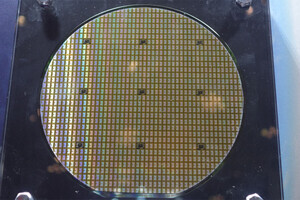昨今、テクノロジートレンドとして度々話題になっているWeb3。中でも注目を集めるのが暗号資産として知られるトークンやNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)だ。だが、実際に購入や運用をしている人が増えているかというと、まだまだ一般的とは言えないだろう。そんなトークンやNFTを現実世界に絡めてマスアダプション(一般に普及)させたいと取り組みを進めているのが、Super Massive Globalだ。2023年11月には、位置情報×陣取りゲーム×Web3が融合したスマートフォンゲーム「MASSIVE WORLD」のクローズドβ版のリリースを控えているという。
同社 CEO 内藤慎人氏に、暗号資産の現況、MASSIVE WORLDの狙い、Super Massive Globalが描くビジョンについて伺った。
お祭りが過ぎた今、普及には課題が残る
内藤氏は現在のトークンやNFTの市場を「お祭りが過ぎ、本来の使われ方を落ち着いて見極めようとしている状態」だと表現する。メディアなどで高額なNFTアートが話題に上ったように、昨年前半まで、NFT市場はバブル状態にあった。しかし一時の盛り上がりが過ぎ去った今、市場は鳴りを潜め、多くの投資家や企業家がその動向をうかがっている。ではなぜ、市場は一気に広がらなかったのか。同氏はミクロとマクロ、2つの視点での課題があると言う。
ミクロの視点では、購入のハードルの高さが大きな課題だ。NFT自体はすでに10年以上テクノロジーとして存在しているが、まだまだ購入のプロセスに難しさが残る。また、税率や、販売による利益の扱いも国によって異なり、法整備も進んでいない。
「業界自体がまだ未成熟の状態です。インターネットが出てきた頃のように、こういうテクノロジーに興味がある人はどんどんと取り入れていきますが、知識がなく、詳しくない人が始めるにはまだまだハードルが高いでしょう。また、NFTで何ができるのかと言うと、革新的なものはまだ出てきていないと考えています。その点でも、一般化には程遠いのです」(内藤氏)
マクロ視点での課題は、「よく分からないものというイメージの先行」だと内藤氏は指摘する。トークンやNFTに関する話題は資金調達の話ばかりで、実際にきちんと運用されているプラットフォームはあまりないと言い、「儲け話が先行してしまい、用途が不明」だと続けた。
では、海外ではどうなのか。内藤氏は自身も足を運んだWeb3.0サミット「TOKEN2049 Singapore」(2023年9月13、14日開催)の様子を挙げ、来場者からの注目度の高さと同時に課題を感じたと語る。Super Massive Globalが参入しようとしているブロックチェーンゲーム関連のブースもあったが、ここでもNFTを流通させるプラットフォームが整備されていなかったり、現実世界とリンクするモデルではなかったりするプロジェクトが多かったという。
狙いは「マーケティング用データ取得」と「推し活の対価還元」
このような市況の中、Super Massive Globalは、「世界中の好奇心をつないで、誰もが簡単に価値の創造と分配が楽しめるコミュニティプラットフォーム」の提供を目指し、11月には、「位置情報」「陣取りゲーム」「Web3」が融合したスマートフォンゲーム「MASSIVE WORLD」のクローズドβ版のリリースを予定している。
同ゲームでまずユーザーは性格診断を行い、「スタン(アバター)」を作成する。そして共通の「好きなもの」で集まるコミュニティに所属し、陣取りバトルや交流を行う。一定期間内に獲得した陣地に応じて、まずコミュニティ単位でトークンを獲得、さらにユーザーの貢献度に応じてコミュニティで獲得したトークンが分配される仕組みだ。トークンは2種類あり、アバターのデコレーションや、陣取りの際に必要なアイテムの購入に充てられるものと、金銭的な報酬として得られるものがある。2024年以降は、リアルでの決済機能との連携や、現実世界とリンクしたアプリ内の土地やアートNFTの購入につなげられるようにする計画だ。また、コミュニティには「フェイブ」と呼ばれるマスコットキャラクターが存在し、コミュニティの活動量やトークンの保有量に応じてフェイブが成長(動く、声がつくなど)していくことで、推し活の醍醐味も味わうことができるようになっている。
Super Massive Globalがこうしたゲームをリリースする狙いはどこにあるのか。内藤氏が挙げるポイントは2つだ。
1つは、新しいテクノロジーやエンタテインメント性を利用して、ユーザーの行動データを取得することである。対象となるのは、移動、移動に伴う決済、心拍などの健康情報、趣味嗜好といったデータだ。ゲーム経由で取得したデータを企業や店舗に活用してもらい、「低予算でもマーケティングができる状態をつくりたい」と同氏は意気込む。
もう1つの狙いは、ブロックチェーンの技術を用いた新たな価値の創造である。ここで言う新たな価値とは、ユーザーに行動の対価を還元することだ。「好きな人やグループ、キャラクターに対して、人がかける熱量は計り知れない」と内藤氏は言う。従来、ユーザーがコンサートへ行ったり、グッズを買ったりと「好きなもの」、いわゆる“推し”を応援する中で、その行動量に応じた対価はなかった。だが、MASSIVE WORLDでは共通の推しを掲げるコミュニティで活動した熱量が、推しが具現化したフェイブの成長やトークンという対価で還元される。
「位置情報ゲームはいろいろとありますが、対価が返ってくるプラットフォームは我々が唯一なのではないかと考えています」(内藤氏)