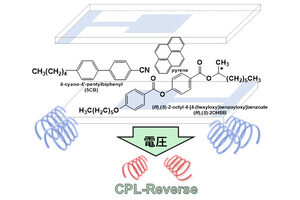SAS Institute Japanは7月27日、東京都内で、アナリティクスやAIの最新動向を紹介するイベント「SAS Innovate Tokyo」を開催した。 本稿では、今年4月に代表取締役社長に就任した手島主税氏による、日本市場に向けた成長戦略に関する講演の模様をお届けする。
冒頭、手島氏は同社が「AI&アナリティクスカンパニーとして、未知の課題に挑戦することをフィロソフィーとしている」と述べ、同社の社名に「institute(研究所)」が含まれている意義について、次のように説明した。
「データの世界では、自動化やモデルだけではなく、意思決定できるまでに専門性が求められる。われわれはその専門性を提供できる」
進まない日本のデータ活用にSASが貢献できることとは?
手島氏は、「情報通信白書令和2年版」のデータを引き合いに出し、日本のデータ活用の現状を指摘した。日本ではデータの活用が行われているものの、データ加工でつまずいていて、分析にまで行きついておらず、結果として、意思決定に活用するまでに至っていないという。
一方、同社が今年初めに12カ国2414名を対象に実施した調査では、企業の回復力においてアナリティクスが貢献すると考えられていることがわかっている。
こうした中、手島氏は「意思決定、戦略策定、製品戦略にデータを活用するとなると、データの品質と活用の頻度が重要になる」と述べた。
これらを実現するため、SASは以下の5つの責務を果たすという。
- インタークラウドAI&アナリティクス
- 意思決定の全体最適化
- ユビキタスな統合プラットフォーム
- 透明性と信頼性
- 社会的イノベーションへの貢献
「インタークラウドAI&アナリティクス」とは、データを活用する環境を意味する。手島氏は、「企業が必要とするデータはさまざまな場所に分散している。こうしたデータをどんな言語でも生かせるような環境を構築しているのはSASだけ」と説明した。
また、手島氏は「特定の人だけがデータ活用をするのではなく、共感を促す方法論の下、すべての共通の理解を持つことが必要」とも語っていた。
日本の変革に向け、SASが果たす6つの役割
さらに手島氏は、日本の変革に向けて、SASが果たそうとしている役割として、以下の6つを挙げた。
- 戦略的パートナーシップ
- 業務特化型ソリューション拡充&開発
- アナリティクスサービス事業モデル発足
- カスタマーサクセス
- 信頼性、透明性、ガバナンスへの責任
- Future Readyエコシステム発足
例えば、「業務特化型ソリューション」に関しては、2022年9月に、塩野義製薬と医薬品業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けたデータ解析コンサルティングサービスの開始を発表している。塩野義製薬は同社のSAS Viyaを中心とした解析環境の活用によって得たノウハウを同業他社に提供する。
今年5月には、AIを活用した業界別アナリティクス・ソリューションに今後3年間で10億ドルを投資することも発表されている。
また、アナリティクスサービス事業モデルに関しては、アナリティクスをビジネスとしてどうやって展開できるかを検討し、事業モデルを立ち上げるプログラムを日本にも提供していくという。
日本の未来のために「Future Readyエコシステム」発足
そして、最後の「Future Readyエコシステム」は、今回発表されたものだ。手島氏は、Future Readyエコシステムについて、「多様化に対する答えとなる。2030年には、AI人材の需要と供給のギャップは14.5万人なると言われている。どこでもアナリティクスを体験できるように、日本の未来創造のためにエコシステムを発足した」と説明した。
「Future Readyエコシステム」のポイントは、「アカデミア産学連携」「活用&組織設計方法論」「プラットフォーム」「人材ファクトリー」の4点となる。
横につながるための仕組みである「プラットフォーム」は、「Analytics Explorer」として近日発表される予定だ。また、「人材ファクトリー」である「SAS Hub」は、高度人材育成に対し貢献する。
手島氏は結びの言葉として、「われわれは好奇心を力に地球規模の道の課題に挑戦し、日本へのアイデンティティを世界に打ち出していきたい」と語っていた。