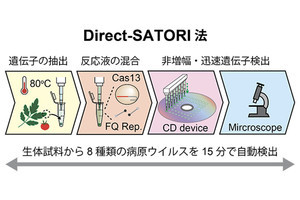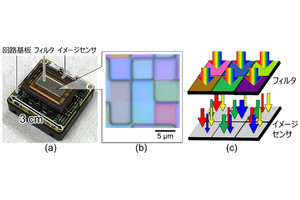東北大学は7月19日、トマト品種「桃太郎」の上部と下部を切断・再結合する自家の接ぎ木処理を行ったところ、処理を行わない桃太郎と比較して、茎頂組織において染色体ヒストンならびにDNAのメチル化を介したエピゲノム変化が生じることに加え、その結果として、ストレス耐性をはじめとする多数の遺伝子発現に変化が生じ、乾燥ストレス耐性が獲得されることを見出したと発表した。
同成果は、東北大大学院 生命科学研究科のマリア・イサベル・フェンテス・メルロス大学院生(研究当時)、同・東谷篤志教授らの研究チームによるもの。詳細は、DNAおよびゲノム関連の幅広い全般を扱う学術誌「DNA Research」に掲載された。
植物の接ぎ木は、土台となる植物に違う種類の植物(穂木)をつなげる技術として、古くから行われてきた。農作物の栽培においては、果樹などでは効率の良いクローン繁殖技術として、またナス科やウリ科の作物などでは強く丈夫な根を台木とし穂木に優良な実をつける品種をつなぐなど、広く利用されており、それにより強く丈夫な台木の根によって養水分の吸収が旺盛になるとともに、病害抵抗性が付与されるなど、穂木の優良な実の収穫量を増やす効果もあるとされている。
また、近年の研究からは、化学物質・ストレス・そのほかの外部からの刺激などのさまざまな要因によって、染色体ヒストンタンパク質のメチル化やアセチル化修飾、DNAのメチル化修飾など、ゲノム上に後生的なエピゲノム変化をきたし、多数の遺伝子発現に変化が生じることもわかってきたという。
そうした中で研究チームはこれまでの研究として、トマトの品種「桃太郎」の上部を穂木として、異なる品種の根を台木とした接ぎ木に加えて、桃太郎の苗木を切断し再結合させることや桃太郎の異なる苗木間での接ぎ木(自家接ぎ木)を実施。3週間かけて活着後、12日間給水を止める乾燥ストレスによる負荷を与えるという実験を行っており、その結果、対照群として接ぎ木が行われなかった桃太郎の苗木では、給水を再開しても、それらの生存率はわずかに約2割であること、一方、強い根を台木として接ぎ木したトマトでは100%の回復率が確認されたこと、ならびに桃太郎の自家接ぎ木でも約6割において回復し、同時に乾燥ストレス負荷直前の茎頂組織において多数の遺伝子発現が変化していることを見出していたという。
これらの結果を踏まえ、今回の研究では、自家接ぎ木処理において生じた遺伝子発現の変化が、後生的なエピゲノム変化が生じた影響なのかどうかの調査を行ったという。
具体的には、自家接ぎ木処理から1週間が経っただけの活着間もない苗木の茎頂組織における、ヒストンH3の4番目ならびに27番目のリジン残基のトリメチル化、さらに、DNAシトシン塩基のメチル化のエピゲノム変化について解析を実施したところ、染色体の活性型エピゲノム修飾ならびに不活性型エピゲノム修飾のいずれも3000を越える遺伝子で、自家接ぎ木処理により有意に変化していることが確認されたという。
また、接ぎ木から3週間後のしっかりとした活着が確認された茎頂組織においても、ストレス耐性に深く関わる熱ショックタンパク質「HSP70」を含む800を越える遺伝子において発現が上昇、77遺伝子で発現の低下が確認されたとしており、研究チームでは、自家接ぎ木の影響が、長期にわたり後生的に受け継がれることが示されたとするほか、ストレス耐性をはじめとする多数の遺伝子発現に変化が生じ、乾燥ストレス耐性が獲得されることが見出されたとしており、今回の研究成果は、植物の接ぎ木の切断と再結合、その後の傷害再生の過程におけるストレスが、次なる新たなストレスに対しても、耐性を付与する後生的なエピゲノム変化を誘導したものと考えられるとしている。
なお、研究チームでは、古くから用いられてきた植物の接ぎ木の手技において、その切断・再結合の傷害再生の過程におけるエピゲノム変化が、乾燥ストレスのほかの非生物学的ならびに生物学的ストレスに耐性を付与することができるのか、トマトのほかの植物種においても同様に観察されるのか、今回の研究成果が接ぎ木における新たな視点を加えるものとして、今後のさらなる展開が期待されるとしている。