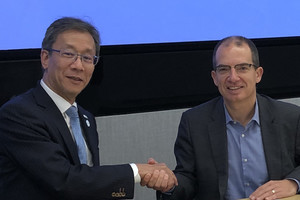東京大学は7月14日、自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥多動症(ADHD)とが、同一人物中で合併する神経メカニズムについて調べた結果、これまでの見解とは異なり、単純な両者の合併症ではないことが生物学的に解明されたと発表した。
同成果は、東大 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)の渡部喬光准教授、同・渡邉大地インターンシップ生(現・米・カリフォルニア大学バークレー校 認知神経学部所属)らの研究チームによるもの。詳細は、脳と神経系に関する全般を扱う学術誌「eNeuro」に掲載された。
ASDとADHDの症状は一見すると対照的なため、かつての国際的診断基準では合併しないものとされていたが、臨床現場から両者それぞれに類似した症状が同一人物に見られるという報告が相次いだことから、最新版の診断基準ではASD/ADHD合併症(以下「合併症」)という概念が認められた。しかし、合併症を生み出すメカニズムの研究が進んでいないことから、研究チームは今回2種類のデータ駆動型解析を用いて検討することにしたという。
今回の研究では、ある特定の脳活動状態から別の脳活動状態への変化は1回の測定につきどのくらいの頻度で観察されるのか、それぞれの脳活動状態はどの程度の時間現れるのか、といった神経ダイナミクスに関わる指標を計算することで、合併症の神経生物学的特徴を描出することを目指し、さらに、機能的MRIで測定された「安静時脳活動」(目を開いた状態でじっとしてぼーっとした状態での脳活動)を解析。合併症当事者、純粋なASD当事者、純粋なADHD当事者、そして定型発達者を比べることで、合併症の神経基盤が探索された。
その結果、まず純粋なASD当事者は定型発達者に比べある特定の脳神経ダイナミクスが過度に安定化しており、その安定化の程度がASDの重症度、特にコミュニケーションの症状の重さを示していることが分かったという。
-

ASD症状と関連している神経ダイナミクス。(A)赤い太矢印は、ASDで低下している神経ダイナミクスの経路。(B)同経路の神経ダイナミクスは、ASD当事者とASD/ADHD合併症当事者で減少していた。(C)その遷移頻度が低下していれば低下しているほど、ASDのコミュニケーションの症状も重症化していた(出所:東大 IRCN Webサイト)
一方、純粋なADHD当事者では、独自の脳神経ダイナミクスについて過度な活性化が確認されたとする。さらに、その活発な神経活動変化は、左半球の下頭頂溝の不安定な活動が、注意のコントロールに関わる「背側注意ネットワーク」の活動を乱した結果として生じていることも判明。このようなメカニズムで過度に不安定化された脳神経ダイナミクスは、ADHD当事者の注意の不安定さや認知の過活動性と相関していたとする。
-

ADHDの神経ダイナミクスとその症状。(A)青い太矢印は、ADHDで活発化している神経ダイナミクスの経路。(B)同経路の神経ダイナミクスはADHD当事者ではより頻繁に発生していた。ASD/ADHD合併症当事者でそれほどはっきりしていなかった。(C)その遷移頻度が上昇していれば上昇しているほど、ADHDの過活動に関する症状も重症化していた(出所:東大 IRCN Webサイト)
合併症当事者に関しては、まず純粋なASD当事者のパターンと同じ神経ダイナミクスに過度な安定化が見られたという。そしてそれは、合併症当事者のコミュニケーションに関する症状の重さを示しており、合併症当事者に見られる社会疎通性に関する症状は純粋なASD当事者と同じようなメカニズムによって生じていることが解明された。
一方、純粋なADHD当事者に見られた過度に活発な神経活動パターンは、合併症当事者においては不明瞭だったという。さらに合併症当事者のADHD的な症状とも相関していなかったとした。
代わりに合併症当事者はまた別な独自の神経ダイナミクスパターンが活発化しており、これは純粋なADHD当事者には認められないものだという。さらに、これを引き起こしていたメカニズムも純粋なADHD当事者には認められないものだったとした。頭頂葉領域ではなく上前頭前野の不安定な神経活動が、背側注意ネットワークとは別の「前頭頭頂ネットワーク」の神経活動を乱すことで、この合併症に特徴的な神経ダイナミクスが生まれていたという。加えて、この合併症当事者に固有な過度な神経ダイナミクスは、ADHD的な症状(認知の不安定性)と相関していることも突き止められたとする。
-

ASD/ADHD合併症におけるADHD症状と関連する神経ダイナミクス。(A)紫の太矢印は、ASD/ADHD合併症例で活発化している神経ダイナミクスの経路。(B)同経路の神経ダイナミクスは、合併症グループで特に頻繁に発生していた。(C)その遷移頻度が上昇していれば上昇しているほど、ADHDの認知は安定し、症状は軽快していた(出所:東大 IRCN Webサイト)
今回の研究成果から、合併症と見えるもののうちASD的な社会疎通性に関する症状は、純粋なASDのそれと同じメカニズムで支えられていることが推測されたとする。一方、ADHD的な症状は、純粋なADHDとは異なるメカニズムが働いている様子を観察。つまり、合併症当事者のADHD的な振る舞いは症状としては純粋なADHD当事者のそれと類似して見えるが、実際には異なる神経基盤の動きによるものの可能性があるとした。これらの結果は、独立した異なる2つのデータセットでも再現されたとする。
もし今回の研究成果が正しければ、合併症に関する概念を多少変更する必要があるばかりではなく治療に関しても注意が必要になるかもしれないという。研究チームは、特に合併症当事者のADHD的な症状に対して純粋なADHD当事者に対ししばしば処方するのと同じ薬物療法を実施して効果が十分期待できるのかといった点については、今後、臨床的にも検討していく必要が出てくるかもしれないとしている。