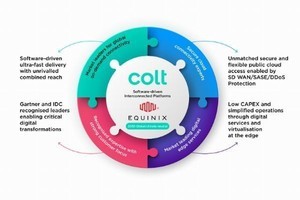エクイニクス・ジャパンは7月10日、都内で記者説明会を開き、2023年度における事業戦略説明会を開催した。説明会ではエクイニクス・ジャパン 代表取締役社長の小川久仁子氏がプレゼンテーションを行った。
25周年を迎えた米エクイニクス
まず、小川氏は現状として「6月で米エクイニクスは25周年を迎えた。これまでを振り返る200年代はWebやSNS、SaaSなど消費者が需要をけん引し、2010年代にクラウド技術の登場で消費者ベースからエンタープライズ企業がデジタル化への変革が加速した。そして、2020年~2022年はパンデミックに伴うDXが加速し、2023年はAI技術が実用化されてビジネスへの適用がスタートしており、デジタル化の波というものにAIが触媒になったと感じている」との認識を示した。
そして、エクイニクスの25年を小川氏は振り返り「1998年にIX(Internet Exchange)からビジネスをスタートし、2003年~2007年にかけてグローバルでデータセンター(DC)の拡大に注力してきた。テクノロジーの変遷とともに2014年ごろまではクラウドの入り口を全世界のDCに配置し、エコシステムを確固たるものにした。2019年~2020年は、パンデミックでデジタル化が加速する中、Network Edgeやベアメタルサービスなどのデジタルサービスの開発に着手し、2021年にはDX業界で初めて、2030年までにクライメイトニュートラル(気候中立)になることを宣言し、2022年にはアフリカに進出した」と述べた。
エクイニクスのグローバルにおける2022年~2023年上半期のハイライトとしては、グローバルエリアの拡大、パートナーシップ、デジタルサービスの3つをポイントとしている。
エリア拡大については、APAC(アジア太平洋)ハイパースケーラー向けDCである「xScaleデータセンター」を韓国で2カ所、すでにシドニーでは初となる同センターを開設し、インドネシア、マレーシアにはIBX(International Business Exchange)データセンターの建設を発表している。
EMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)は、ナイジェリア、ガーナ、コートジボワールの西アフリカ地域に拠点を持つMainOneの4つのDCを買収し、南アフリカ(ヨハネスブルグ)ではDCの建設を発表。アメリカ地域ではチリで3カ所、ペルーで1カ所のDCを買収し、コロンビアではDCの建設を発表している。
パートナーシップに関しては、昨年11月に「VMware Cloud on Equinix Metal」、今年6月にさまざまな場所のアプリケーションとデータにクラウド運用モデルを提供する「HPE GreenLake Private Cloud」の協業と、Google Cloudへのセキュアでオンデマンドな仮想接続を提供する「Equinix Fabric」の拡張サービスを発表している。
東京、大阪と国内で着々と整備が進むデータセンター
一方、国内では昨年6月に東京のIBXデータセンター「TY11」の第3フェーズ拡張、同8月に大阪のxScaleデータセンター「OS2x」の第2フェーズ拡張、同11月に大阪のIBXデータセンター「OS3」の第2フェーズ拡張をそれぞれ完了し、東京の同データセンター「TY15」の建設を発表。また、今年6月には東京のxScaleデータセンター「TY13x」を開設した。
パートナーシップとしては、今年3月に英Oxford Quantum Circuits(OQC)と都内にあるエクイニクスのデータセンター「TY11 International Business Exchange(IBX)」を通じて、量子コンピュータを世界中の企業に商用提供することを発表。さらに、4月には日立製作所と、協業強化に向けてMOU(Memorandum of Understanding:基本合意書)を締結している。
加えて、デジタルサービスも拡充しており、今年4月にNVIDIAとエンド ・ツー ・エンドのデータサイエンスやAIワークロードのテストやプロトタイプ作成を支援する環境を提供するプログラム「LaunchPad」の国内での本格展開を始動し、ネットワーク機能仮想化をオンデマンドで利用できる「Network Edge」を大阪エリアで提供を開始。
2023年度の事業戦略
こうした取り組みを背景に2023年度に同社が注力する戦略は「AIとPlatform Equinixの融合」「エコシステムの進化」「サステナビリティの実践」の3つだ。
同社におけるプラットフォーム構想は、グローバルに展開するデータセンターのフットプリントをベースに、相互接続するためのインターコネクションサービスを使いながら、データセンターサービスとデジタルサービスを融合し、顧客が同社のプラットフォーム上で相互接続しつつ、デジタルエコシステムに参加して、ビジネスを推進してもらうという。小川氏は「当社のプラットフォーム自体がマーケットプレイスになるという構想のもと、さまざまなサービスを開発している」と説明した。
その中核となるPlatform Equinixはグローバルなデジタル・インフラストラクチャ・プラットフォームであり、分散化、クラウドへの接続性、エコシステムの活用、オンデマンドへの高い需要、サステナビリティの高い要求の5つの分野において顧客の要求を満たすものと位置付けている。
AIとPlatform Equinixの融合については、AIの実装で必要な要件であるデータ、クラウドへの近接性、低遅延、自動化の効果をPlatform Equinix上で最大化するという。すでにデータにもとづいた交通安全ソリューションや臨床医手動のヘルスケアAIプラットフォーム、精密でインテリジェントな手術ロボットなどに適用されている。
実際、シドニーを拠点とするAI医療テック企業のHarrison.aiでは同市のIBMデータ戦t-あを活用し、機械学習プラットフォームを支える複数のGPU「NVIDIA DGX A100」システムを設置。これにより、1枚のX線フィルムに124セットの所見を生成し、肺疾患の正確な診断を可能にする胸部X線画像ソリューション「Annalize CXR」を立ち上げている。
エコシステムの進化では、Platform Equinix上での企業とサービスプロバイダーのデジタルエコシステムへの参加を支援。クラウドについてはAWS(Amazon Web Service)やMicrosoft Azure、Google Cloud、IBM Cloud、Alibaba Cloud、Oracle Cloud Infrastructureをはじめとした接続拠点を国内では有している。小川氏は「クラウドへの接続拠点のカバレッジは世界でもトップクラスであり、強みだ」と主張した。
クラウドエコシステムに加え、前述したQOCとの量子コンピューターの活用の民主化や、日立製作所とはハイブリッドクラウドを提供し、DXソリューションの拡充を図っている点も訴求していた。
そして、サステナビリティの実践に関しては、2022年度の進捗として2019年比23%の炭素削減を実現(2030年までに2019年比50%減が目標)し、世界220以上の拠点で平均96%の再生可能エネルギーに対応するとともに、年間平均PUE(Power Usage Effectiveness:DCなどIT関連施設におけるエネルギー効率を測定する指標の1つ)は1.46となった。
引き続き、同社では低炭素エネルギーの採用や高効率な冷却、サーキュラー江尾許斐の導入、ソフトウェアによる最適化・自動化を推進していく方針としている。さらには、さまざまな団体や企業と連携し、デジタルインクルージョンを推進するため「エクイニクス基金」と設けており、2022年9月から5000万USドルの資金を提供している。