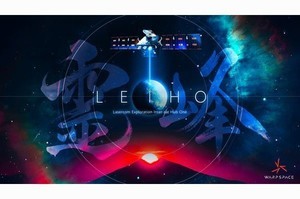近年、各国の政府の後押しもあり、宇宙産業を拡大しようという機運が高まっている。日本政府は2017年に、第4次産業革命下の宇宙利用創造を目指す「宇宙産業ビジョン 2030」を発表している。
また、経済産業省は宇宙基本計画で掲げている「我が国の宇宙産業の規模(約1.2兆円)を 2030年代早期に倍増することを目指す」という政府目標の達成に向け、宇宙機器産業の国際競争力の強化、宇宙利用産業の振興に取り組んでいる。
こうした動きにITベンダーも呼応しており、米マイクロソフトは2020年に宇宙事業「Azure Space」を発表している。当然、IT市場でMicrosoftと肩を並べるAmazon Web Services (AWS)も宇宙産業に参入している。
今回、AWSの宇宙産業に関する説明会が開催されたので、以下、AWSの宇宙産業の最新動向についてお伝えする。説明会には、AWSのサービスを活用するワープスペース、スペースシフト、インフォステラのCEOも参加した。
米Amazon Web Services 航空宇宙・衛星部門Director クリント・クロージャー氏は、「ある調査結果によると、宇宙産業の市場は2040年には1兆ドルに達し、向こう10年間で衛星の数も4倍から5倍に増えると予測されている。こうしたグローバルの状況と同様、日本もエキサイティングな状況にある。例えば、日本政府は国内の宇宙産業を2030年には倍増するという目標を立てており、大きなチャンスがある」と、宇宙産業の市場が拡大傾向にあることを強調した。
宇宙におけるAWSクラウドの活用状況
続いて、クロージャー氏は、宇宙における同社のクラウドサービスに活用状況を紹介した。例えば、オーストラリアでは、衛星画像を活用して、山火事を発火から3分で検知している。
また、米国では衛星画像や宇宙からの信号を解析して、絶滅の危機にある生物が船に近づきすぎている時 その船を所有する企業に警告するという取り組みが行われている。
これらを実現するシステムにAWSのサービスが活用されている。「気候変動、野生動物保護、森林火災の社会課題に対し、AWS上で宇宙とクラウドが一つになって解決している」とクロージャー氏。
そして、クロージャー氏は「宇宙における生成データの増加とともに、地球に伝送されて活用されているデータも増えている。こうした状況では、衛星やロケットではなく、データが重要」と述べた。
AWSを活用して宇宙事業を展開している日本企業
宇宙のデータ活用に関わるビジネスを立ち上げているのが、前述した3社だ。ワープスペースは、光空間通信の技術を活用し、衛星間光通信を軸とした宇宙における次世代通信ネットワーク「WarpHub InterSat」の開発などを手掛けている。
最高戦略責任者/WARPSPACE USA CEO 森裕和氏は、「光を活用して通信容量を増やすことで、地球観測市場の通信のボトルネックを解消しようとしている。また、中継衛星を高い軌道で打ち上げて、衛星画像を取得して中継衛星からデータを下ろすことで、データを常に下ろせるようにしようとしている」と、同社の事業について話した。
今後は、データを下ろす時間を短縮すること、AWSを活用したエンド・ツー・エンドの通信を介してデータを取得するサービスを計画しているという。データはAmazon S3に格納され、ユーザーははCloudFront経由でデータを取得する。
スペースシフトは、衛星データ解析システムの開発、衛星データの解析などに取り組んでいる。今後5年間で、地球観測衛星が2,000~3,000機が打上げ予定であることを見越し、同社は衛星データの活用の幅を広げるため、衛星データ処理のソフトウェア開発に注力している。
代表取締役 CEO 金本成生氏は、スペースシフトの強みとして、解析が難しいとされるSAR衛星データのAI解析技術を開発していることを挙げた。SAR衛星は対象物の反射波を用いて画像を作成するため、モノクロ画像であり、直感的に画像判読が困難だという。
そこで、スペースシフトはSAR衛星のデータをAIで自動解析可能にしている。現在、SAR衛星の数は少ないが、2025年には超小型SAR衛星網が150~200機体制になるとのことで、世界中でほぼリアルタイムで観測することが可能になるという。
金本氏はAWSの活用事例として、ウクライナ情勢について、AIによるSAR衛星画像の解析をAWS上で実行していることを紹介した。アーカイブデータがAWSの環境に格納されており、アルゴリズムを走らせると データを解析できる仕組みになっている。
また、同社はJ-SPARCによる「人工衛星データ活用による広告の高度化を通じた需給連携事業」に参画している。同事業では、AWS IoT Greengrassを活用している。
インフォステラは、クラウドベースの宇宙利用地上セグメントサービスの開発や提供を行っている。共同創業者/代表取締役CEO 倉原直美氏は、「当社は通信用のアセットを持たない。ステラステーションというソフトウェアによって、アンテナ設備を仮想的に一つのネットワークにして提供している」と、同社の事業について説明した。
蔵原氏によると、現在、衛星は増えたが、衛星通信の標準化が進んでいないため、アンテナ局を使おうとすると個別に交渉する必要があり、手間がかかるという。そこで、同社は異なるインタフェースの地上局を共通のインタフェースとプロトコルで扱えるようにしており、予約と契約を一本化している。
同社は、AWS Ground Station(衛星通信のコントロール、衛星データの処理、衛星運営のスケーリングを行うマネージド・サービス)を導入したことで、ネットワークのカバレッジが拡大したそうだ。
クラウドと宇宙の融合により生まれる新しい経済
こうした宇宙に関わる企業の活発な活動を踏まえ、クロージャー氏は「クラウドと宇宙が一つになるとイノベーションが生まれ、新しい経済が生まれる。今、宇宙でも経済が生まれている。宇宙経済として、地球上と同じことができるようにする必要がある」と述べた。
クロージャー氏は、AWSが、AI、機械学習(ML:Machine Learning)、オートメーション、ロボティクス、エッジコンピューティングを宇宙でも使えるようにしていると説明した。
宇宙におけるエッジコンピューティングの事例としては、「AWS Snowcone」が紹介された。「Snowcone」は今年4月、Axiom SpaceとNASAのISS滞在ミッション「Axiom Mission 1」の一環として、SpaceXの宇宙船「Crew Dragon」に搭載され、「Falcon 9」ロケットで宇宙へ打ち上げられた。
クロージャー氏は、「Snowcone」がISSのミッションに参加するにあたり、衝撃や熱などについて、NASAの宇宙飛行認定を受ける必要があり、認定を受けるまで7カ月かかったと述べた。また、ISSでデータを解析するため、MLモデルの開発も行われた。
クロージャー氏は、宇宙産業における生成AI(Generative AI)の活用についても触れた。同氏は、生成AIについて、「従来のAIは人間よりも早く考えられるが、回答は想定内にとどまる。一方、生成AIは人間の想像を越えて、新しいアイデアを生む」と述べた。
例えば、衛星の画像分析に生成AIを活用することで、モデルの学習が速くなり、速くかつ安く運ぶ形でサービスを提供することを実現できるという。また、生成AIによって最適な飛行経路によるミッション計画を実行できる可能性もある。
クロージャー氏は、「インターネットは一つの会社が作っているわけではない。同様の形で、われわれは宇宙のコンピュートも作っていく」と語っていた。