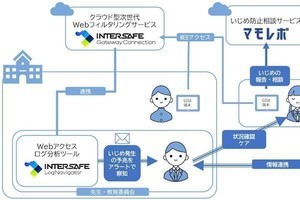マイクロソフトは6月30日、教育関係者向けのオンラインセミナー「Microsoft Education EXPO 2023~これからの教育のかたち~」を開催した。
同セミナーでは、教育業界向けのサービス「Learning Accelerators」(ラーニングアクセラレーター)で利用できる音読練習ツール「Reading Progress」の足立学園(東京都足立区)における活用事例が紹介された。
コロナ禍で始まったオンライン授業で、音読の評価基準を明確化
Learning Acceleratorsは、2023年2月に米マイクロソフトが開催したオンラインイベント「Reimagine Education」で発表された、Microsoft Teams for Educationにて無償で利用できる新サービスだ。
国内では現在、音読の学習・評価ツールである「Reading Progress & Reading Coach」と、児童・生徒の感情のアンケートを取れる「Microsoft Reflect」、Teams上の各種ツールのデータを基に個人やクラス・学校単位でのデータ分析が可能な「Education Insights」が利用できる。
今後はプレゼンテーション向けツールの「Speaker Progress & Speaker Coach」、情報収集のサポートツールの「Search Progress & Search Coach」、「算数・数学」の学習・評価ツールである「Math Progress & Math Coach」が提供される予定だ。各種ツールには同社が開発したAIが活用されており、児童・生徒の課題の取り組みをAIが支援する。
足立学園では、2020年4月にコロナ禍に対応すべくオンライン授業を実施した際に、Teamsの課題機能の利用を開始した。家庭での英語学習の一環として、生徒が音読練習の様子を録音した音声データを基にした音読テストも行っていたが、同テストを続けるうえでは課題があったという。
音読課題を読み上げた音声は1~2分ほどあり、音声を1人ずつ聞いていると時間がかかってしまう。また、音読そのもののフィードバックはできるが、点数を付けるうえでの明確な評価基準を設けるのが難しいため、Reading ProgressとReading Coachの利用を開始した。
足立学園中学校・高等学校の英語科主任で、中学1年生の担任も務める冨岡雅氏は、「Reading Progressの課題配信機能でWordかPDFの文書をアップロードすると、音読課題用のテキストが自動で読み込まれて表示される。単語がうまく読み込まれない場合もあるため適宜修正し、Reading Coachの機能をオンにすれば音読用のテキストの準備は完了となる。動画で撮影されると恥ずかしがる生徒もいるため、基本的にはビデオ撮影の機能はオフにしている」と説明した。
なお、日本語の名前や地名などは正しく発音しても、「誤った発音」としてカウントされてしまうため、採点対象としてカウントしないように修正している。
教師が利用するReading Progressの設定画面では、生徒が課題を提出したかどうかが一覧で表示される。提出が遅れた場合に教員にアラートメッセージを送る設定も可能だ。
1分間で正しく読めた語数を評価し、AIの採点をフィードバックに生かす
生徒には音読課題用のテキストがTeamsで配信される。生徒はテキストの音読を録音してTeams上で提出することで、課題の提出完了となる。提出された音声データはAIが分析し、誤って発音された箇所や、うまく発音されず省略されて聞こえる箇所などが色分けして示される。
冨岡氏は、1分間で正しく読めた語数を評価対象として、AIによる細かな採点内容をフィードバックのヒントとして利用している。
例えば、2023年4月に入学した中学1年生の指導において、書き取りが苦手なものの音読の結果が良い生徒には、「音読がちゃんとできているから、このままがんばっていれば大丈夫だよ」と富岡氏は声掛けしている。文法を理解していても音読がうまくできていない生徒に対しては、「音読をもう少しがんばってみると、もっと理解が深まるよ」などとアドバイスしているという。
「音読を正しく行えるということは、単語を正しく認識して文脈をつかみ、文書の流れや意味の切れ目を理解しながら読めるということだと考えており、音読の結果を英語学習の声かけに活用している」(冨岡市)
今後はEducation Insightsのデータ分析機能を用いて、生徒の学習傾向や変化を個別に把握したり、クラス全体の平均結果と個人の成績の推移を比較したりして英語学習の指導に生かす方針だ。また、AIによる採点制度を高めるために日本語特有の人名、地名、カタカナ語などの修正も継続していく。
このほか、Teams上で音読の練習を自主的に取り組めるよう、テキストの音声読み上げ機能である「イマーシブリーダー」も利用する予定だ。
「課題で利用するテキストのファイルをTeamsでアップロードし、イマーシブリーダーを起動。正しい発音を聞いてから、Reading Coachの機能をオンにして、自分の音読音声をチェックすることができる」と冨岡氏。
約2年間、Reading ProgressとReading CoachによるAI採点を続ける中で、冨岡氏は音読テストのデジタル化の効果を実感している。
2022年における中学3年生の最後の課題配信では、1分間に140語以上の単語を正しく読めた2人の生徒が外部の英語検定試験で2級に合格した。一方で、準2級に合格できなかった生徒の多くが1分間に正しく読めた単語数は80語未満だったそうだ。
冨岡氏は、「検定の合否に関してはさまざまな要素が関わるが、検定結果に音読の影響が出ていると思う。自分に必要な単語の発音練習など、個人の習熟度に応じて学習を行えるのがICTの利点だ」と語った。