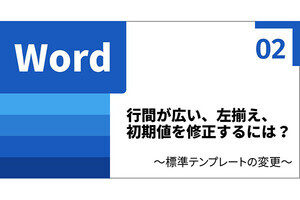コロナ禍で百貨店業界は大きな打撃を受けた。三越伊勢丹も例外ではなく、基幹店である伊勢丹新宿本店は、2020年度に大きく落ち込んだ。しかし、2022年第3四半期には統合以来最高の売上高を計上、V字回復を果たしたという。その背景にあるのは何か。
3月22日に開催した「流通ニュース×TECH+ セミナー リテールDX 店舗運営の最適化から生まれる顧客体験価値」に、同社 営業本部 オンラインストアグループ長を務める北川竜也氏が登壇。「三越伊勢丹のDXと直面した課題」と題し、講演を行った。
コロナ禍で実感した、変わるものと変わらないもの
まず北川氏は同社の現在の状況について説明した。一時期コロナ禍で苦戦したものの、現在は「新宿伊勢丹、日本橋三越など基幹店を中心にお客さまが戻っている」と言う。その背景には、ロイヤリティの高い顧客の存在がある。同社の発行する「MIカード」で言えば、ポイント優待率10%という顧客層の購買が好調だ。この点を同氏は、「我々がショッピングを通じて提供している、エンタテイメント性、非日常性を感じていただいている」と分析する。
コロナ禍で、百貨店業界は大きな変化をしなければならない状況に追い込まれた。来店して購入するというそれまでの”当たり前”が、オンライン購入やオンライン接客に変わったことなどを挙げた北川氏は「常識や習慣は、きっかけ次第で簡単に変わってしまうことを実感した」と振り返る。しかし、一方で「本能や本質は変わらない」とも感じたそうだ。三越伊勢丹が創業以来大切にしてきたショッピングにおけるエンタテイメント性や非日常性は、変わらずに支持されており、「我々は本質や本物を届けていくことが重要だと改めて実感している」と続ける。
それを実現するのが、同社にとってのDXだ。
「DXとはコーポレートトランスフォーメーションそのものです。お客さまが求める本物や本質、憧れやワクワクなどの湧き上がってくるニーズを捉え、それらを商品やサービスとして届けるための仕組みを変える、それを支えるためにビジネスモデルや仕事のやり方を変えることなのです」(北川氏)
特に仕事のやり方の変化については、「そう簡単なことではない」と述べながら、「ここにしっかり踏み込んで、業務フローやビジネスモデルを変える、そして変化し続けることがDXの本質と理解している」とした。
売上最大化では対応できない時代に、逆ファネル的発想で挑む
次に北川氏は三越伊勢丹のDX戦略の根底にある考え方を紹介した。ポイントは、「自社の強みをベースに絞り込む」「顧客への提供価値を再定義する」「業務フローを変更し、超短サイクルで仮説検証し、変化し続ける状態にする」ことだ。これを自社に当てはめ、「店舗/人/商品という圧倒的な得意領域にレバレッジを効かせられるデジタルサービスと機能を具備する」「リアルでもオンラインでも、お客さまの期待に応えられる状態にする」ことを定めているという。
顧客の変化と共に、アプローチも変化している。これまでの顧客戦略は「瞬間最大風速を高める」(北川氏)ことであり、前日、前月と比較して売上を伸ばすことが重要だった。しかし、顧客の選択肢は増え、得られる情報も多様化している。
「売上の最大化だけでは対応できなくなりました」(北川氏)
そこで顧客戦略を再定義し、従来のファネル的な発想から、「逆ファネル的発想」に転換したという。具体的には、いかに既存のコアのファン層に、継続的に使いたいという顧客になってもらい、そこから口コミや評判を通じて顧客層を広げていくかだ。
北川氏は、三越伊勢丹の基幹店の売上は近隣5~6区に住む人が50~60%を占めており、店舗のコンバージョンレートは100%を超えているというデータを示す。このような店舗の強みに、オンラインの利便性を掛け合わせるというのが現在の戦略となる。
そこで、基幹店や地域の母店などのリアル拠点とオンラインのシームレス化、百貨店の強みである外商機能の強化などを図っているという。