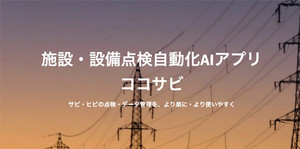建設業界と聞くと、皆さんはどんなイメージを持つだろうか。
本来であれば、国や生活を支える魅力的な産業にもかかわらず、「3K(「きつい」「汚い」「危険」の頭文字をとって作られた略語)」の代名詞的な業界として知られていることもあり、マイナスなイメージを持つ人も少なくないのではないだろうか。
野原ホールディングスが今年2月、全国の大学1~3年生の男女1,000人を対象に行った「建設業界のイメージ」調査では、「建設業界への志望意向」について「受けるつもりはない」が69.1%で最も多い結果となった。このように、「残業・休日出勤が多い」「給料が低い」「デジタル化が進んでいない」といったイメージから、就職活動の際に志望する学生が少ない不人気な業界としてのレッテルを貼られてしまっている側面も否めない。 そんな業界をDX(デジタルトランスフォーメーション)により「働く場所としてもカッコよく、魅力的な、学生の人気業界にしたい」と、建設現場のDXを推進しているのが野原ホールディングスグループCDOの山﨑芳治氏だ。
本誌では前編と後編に分けて、日本の建設業界の現状や今後の建設DXの未来をひも解いていく。前編となる今回は、悪しき風習が残る建設業界の現状とそこからの脱出のヒントを紹介する。
曖昧な設計図を現場で調整している現在の建築業界
野原ホールディングスは、設計事務所やゼネコンを対象とした、BIM関連サービスと専門工事業者への建設資材の販売をメインに展開している建設資材の専門商社だ。
BIM(ビム)とは、Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称で、建設物のデジタルモデルに、部材やコストなど多様な属性データを追加した建設物のデータベースを持たせ、設計・施工・維持管理の各プロセスを横断して活用するため考え方や仕組みを指す。
「BIMを語る上で最も重要なことは、各種の『Information(情報)』を持っているという点です。設計・施工に必要な外形などの情報だけでなく、各種シミュレーションに必要な情報、完成時引渡しに必要な情報、運用段階の情報などを追加・拡張できます。BIMの作成は、建設に特化したデータベースを作るプロセスであり、それは空間を構成する最小単位である建材データの集合体ともいえます」(山﨑氏)
では、BIMを使って、野原ホールディングスは業界にどんな影響を与えていこうとしているのだろうか。まずは、建築業界の現状を解説してもらった。
「よく製造業関係者に驚かれるのですが、建設の現場では、設計図通りに建物ができることがありません。取り合い(建築物などにおいて、異なる構造物が出会う接合部分のこと、またはその接合部分における処置のこと)や納まり(各部材が接合される部分などの総称)は図面に表しきれず、各工程で調整することがほとんどです(施工用に別途、施工図を作成したり)。そのため、例えば、完成後に追加で発生した材料費・労務費など、ゼネコン‐サブコン‐工事業者間での清算行為が複雑化してしまう場合も少なくありません」(山﨑氏)
この説明を聞くまで、筆者は設計図にはかなり細かく数字の記載があり、その通りに作れば建物が完成するのだと思っていたのだが、これは大きな勘違いだったようだ。
「これは日本だけで起きていることであり、海外から見ても不思議に思われているポイントです。このようなことが起きる理由としては、『日本の現場従事者が優秀』ということが最も大きいと思います。設計図が多少曖昧でも、職人が現場でなんとかうまく調整できてしまう。それゆえに、工事に必要な詳細な情報を全て表しきれない従来の図面でも工事を進めてしまうということが、戦後40年以降から慣習化してしまっているのだと思います。これは、従来のやり方では、設計段階で決められる事項が限られているため仕方ない面もあります」(山﨑氏)
人手不足で今の方法は限界を迎える?
しかし、山﨑氏はこうした日本の「(工事に必要な詳細な情報を全て表しきれていない)設計図を現場が調整する」というやり方には限界が来ていると警鐘を鳴らす。
そもそもこの方法がうまくいっていたのは、団塊世代の人手も多かった点がその理由の一つに挙げられるという。しかし現在は、少子高齢化で若い働き手が少ないにもかかわらず、先に挙げたような3Kのイメージから就職志望者も多くない時代に突入してしまっているため、「曖昧な指示を調整する」という無駄な作業に時間を取ることが難しくなっている。
「加えて、『外国人労働者の増加』もこの方法の限界を感じているポイントです。近年、建設の現場では人手不足を補うために外国人労働者を増加するケースが増えていますが、日本独自の慣習をなかなか理解してもらえなかったり、言語の壁があったり、と阿吽の呼吸での現場調整が難しくなってきています」(山﨑氏)
山﨑氏曰くこの慣習を打ち壊し、新たな建設業界の常識を作っていくためには「フロントローディング」が欠かせないキーになってくるという。 「フロントローディング」とは、「プロジェクトの早い段階で建築主のニーズをとりこみ、設計段階から建築主・設計者・施工者が三位一体でモノ決め(合意形成)を進め、後工程の手待ち・手戻りや手直しを減らすことにより、全体の業務量を削減し、適正な品質・コスト・工期をつくり込むこと」と、日本建設業連合会は定義している。
建設プロジェクトの前段階にある設計工程を最重要視する「フロントローディング」に転じることが、これからの建設業の生産性向上に重要であり、それを実現するツールがBIMであると山﨑氏は説明する。
後編では「建設業界はなぜDXに取り組むべきなのか」「建設業界の未来」について紹介する。