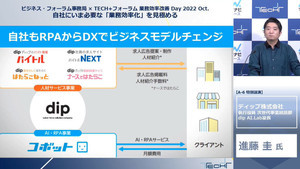アルバイト・パート求人掲載サイト「バイトル」や総合求人情報サイト「はたらこねっと」などの人材サービスで知られるディップ。2019年からはDX事業も展開しているが、ディップに対して“IT企業”、“テックカンパニー”といった印象を持っている人はそう多くないはずだ。
そんなディップが、ここ数年で生まれ変わろうとしている。2021年には同社初となるCTOのポジションに豊濱吉庸氏を迎え、エンジニア組織を強化。当時50名だった開発部は現在100名を超え、今なお増員を続けている。また、縦割り化してしまっていたシステム面では可観測性プラットフォーム「New Relic」を採用し、開発のスピードアップのほかエンジニアの意識向上などにも効果が表れているという。
多くの企業がエンジニアの採用に苦慮する中、ディップはどのようにして短期間でエンジニア組織を再構築し、新たな開発体制をつくり上げていったのか。
執行役員 CTO 兼 商品開発本部 システム統括部長を務める豊濱吉庸氏と商品開発本部 システム統括部 バイトルエンジニアリング部 部長 五月女直樹氏に話を聞いた。
あなたにもできるDX - エンジニアゼロからDXを始めたディップ執行役員が語る「3つのポイント」
テック企業に聞く! 長期インフラ整備計画 - CTO、アーキテクト、インフラ責任者の考慮点
受動的な開発体制から脱却するために
アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」や総合求人情報サイト「はたらこねっと」などを運営するディップは、2019年よりDXサービスの提供を開始。現在は人材サービスとDXサービスの2軸で事業を展開している。
しかし、DXサービスの提供を開始した当時、社内の開発体制やフローは旧態依然としており、エンジニアチームは「バイトル」と「はたらこねっと」を合わせても50名規模。開発のかなりの部分を業務委託やパートナー企業に頼っている状態だったという。
そのような状態では、どうしてもプロダクトの改善スピードが遅くなってしまう。また、決められた仕様に従って開発を進めるだけで手一杯になることが多く、エンジニア自身の主体性も不足しがちだった。
そこで、テコ入れを行ったのが2021年に入社した豊濱吉庸氏だ。同社初のCTOに就任した豊濱氏は、まずエンジニア組織の強化を進めた。
「私が入社した当時、圧倒的に人が足りていませんでした。当社のプロダクト規模を考えるとエンジニアの人数が50人というのは少なすぎます。プロダクトの目的などを考えながら開発を進められる仲間を、もっと増やす必要がありました」(豊濱氏)
とは言え、エンジニアの採用はそう簡単ではない。そもそも世の中の需要に対して供給が足りておらず、さらに数少ない優秀なエンジニアは当然、自身のキャリアアップを考えてもともとITのイメージが強い企業を選ぶ傾向が強い。
そこで豊濱氏は、自らエンジニア関連のイベントに参加するなどして、ディップがDXサービスも提供しているIT企業であることを地道に周知していった。
またその際、聞こえのいい言葉を使わず、自社のリアルな実情を伝えたことも功を奏したのだという。
「入社してからのズレをなくすことが大事だと考えています。例えば、当時の弊社のエンジニア組織は決して完成されたものではなく、むしろこれからつくり上げていくフェーズでした。そうした点を隠すのではなく、むしろ『オープニングスタッフ募集中です!』と伝えることで、ポジティブに捉えてもらうことを心掛けました」(豊濱氏)
増えた人員をいかに活かすか? 全体を“見る”ためにやったこと
IT企業としてのディップをアピールし、さらに自社の状況をありのまま誠実に伝えることで、同社のエンジニアチームは短期間で順調に拡大していった。
次に豊濱氏が取り組んだのは、開発体制の構築だ。大きな変化は、システム統括部内にR&D推進室を作ったことである。
「R&D推進部は、純粋にシステムのことだけを考える部署です。短期的な収益のことだけでなく、プロダクトを長期的に見て改善すべき点を考えられる部署を社内に作れたことは、弊社にとって1つのマイルストーンになったと言えます」(豊濱氏)
R&D推進室と同様の考え方で採用に至ったのが、システムを監視・可視化する可観測性プラットフォーム「New Relic」だ。いくら開発部に人を増やしても、プロダクトの全体像が可視化されていなければ、効率的な人員配置は難しい。New Relicを導入することで、「プロダクトが今どんな状態にあるのか」が明らかになり、それを踏まえて各エンジニアが何を行うべきなのかも明確になっていった。
「具体的にNew Relicで改善したかった課題は3つある」と話すのは、エンジニアリングマネジャーの五月女氏だ。
「New Relicで実現を目指したのは、『人的コストの改善』『システム全体の可視化と監視ツールの浸透』『エンジニアの貢献の可視化』です。これらを全て解決できるツールを探しました」(五月女氏)
ツールの導入が現場に与えた影響
これまでにない可視化・監視ツールの導入に、現場のエンジニアたちはどんな反応を見せたのか。
「会社としてもNew Relicの導入は推進しましたが、それ以上に現場のメンバーが積極的に活用してくれています。エンジニア一人一人が、プロダクトを自分たちで良くしていこうという想いを持っているからではないでしょうか。また、New Relic社の手厚いサポートにも助けられました」(五月女氏)
現在、New Relicはシステムの一部への導入に留まっており、プロダクト全体への導入は今年の9月を予定しているが、すでにその効果はさまざまな場面で表れているという。
例えば、これまでアクセス分析や障害発生時の調査は人手で行っていたため、そもそも調査の依頼をする手間や、情報共有に相応の時間がかかっていた。これが50%ほど削減できたほか、ログ解析に関しても「30~50%の費用削減を見込んでいる」(豊濱氏)という。
また、エンジニアの意識も変わりつつある。
「New Relicという新しいツールの活用方法をエンジニアが自分たちで見出すことで、『これは自分たちのシステムであり、プロダクトなんだ』という想いが強くなり、当事者意識の向上が図れていると感じています。それが、開発スピードの向上にもつながっています」(豊濱氏)
200名規模への増員と完全クラウド化に向けた取り組み
今後はさらに採用を進め、エンジニア組織の拡大を目指すというディップ。具体的には、2025年中に200名までの増員を予定している。人数が増えると育成面が課題になりがちだが、同社では新卒で入社した社員に対して体系的に学べる研修を用意したり、中途入社者に対しては1on1の頻度を上げたりとさまざまな施策を整えている。
もちろん、こうしたシフトチェンジに向けた取り組み全てが順調に進むとは限らない。例えば、これまでにもオンプレミスからクラウドにシステムを移行する際は、経営層の理解を得るのに苦労したともいう。
「経営層からは『今動いているものを、なぜお金をかけて移行するのか』といった意見も出ました。オンプレとクラウドの違いを説明しても理解してもらうのは難しいので、将来的なコストにどれだけ違いが出るのかといった説明をすることで納得してもらいました」(豊濱氏)
今後はサービス全体のクラウド移行を進めつつ、同時にNew Relicの適用範囲も広げていくという。予定では今年中にデータセンターから脱却し、クラウド移行が完了するとのことで、「そこまでいけば、ほぼ完遂と言える」(五月女氏)見通しだ。
豊濱氏がCTOに就任してから2年で、ディップのエンジニア組織は大きく変化した。増員による規模拡大だけでなく、長期的な視点を持って組織体制を整え、全員がシステム全体を見渡せるようにしたことで開発効率の向上だけでなく、エンジニアたちの意識も高まっている。
「サーバにアクセスしてログを探して……といった作業はツールに任せればいい」と豊濱氏は語る。
「『自分がやっている仕事が事業にどう貢献しているのか』という意識を持ってプロダクトをつくるエンジニアがたくさんいる。そういう組織が一番いいと思っています」(豊濱氏)
2025年、主体性を持ったエンジニアが集結し、テックカンパニーと化したディップがどのようにビジネスを展開していくのか。今後の動向に注目したい。