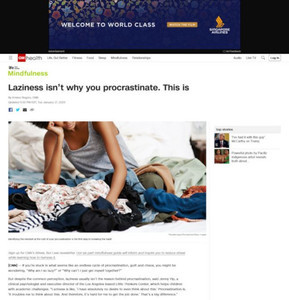米国でQuiet Quitting(静かな退職)がちょっとした流行語になって半年、その後、ハイテク企業の大規模な人員解雇の発表が相次いだこともあり、静かな退職という言葉をあまり見かけなくなった。だが、企業にとって課題であることに違いはない。Rolling Stone Culture Councilが「11 Effective Strategies to Handle ‘Quiet Quitting’ in Your Workplace」という記事で、企業がどのように対処すべきかアドバイスしている。
静かな退職は、退職をするのではなく企業に残りながら、最低限の仕事のみをこなすというトレンドだ。積極的に働いて結果を残す必要はないという仕事への意識の変化に、当時企業の幹部は驚いた。この"静かな退職"、震源地である米国では若者世代のトレンドだが、エクスペリエンスギャップを解消する技術を開発するクアルトリクス(Qualtrics)の「2023年 従業員エクスペリエンス トレンド」によると、日本では40代~50代に多いという。
Rolling Stoneの記事では、このような静かな退職状態の人が増えることで生産性の低下、職場環境の悪化、そして離職率の上昇を招く、と記す。では、静かな退職状態にある人にどのようにして、「やる気」を呼び起こしてもらえばいいだろう?以下に対策を紹介する。
1.表彰制度
「従業員のやる気を高め、組織を成功に導くためには、従業員の承認欲求を満たし、感謝を示すことが不可欠」と記事。感謝の気持ちを伝えるだけでなく、表彰制度のようなものを作ることも提案している。
2.その人の原動力を探る
大体の場合において従業員の仕事や作業が鈍化してきた時は、モチベーションが低くっていると考えることができる。仕事を通じて成長できる、仕事で得られる学びがある、などと感じている時は、自然とやる気が出るはず。であれば、静かな退職状態にある従業員の状態を理解してみよう。
従業員を理解するために、面談は有効な手段だ。できればオンラインではなく対面で、表情を見ながら、考えていることや会社への意見を聞こう。
4.根本的な原因を見つける
やる気が持てなくなっている根本的な原因を探ろう。会社の方向性が見出せない、必要としているサポートが得られない、認めてもらえない、成長の機会が得られない、会社の決断に不満があるなど様々だろう。1対1の面談のほか、定期的にフィードバックをすることで、根本的な原因とそれに対する対応を進めたい。
5.つながりを深める
平行して従業員との関係を見直す。信頼しあえる関係か、共感しあえる関係か。そのためには、数字の話ばかりでなく、何が良かったのか・悪かったのかなど、数字の周辺の話もしたい。
6.自分が問題の一部になっていないか?
ひょっとして静かな退職状態になった従業員が感じていた問題の一部に、自分がなっていないだろうか、自問してみよう。自分が大切にされていない、尊厳が傷つくと感じる職場でやる気がなくなるのは無理もない。あなたの発言を振り返ってみよう。
7.必要なツールや備品を提供する
仕事を効率化するためのツール、従業員が使いやすいツールを提供することも重要だ。特にデジタルツールでは、世代にギャップがある。若い世代は、上の世代のあたりまえが通じない。業務に必要なことをスマホでやりたいという提案があれば、まずはその提案をポジティブに受け止め、セキュリティなどの問題がないのであれば積極的にその環境を提供しよう。
8.目標設定と改善に向けた時間軸を
静かな退職状態にある従業員の、根本の問題がわかり、対策を打ったら、業績の目標を持って退職状態から脱してもらおう。もちろん、継続して1-1の面談をもったり、つながりを深めるための取り組みは行なっていく。