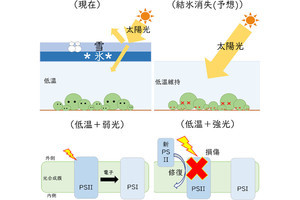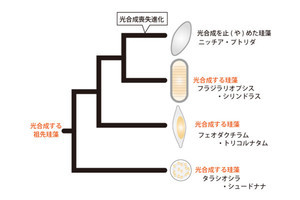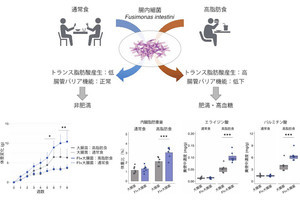理化学研究所(理研)は2月2日、植物が種子に多く蓄える油脂を合成する際に、酵素「LPPα2」と「LPPε1」が協調していること、また葉緑体もその合成に関与しているというこれまで知られていなかったメカニズムを明らかにしたと発表した。
同成果は、理研 環境資源科学研究センター 植物脂質研究チームの中村友輝チームリーダー(東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻 教授兼任)、同・ヴァン・カム・グエン特別研究員らの研究チームによるもの。詳細は、米国植物生物学会が刊行する植物生物学全般を扱う学術誌「The Plant Cell」に掲載された。
油脂は、アルコールの一種であるグリセリンに長鎖脂肪酸が結合したもの。植物に限らず、細胞内小器官の1つである小胞体において合成され、酵素「フォスファチジン酸フォスファターゼ」(PAP)が合成の鍵段階の反応を触媒することがわかっていた。しかし植物においては、同酵素の実体が長らく不明だったという。
モデル植物のシロイヌナズナには多くのPAP酵素の候補が存在するが、そのうちのLPPα2とLPPε1を二重に遺伝子破壊すると、植物体が死に至ることが発見されていた。そこで研究チームは今回、これら2つの酵素が協調して油脂の合成を担っているという仮説を立て、それを確かめることにしたとする。
今回の研究ではまず、これらの酵素がどこに局在するのかが調べられた。すると、LPPα2は小胞体に局在していたのに対し、LPPε1は葉緑体の外包膜に局在することが判明した。続いて、これらの酵素をそれぞれ植物体内において過剰に生産するように操作が行われた。その結果、葉緑体のLPPε1だけを過剰生産させた場合も、小胞体のLPPα2だけを過剰にした場合と同様に、種子の油脂量を20%程度増加させることが確認されたという。また、LPPε1は葉緑体外包膜の特定の部位に局在し、小胞体に局在するLPPα2と近接していることも明らかにされた。
これらのことから、細胞内で異なる場所にある2つの酵素が、葉緑体と小胞体が近接する特定の部位(コンタクトサイト)において協調して油脂合成を司ること、つまり小胞体の油脂合成には葉緑体が関与しているという、油脂合成の新しい仕組みがわかったのである。
今回の研究により、長らく不明だったPAP酵素の実体がLPPα2、LPPε1という2つの酵素であり、これらを植物体で過剰に生産させると種子の油脂量が増加することが確認された。また、これまで油脂の主な合成の場とは考えられていなかった葉緑体が、油脂合成において重要な役割を果たすことも解明された。
油脂は種子の主たる貯蔵脂質であり、植物の光合成でCO2から作られる糖分に由来する。このことから研究チームは、今回の研究成果について、油脂を植物体内に蓄積させる技術開発を通じ、低炭素社会の実現に向けて、大気中のCO2を植物体内で有用な油に変換して活用する"バイオものづくり"に貢献することが期待できるとした。