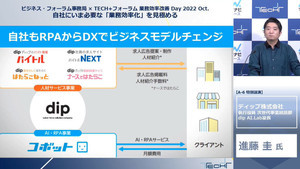大手コンビニエンスストアチェーンのセブン-イレブン・ジャパン(以下、セブン-イレブン)が、今、精力的にDXを進めている。12月13日、14日に開催された「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」に、同社 執行役員 システム本部長を務める西村出氏が登壇。セブン-イレブンのDXのベースとなるデータの利活用について、構築した活用基盤の話を交えて説明した。
【あわせて読みたい】「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」その他のレポートはこちら
セブン-イレブンが「2025年の崖」の克服に向けて進めるDX
2万1300店を超える店舗数を誇るセブン-イレブン。「地域社会を支える存在」として近くて便利なお店を目指している。その実現に向け、全国160を超えるセブン‐イレブンのオリジナル商品だけを製造する工場をはじめ、約160カ所の共配センターを構えるほか、本部・地区事務所がオペレーション、商品、物流管理などを見ている。これに加え、約3000人いるオペレーション フィールド カウンセラー(OFC)が、全国の加盟店の経営を支援する体制だ。
市場の変化に対応しながらこのような体制を維持していくには、DXの推進が欠かせない。また、同社がDXを進める背景には、「2025年の崖」にまさに直面しているという事情もある。2025年の崖とは、経済産業省が2018年に警鐘を鳴らしたレガシーシステム残存によって企業に起こり得る問題を指す言葉だ。西村氏は、「IT黎明期から積極的なIT投資を行ってきたが、クラウド、スマホの普及などの変化に対し、巨大化したシステムでは技術的な乖離が大きくなりつつある」と同社の現状を説明する。
三段構えのDXで目指す姿
セブン-イレブンがDXで具体的に目指す姿は、次の4つから成る。
これらの実現に向けた取り組みは「三段構え」で進めている。まずは「データ利活用の推進」を行い、次に「SaaSの積極活用」、そして「基幹システム再構築」といった具合だ。こうした進め方にした理由については、「AIを使うにしても、さまざまなサービスを構築・再構築するにしても、インプットするデータが整備されていないとDXが上手くいかないと考え、最初にデータの整備から始めた」と同氏は明かす。
講演では、これらの取り組みのうち主にデータ利活用の推進に焦点を当てて解説が繰り広げられた。
データ活用の基盤に求めたのは「コントローラブルであること」
セブン-イレブンがデータの利活用を推進するために構築したのが、データ活用デジタル基盤「セブンセントラル」だ。
店舗からのPOSデータ、汎用的に使う資料や収集したデータなどを構造化し、セブンセントラルに送ると、システムが1分で処理してBIツール、アプリ、タブレットなどで利活用できるようになる。これを可能にしているのが、Google Cloudの高性能で堅牢な基盤だという。具体的なサービスとしては、「Big Query」「Spanner」「Cloud Storage」などが使われている。
ここでの考え方として西村氏は、「事業会社が自分たちでコントロールできる(=コントローラブルである)ことが重要」だと強調する。ベンダーロックインになっていたり、自分たちの思想とずれたシステムであったりすると、せっかく良いデータがあっても、それを柔軟かつ自由に使えなくなってしまう。そうした事態を回避するために、セブンセントラルは、セブン-イレブンの意志が直接反映される基盤になっているのだという。
セブンセントラルの特徴として、西村氏は、リアルタイムデータを活用した取り組み、実現したい要件に耐え得る高い機能性、セブン-イレブン主導による新しい開発スタイルの3つを挙げる。
特に、リアルタイムデータを活用した取り組みでは、セブン-イレブンの商品を最短30分で届けるサービス「7NOW」という新しい買い物体験の創出が可能になった。また、データから顧客のニーズを分析し、それに基づいた品揃えと店舗づくりをしたり、地域社会に貢献する生活インフラ機能の強化として災害対策システム「セブンVIEW」を展開したりと、リアルタイムデータの利活用がかたちになっている。