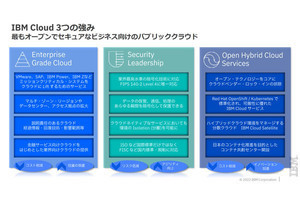旭化成は12月13日、同社のDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略と、DXの取り組みの進捗を紹介する記者説明会を開催した。
同社は、2016年から段階的にDXに着手してきた。2021年4月には全社横断のDX推進組織「デジタル共創本部」を設立。2022年4月よりスタートした「中期経営計画 2024~Be a Trailblazer~」では、経営基盤強化に向けて4つの重要テーマの1つとしてDXに取り組む。
500超のDXテーマに取り組み、2024年度までに増益貢献100億円
旭化成は、2022年度から2023年度を「デジタル創造期」と位置づけ、デジタル技術を活用した無形資産の価値化、新たなビジネスモデルや新事業の創造を進める。2024年度からは、全社員がデジタル技術を当たり前のように活用するマインドセットで働く「デジタルノーマル期」に移行する計画だ。
2024年度の目標としては「DX-Challenge 10-10-100」を設定し、デジタルプロフェッショナル人材を2021年度比で10倍、グループ全体のデジタルデータ活用量を同比10倍、DX重点テーマでの増益貢献として100億円を目指す。
旭化成 取締役 兼 専務執行役員 デジタル共創本部長の久世和資氏は、「3つの目標に向けた取り組みは順調に推移している。増益貢献は2022年度から2024年度の3年累計での既存事業の強化、事業変革、新規事業、経営基盤強化による合計額となるが、前倒しでの達成を目指す」と説明した。
旭化成では、従来から現場が自立的に取り組むDXテーマが400以上あった。現在では、全社的に取り組む「全社戦略テーマ」、代表取締役社長の工藤幸四郎氏が進捗・成果を管理する「CEOマイルストーンテーマ」、各事業部とデジタル共創本部が共同で取り組む「共創テーマ」が加わり、DXテーマは500超に上る。
デジタル創造期では、データマネジメント基盤「DEEP」(Data Exploration and Exchange Pipeline)をベースに、「デジタル基盤強化」「経営の高度化」「ビジネス変革」の3つの柱でDXを推進していく。
MIやデータ分析を活用できるデジタルプロ人材を育成
デジタル基盤強化では人材育成に力を入れる。旭化成は全社員(約4万人)のデジタルスキルやリテラシーを高度化し、デジタル活用人材に育成すべく、「DXオープンバッジ」という人材育成プログラムを2021年から開始している。
製造現場の社員向けには、「デジタルプロフェッショナル人材(デジタルプロ人材)」の育成を推進している。デジタルプロ人材の育成はリスキリングではなく、現場の業務知識、経験にデジタルスキルを掛け合わせることを目的とする。
2019年からは化学・材料研究者を対象にしたマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の中級・上級人材育成や、生産製造の技術者にデータ分析教育を実施するパワーユーザー育成、ITフィールド/デジタルイノベーション領域における高度専門職の後進育成を進める。
データ分析のニーズは製造現場に留まらず、営業、マーケティング、事業企画、品質保証、知財、購買などの他部署からもデータ分析人材育成プログラムに参加しており、2022年度は参加者の約20%が非製造系の職種だったという。
2022年度からはMI中級・上級人材やパワーユーザー育成に対応したレベル4、5のDXオープンバッジプログラムを開始しており、旭化成は2500人のデジタルプロ人材を育成する目標だ。
久世氏は、「MIを活用しやすくなるデジタルプラットフォーム整備やコーチング、メンタリングなどのサポートのほか、複数テーマの解決や人材育成・教育ができる『MI上級人材』が核となったコミュニティ活動などにより、社内でのMI活用が加速している」と明かした。
パワーユーザー育成では、データ分析をデータサイエンティストがサポートするほか、工場長などの現場を熟知する定年退職者を再雇用し、「原理原則アドバイザー」としてプログラムに参加してもらっている。
旭化成 代表取締役社長の工藤幸四郎氏は、「人材はDXにおいても最も重要な要素と認識している。当社ではすでに『終身成長』を目指した人事施策や高度専門職制度の採用などを進めているが、DX人材を育成・獲得し、人材の幅を広げるために、現在、コアの人事制度改革を進めている」と述べた。
CFP算定システムやスマートラボで製造・開発を高度化
経営の高度化に向けては、社内外のデータを集約、可視化、分析できる経営ダッシュボードの全社導入を進めている。
併せて、サステナビリティ経営を実現するために、2022年4月には最終製品別のCFP(Carbon Footprint of Products)算定システムを開発し、機能材料事業部で4月から本格的に運用を開始した。同システムでは、工場など自社活動からのCFP(Scope1、2)に加え、購入原料などに含まれる自社外のCFP(Scope3)に関連するデータを管理・分析することができる。現在は、全社標準のCFP算定システムを開発中だ。
将来の事業優位性に繋がるR&D(研究開発)の変革では、MIを活用して新領域の探索と開発期間の短縮、開発効率の向上に取り組む。
R&DのDX事例として、MIとハイスループット実験装置を組み合わせたスマートラボの取り組みが紹介された。スマートラボによって、MIが提案する実験設計に基づいて、人が介さない自動実験が可能だという。MIによる開発事例としては、樹脂コンパウンド、触媒、合成ゴム、ウイルス除去フィルター、DFR(ドライフィルムレジスト)があり、将来的にはスマートラボで開発速度を20倍以上に高める目標だという。
旭化成では製造現場の最適化、保守保全の高度化を目指してスマートファクトリー化も進める。プラントではデジタルツインを活用しており、現場の360画像と3Dモデルで設備の構造などを遠方地から確認することができる。また、装置の図面やマニュアル、装置内を流れる液体の種類、温度などをスマホでも確認可能だ。
日本や世界を巻き込んだ連携でDXを進展
ビジネス変革では、中期経営計画で示した次の成長を牽引する10の事業「GG10」(Growth Gears 10)の成長に寄与する領域でDXを進め、新たなビジネスモデルや新規事業の創造を目指す方針だ。
水素関連事業では大規模アルカリ水電解システムにデジタルツインを活用し、自動車内装材の事業では自動車領域の売上データを集約する基盤を構築し、消費者の購買特性や事業者業界の市場動向などのマーケティング活動に自社製品のデータを活用している。
旭化成では、デザイン思考やアジャイル開発のアプローチを用いたイノベーション創出支援プログラム「Garage」を展開している。同プログラムからもテリボン(骨粗鬆症治療剤)投与の継続率向上のための患者向けソリューションや、製造現場関係者向けの「トラブル発生時コミュケーションアプリ」の開発など、新たなビジネスアイデアが生まれている。
このほか、プラスチック資源循環の領域では業界を超えて61社と共創活動「BLUE Plastics」を推進し、ブロックチェーン技術を活用したデジタルプラットフォーム開発を進める。
説明会の最後に工藤氏は、「DXが進むことにより、ビジネスを強制的に変革せざるを得ないステージに到達していると考える。また、『連携の域を広げる』がキーワードになるだろう。DXが進展することにより、その活動は個社に留まらず、日本全体あるいは世界を巻き込んでいく。当社のDXは5-10年後、会社の枠に留まらずにグローバル、ユニバーサルな活動に発展する可能性もある。さらにもう一歩、DXを強く進めていきたい」と語った。