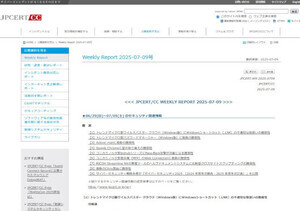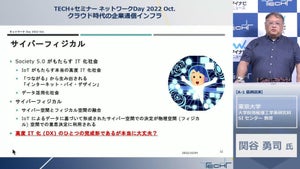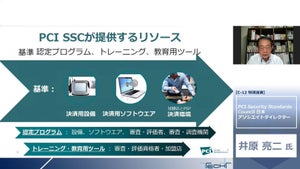2022年に「全社DX推進宣言」を出したサッポロビール。2018年から始まったDXの歩みはどのように進んできたのか。そしてこれからどのようにDX推進人材を育てていくのだろうか。
10月25日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+フォーラム 業務効率改善 Day 2022 Oct. 自社にいま必要な『業務効率化』を見極める」に、サッポロビール 改革推進部 リーダーの林佐和子氏が登壇。「サッポロビールの業務改革2.0~全社員DX人財化に向けて~」※と題して、講演を行った。
※サッポロビールとして業務改革1.0、2.0の位置付けを正式には行っていないが、本講演では同社の業務改革フェーズを分かりやすいように各フェーズごとに業務改革1.0、業務改革2.0と名付けている。
【あわせて読みたい】「自社にいま必要な『業務効率化』を見極める」その他のレポートはこちら
2018年に始まったサッポロビールのDX
サッポロビールが所属するサッポログループは、「世界に広がる『酒』『食』『飲』で個性かがやくブランドカンパニーを目指します」をビジョンに掲げ、酒類、食品飲料、不動産の3分野をコアとして事業展開している。
同社のDXの歩みは2018年に始まった。BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)をDX実現に不可欠な活動と考え、まずBPR推進基盤の確立に着手。あわせてRPA・AI・OCRといったデジタルツールの活用をスタートさせた。2020年にはBPR基盤も整い、業務の自動化をさらに加速。2021年からはAIなど最新技術の活用も進めている。
林氏はこの2018年から2021年までのフェーズをこの講演内では「サッポロビールの業務改革1.0」とすると説明し、初めに取り組んだBPR推進基盤の構築事例を紹介した。
最初のステップは「廃止」だ。既存業務に関して、それぞれの必要性を判断するために業務フローの可視化を実行したという。担当者と会話を重ね、業務プロセスの精査を進めることで、まず必要性のない仕事を廃止していった。
次のステップは「簡素化・集約化・標準化」だ。必要性があると判断した業務プロセスに対して、その仕事を社員が行う必要があるのかという確認を進めた。そして最終的に、再配置/外部化、もしくはデジタル化を視野に入れ、システム化・RPA導入などの「自動化」の検討を行った。
「RPAは即効性がある有効な手段の1つだと考えています。しかし、初めから自動化ありきでBPRを進めないことが重要です」(林氏)
段階を踏んだRPA構築で得られた効果
では、検討を経た上で、どのようにRPA構築を進めていったのか。
2018年の開始当初は、外部ベンダーやコンサルタントのサポート体制をCoE(センター・オブ・エクセレンス)部門内に受け入れるかたちでRPA構築が進められた。そして2019年に、CoE部門内での教育がスタートする。これによってRPAを構築できる人員を増やし、多くのRPAを作成できる体制が整った。この期間を経て、社員のRPA技術も向上し、2020年にはRPA構築の完全内製化を実現。また、社内メンバーが講師として教育を行えるようになったことで、2022年末、約200人分の仕事削減を実現する見込みだという。
実際にRPAを利用し業務の自動化を行った事例として、RPAとAI-OCRを組み合わせた物流部門での取り組みが紹介された。具体的には、納品後に持ち帰る受領証と出荷データとを照合し、不備なく回収できていることを確認する作業を自動化したものだ。
従来は、出荷データをシステムから出力・印刷し、受領証と照合、そして蛍光ペンでチェックする作業を人手で行っていた。一連の作業には年間9,600時間がかかっており、約5.7名の工数が割かれていたそうだ。だがRPA化により年間5,500時間の作業時間を削減、現在は同じ業務が年間4,100時間で行えている。
「RPAを設計する際、案件に関わる全ての担当者間で相互理解を深めることが重要です。現場側担当者からは『RPAが正しいのか不安』『これまでのやり方の方が慣れていてやりやすい』という声をよく聞きますが、その不安を事前に解消しておくことで自動化の効果が出やすくなります」(林氏)