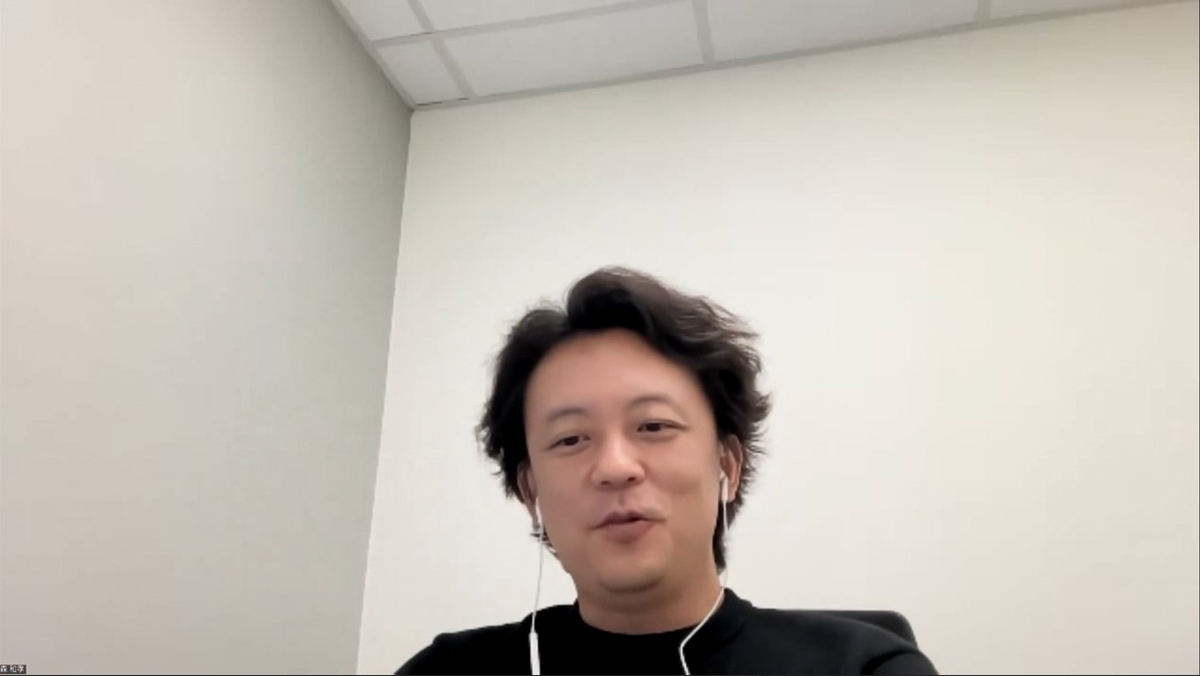暗号資産やNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)など、ブロックチェーンの特徴を活用した分散型のWebサービス、いわゆる「Web3」について耳にしたことがある読者も多いだろう。
Web2以前の従来のWebサービスは多くの場合、国単位で展開されてきた。しかし昨今は世界中でWeb3サービスが多数開発されており、NFTやトークンは最初から国境を越えて取引される前提で開発が進められている。そうした中で注目されている土地がシンガポールだ。
2020年ごろに若い優秀な企業家がシンガポールへ進出し、2021年からは大手企業もシンガポールで事業の展開を始めている。なぜ、多くの国内ビジネスがシンガポールに進出するのだろうか。今後のWeb3ハブを狙う各国の争いはどのように変化するだろうか。日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が開催した勉強会の中から、その答えを探ってみたい。
現在の日本でWeb3サービスを開発する場合、トークン発行全般について交換業ライセンスが必要となる。また、法人が保有するトークンは期末にみなし課税される。その他、DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)など新しい分野の規制が不明確である点なども日本の課題となっているようだ。このような背景から、拠点を国外に求める企業が増えているという。
一方、シンガポールは2017年にMAS(シンガポール金融管理局)がICO(新規暗号資産公開)に関するガイドラインを策定した。この中で、STO(有価証券の性質を持つトークン)に該当しない資金調達はトークンで行っても良いとする方針が定められたため、多くのICOが行われたようだ。その後、2018年にはSGX(シンガポール証券取引所)が上場企業によるICOガイドラインを策定した。
このころから、暗号資産を利用したマネーロンダリングや犯罪行為が問題視されるようになり、2020年にPayment Service Actを施行している。2022年にはDPT(Digital Payment Token)サービスに関する広告を規制した。なお、NFTに関しては規制する方針がないことを国会で発表している。
シンガポールはこれまで、決済システム法と両替・送金業法の2法によって決済サービスに対し規制をかけていた。しかし、暗号資産ビジネスをはじめとするフィンテックの急激な進展によって、これら2法での対応が不十分となってきたため、既存の2法と置き換わるように2019年に新法を制定した。
新法では、両替サービスや決済口座発行サービス、電子マネー発行サービスなどに加えて、デジタル決済トークンサービスを提供する際もライセンスが必要だと定めている。同法では、「少なくとも公衆の一部に受け入れられているものか、またはそうすることを意図しているもの」を暗号資産として規制の対象としている。規制当局はこれ以上の方針を示していないため、非常に解釈の余地が広いのだという。
そのような中で、シンガポールではフィンテックに関するサンドボックスの活用が積極的だ。サンドボックスとは、新たな技術やビジネスの実用化を目指す際、ライセンスや現行規制との関係によって実現が困難な場合に、事業者の申請に基づいて一定の範囲で免除を受けられる制度だ。2022年にはサンドボックスプラスという制度を開始し、参加資格の拡大や手続きの迅速化などを行っている。
順調に思えたシンガポールでの暗号資産ビジネス開発ではあるが、2022年5月7日に発生した「テラショック」以降は少し風向きが変わったようだ。法定通貨であるドルとの連動性を持つことが特徴とされていたステーブルコインのテラ(Terra)とルナ(LUNA)の価格が大暴落したため、一躍話題となった。本件をきっかけにシンガポール内でも規制対応を強める動きが出ている。
例えば、Proposed Regulatory Measures for DPT Servicesが2023年の3月から4月に改正される見込みだ。この中では、認定投資家となるための条件が見直される上、それ以外の消費者の取引が厳格化される案が示されている。加えて、認定投資家も年間の取引額に上限が設けられるのではないかと考えられている。
ステーブルコインの発行者と仲介者を規制対象とするProposed Regulatory Approach for Stablecoin Related Activitiesも新たに規制が強まるとみられる。これにより、単一通貨にペッグ(連動)されたステーブルコイン(SCS)をDPTとは異なる「ステーブルコイン発行サービス」として新たなライセンスが作られるようだ。SCSは米ドルや日本円などG10通貨とペッグするもののみ発行可能となる。
テラショック以降はこうした変化に加えて、賭博法の規制なども強まっている。勉強会の講師を務めたOne Asia Lawyersの森和孝氏によると「シンガポールは以前のようなクリプトヘイブンで何でもできる雰囲気は薄れてきた。日本との時差が小さく英語が通じるので、いくつかある国の中の選択肢の一つになっている」と述べていた。
さらに「シンガポールは依然としてWeb3ビジネスを始めるために良い部分もあるが、シンガポールがベストチョイスなのではなく、ケースバイケースになってきている」とも語っていた。