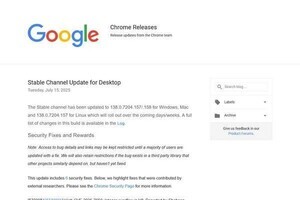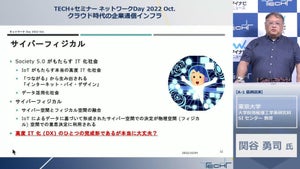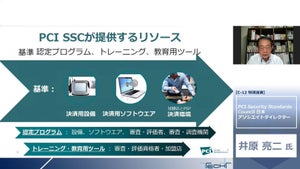長引くコロナ禍の中、著しい事業成長を見せているのがアイリスオーヤマである。多くの企業が苦しんだこの2年半で売上を1.5倍に伸ばし、今後もさらなる成長が見込まれているという。
なぜアイリスオーヤマはこれほどまでに成長を続けられるのか。その背景には、同社が実践するユーザーイン戦略がある。
9月29日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+フォーラム for Executive 2022 変革を担う経営者の条件」にアイリスオーヤマ 代表取締役 会長の大山健太郎氏が登壇。同社の戦略について、一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻 教授の楠木建氏と対談を行った。
マーケットインのさらに先を行くユーザーイン戦略
楠木氏は冒頭、「以前からアイリスオーヤマの戦略が現代日本における最高傑作だと思っていた」と称賛。特にコロナ禍からの2年半で同社の地力が見えてきた、と評価した。
事実、アイリスオーヤマはコロナ禍以降、大きく売上を伸ばしている。2019年に5000億円だった売上は2021年には8000億円。今後、1兆円も見えているという。
こうしたアイリスオーヤマの成功の裏には、どのような戦略があるのだろうか。
大山氏が挙げるキーワードが「ユーザーイン」である。これは、マーケットインのさらにその先、ユーザーすら気が付いていないニーズを捉えて市場を創造していく考え方だ。アイリスオーヤマの躍進の原動力にもなった戦略だが、同社も最初からユーザーインを実践できていたわけではなかったという。
「私は19歳で家業を継ぎ、そこからしばらくはプロダクトアウトで商品開発を行っていました。しかし、オイルショックで過剰生産に陥り、需要が減退したことで倒産寸前になってしまったのです」(大山氏)
そこで大山氏はプロダクトアウトを諦め、マーケットインの考え方に切り替えた。だが、当時のアイリスオーヤマがマーケットインで大企業と戦うには企業体力が不足していた。
そこで同社が見いだした戦略こそ、ユーザーインだったのだ。
ただし、「ユーザーインという言葉は後付け」だと大山氏は言う。戦略から入ったわけではなく、消費者自身も気が付いていないニーズを捉えて商品開発を行った結果、それがユーザーインという戦略になったのだ。
大山氏は事もなげに話すが、ユーザーインを実践するのはそう簡単なことではないと楠木氏は話す。
「私が大山さんからユーザーインという戦略について初めて伺ったのは26~27年前のことでしたが、その時はそれがどういうものなのか、よく分かりませんでした。ユーザーインはそれくらい奥深い考え方です。“ニーズを捉える”とは言うけれど、それは市場のニーズではなく特定のユーザーのニーズ。この点について、多くの人が混同しています」(楠木氏)
大ヒットした収納クリアケースはいかにして生み出されたか
市場ではなく、特定のユーザーのニーズを捉える――このユーザーインの考え方を象徴する商品がある。
アイリスオーヤマが生み出した大ヒット商品、収納用のクリアケースだ。
今では当たり前になったクリアケースだが、実はアイリスオーヤマが1989年に開発するまでは存在していなかった。
商品開発のきっかけとなったのは、大山氏自身の体験だ。
「ある寒い朝、釣りに行くためにセーターを探したのですが、見つからずに困りました。収納ケースを開けてもなかなか見つからないのです。その時、いちいち収納ケースを開けなくても外から中が見えれば良いのにと思いました」(大山氏)
この体験を基に、大山氏は半透明で外から衣類が確認できる収納ケースの開発に着手した。前例のない商品に対して、当初は否定的な声も多かったという。
しかし、実際に販売してみると、クリアケースは飛ぶように売れた。それまでになかったクリアケース市場が生まれ、海外にも展開。アイリスオーヤマは一気にグローバルメーカーへと飛躍していった。
市場が否定的な反応を示しても、その先にいる個別の生活者のニーズを捉え、商品を開発する。これこそがまさにユーザーインの考え方なのだ。