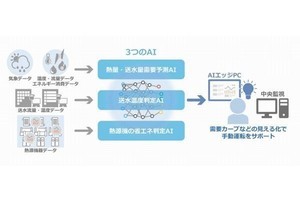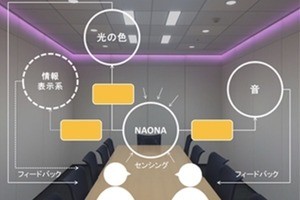日建設計とホロラボは11月10日、仮想空間と現実空間が融合するワークプレイス「Cyber-Physical Workplace」の実現に向けて、MR(Mixed Reality:複合現実感)アプリケーションのプロトタイプを開発したと発表した。
今回、日建設計の東京本社で同アプリを体験する機会を得たので、それをもとに「Cyber-Physical Workplace」の正体を明らかにしてみたい。
テレワーカーの孤独感をテクノロジーで解決する新たなワークプレイスとは?
「Cyber-Physical Workplace」とは、BIMデータを基に構築されたサイバー空間(仮想空間)と、IoTを活用したフィジカル空間(現実空間)のセンサー情報を組み合わせ、異なる空間をMR技術でつなぐ事により、高度なコミュニケーションと労働生産性向上を目指すワークプレイスを指す。BIMとは、コンピュータ上に作成した主に3次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、建築物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステムだ。
ここ数年の新型コロナウイルスのまん延を背景に、在宅勤務を中心としたテレワークが急速に普及し、デジタルコミュニケーションの心理的ハードルやコストが下がっている。その一方で、生じている「テレワーカーの孤独感」や「偶発的なコミュニケーションの低下」をテクノロジーで解決することが「Cyber-Physical Workplace」の肝だ。日建設計は、設計事務所として「時代に必要とされるワークプレイス」のデザインを手掛けており、その経験とノウハウを生かしながら新しい発想で、現実のオフィスと仮想のオフィスが等価に融合していくワークプレイスを目指していきたいという。
今回、「Cyber-Physical Workplace」の実現に向けた第1段階として、MRアプリケーションのプロトタイプが開発された。同アプリは、テレワークであるか、現実のオフィスに出社しているかを問わず、ワークプレイスの偶発的な出会いを創出し、MR技術により非言語的なコミュニケーションを強化し、テレワーカーの孤独感を軽減や偶発的なコミュニケーションを誘発するもの。
テレワーカーはVRデバイスを通じてオフィスの仮想空間に没入し、オフィス内に実在するオフィスワーカーのアバターと交流できると同時に、オフィスワーカーはARデバイスを通じてオフィスの現実空間に投影された在宅ワーカーのアバターと触れ合うことができる仕組みになっている。
実際にリアルとバーチャルが交わるワークプレイスを体験!
VRゴーグルをつけて、いざバーチャルとリアルが交じり合うオフィス空間へ!
今回は「会社に出社していることを想定したスペース」と「在宅勤務でテレワークをしている想定のスペース」を作っていただき、オフィスワーカーとテレワーカーの両方の視点を体験させていただいた。
最初はオフィスワーカー側の視点を体験した。始めてすぐに感じたのは、通常のVR体験と違って完全な映像空間ではなく、透過型ディスプレイを通して現実世界にバーチャルのアバターが登場する技術であるため、VRゴーグル特有の画面酔いが非常に少ないということだ。またスペース内を歩き回っても、ゴーグルを通して見えている世界と現実の世界のモノの配置などに誤差がないので、比較的安全に歩き回ることができる。
同じ空間にいるオフィスワーカー役の方のアバターと交流したり、隣のスペースからテレワーカー役として参加している方と交流したり、まるで現実世界にアバターだけが飛び出してきたかのような世界観になっている。
続いて体験したテレワーカーの視点は、目全体を覆うVRデバイスを装着して行う、バーチャルで再現されたオフィスの映像だった。背景や家具などは、前述したBIMを使って再現されており、IoT(人感センサー)を活用した背景アバターも再現されている。それによって、オフィスにいる時と変わらない環境で作業できるうえ、オフィスの賑わいなどを感じることができ、孤独感を和らげる効果がありそうだ。
今回の実証実験で使用されているアプリケーションは、基本的に偶発的なコミュニケーションの低下を食い止めることを目的として開発されたものなので、活用のシチュエーションはミーティングや雑談などを想定しており、アバターは表情や個性を持たせていないという。一方、手のモーションにはかなりこだわっており、指までハンドトラッキングが効いていて、握手やハイタッチはもちろん、じゃんけんなどもアバター同士で行うことができた。
しかし、実証実験を行う中で「コミュニケーションをより図るためには表情まで見えた方が良いのではないか」という意見も出ているそうで、その点も検討していくという。
両社は今後、コンテンツ共有やプレゼン機能といったアプリケーションのビジネス向け機能およびノンバーバルコミュニケーション機能を強化するとともに、顧客にも体験してもらい、意見や感想などを反映させていきたいとのことだ。また、このような技術のスマートビルやメタバースへの応用、さらなる技術開発を行い、ワークプレイスの提案力強化とコンサルティングビジネスへつなげていく方針だという。