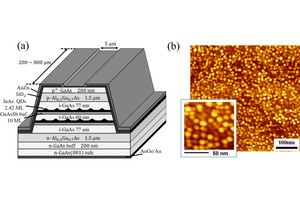東京大学(東大)と山形大学は11月9日、一辺当たり4つ、計64個の鉛原子からなる立方体の「純青色ペロブスカイト量子ドット(QD4)」を高精度かつ無欠陥で合成し、蛍光発光波長463nm、半値幅15nm、蛍光量子効率97%という、発色の国際規格「BT.2020色度」が理想とする純粋な青色(0.131,0.046)に肉薄する発光(0.135,0.052)を実現したと発表した。
同成果は、東大大学院 理学系研究科 化学専攻の中村栄一特別教授(東大名誉教授兼任)、同・シャン・ルイ特任准教授、同・中室貴幸特任准教授、山形大 学術研究院の城戸淳二教授、同・千葉貴之助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する機関学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。
有機EL(OLED)は、自身が発光することから動画視認性には優れるが、発光波長の幅が広いために色純度が低いという課題があったほか、青色については、発光効率も低いという課題も抱えており、有機発光材料を高輝度の量子ドット(QD)に進化させたQD-LEDが、高い色純度と高い発光効率を同時に実現できる次世代ディスプレイ技術して期待されている。
QDは、半導体ナノ粒子を数nmスケールまで小型化したもので、結晶構造は同じままでありながら電子状態が変化し、電子を持つ状態と持たない状態の2つを持ち、特徴的な発光を示すようになるという。
ただし、高輝度で純粋な青色を発色させるためには、ナノ粒子を完全に同じサイズと構造を持たせて製造することが必須とされており、理想的な青色の基準はBT.2020色域規格である467nmにできる限り近く、発光波長幅15nm、蛍光量子収率100%とされている。
これまでのQD調製法はサブマイクロメートルサイズのコロイド微粒子の標準法を基盤にして、高温からの急速冷却という、物理的条件を変化させるトップダウン的アプローチで合成されてきた。しかし同手法では、サイズおよび構造を揃えることが困難であり、発光輝度および色の純粋さの両方を満たす性能の実現はできなかったという(量子収率は50%以下)。
そこで研究チームは今回、調製法の基本発想を転換し、原子と分子から組み上げる「自己組織化による精密合成」の概念に基づくボトムアップ手法でQDの調製を試みることにしたという。