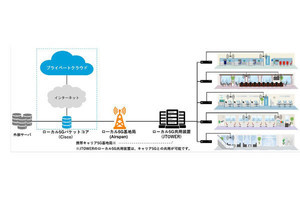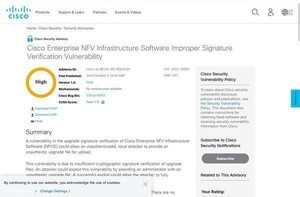シスコシステムズ(シスコ)は10月19日、2023年度の事業戦略を発表した。発表会に登壇した代表執行役員社長の中川いち朗氏は、「2023年度はクラウド時代のDX(デジタルトランスフォーメーション)プラットフォームを強化し、『やわらかいインフラストラクチャ』を実現していく」と説明した。はたして、「やわらかいインフラ」とはどのようなものなのだろうか。
やわらかいインフラとは?
同氏が定義する「やわらかいインフラストラクチャ」とは、仕事をする場所、仕事に使うデバイス、データの保管場所などに、自由度を持たせるインフラストラクチャのことだ。このやわらかいインフラでは、アプリケーション開発のサイクルを年単位から週単位へと短縮し、セキュリティの考え方も「ファイヤーウォールの中は安心」から「社内であっても信用しない」へと強化する。シスコが目指すのは、柔軟性のあるインフラだ。
近年の働き方改革や新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事をする場所はオフィス中心からリモートを組み合わせたハイブリットが主流になり、仕事に使うデバイスは会社支給のPCからモバイルデバイスやBYODなど、利用する端末の多様化が進んでいる。
一方で、日本のデジタル競争力は先進国最低レベルだ。その足かせとなっているのが旧来型のITインフラ。シスコによると、顧客の大半は旧来型のITインフラを構築しており、「新たな開発環境の提供には数週間から数カ月かかる」、「クラウド基盤はすぐに提供できるが、ネットワークの設定は手動なので時間がかかる」といった悩みを抱えているという。
「デジタル競争力が低いのは、日本企業が何もしていないからではない。クラウドの活用などさまざまな努力をしているが、世界のスピードに追いついていないからだ。新しい仕組みを作っても、旧来型の仕組みも同時に動かすという根強い日本の企業文化が、IT人材の減少ややスキルの低下を招いている」と、シスコ 副社長 カスタマーエクスペリエンス担当の望月敬介氏は日本の現状を分析してみせた。
DXプラットフォームを強化するシスコの新戦略
シスコは、10年間同じ課題を持ち続ける旧来型のシステムをもみほぐしていく。具体的には、旧来型のシステムにおいて、BYODやIoTデバイス、5G、エッジなどあらゆる接続に対応し、SASE(Secure Access Service Edge)やゼロトラストといったセキュリティの概念を取り込み、DXを加速するインフラへと最適化する。さらに、運用を自動化することで省力化やオペレーションミスの低減につなげ、インフラ全体の可視化により、ビジネス変革のスピードに対応させる。
「やわらかいインフラを実現するためのテクノロジーとサービスの準備は自社内でできており、それぞれのサービスは連携できる状態だ。まだまだ発展途上の領域もあるが、クラウド時代の顧客にコミットメントしていく準備はできている」(望月氏)
やわらかいインフラの実現による効果は数字に出ている。米国シスコの導入事例によると、新たな取り組みに充てられる時間は203%増加し、ネットワークの運用費用は36%削減したという。セキュリティの強化やITの効率性の向上などで定性的な効果も確認されたという。
さらに、同社はパートナー企業との共創にも力を入れる。10月13日、オフィスの固定電話にかかってきた電話を自宅などで受け取れるサービスの提供をNTT東日本と共同で開始した。
シスコはパートナーデリバリーモデルとして、今後さらにパートナー企業との共創サービスを展開していく考えだ。「約800人体制のカスタマーサポートを構築しているが、われわれだけですべての顧客のDXを支援するのは難しい。パートナー企業との共創は不可欠だ」(望月氏)
中川氏は、「10年後の日本がDX先進国になるためには、今が過渡期になる必要がある。顧客とパートナー企業の成功こそがシスコの成功だ。信頼される製品ベンダーから、常に寄り添う戦略的ビジネスパートナーへと進化していく」と熱弁をふるい、発表会を締めくくった。