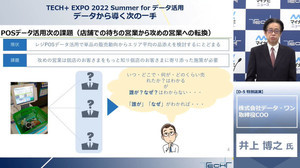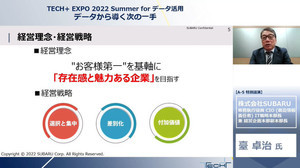21世紀が始まって20年以上が経過し、平成を超え、令和を迎えた現代において、企業はいつまで昭和の感覚を引きずった人事を続けるのか。
10年後どころか、3年後すら見通せないようなVUCA時代において、何よりもまず変革するべきは人事部門である。なぜなら、人事こそが組織全体の行く末を左右する重要な存在だからだ。
価値観が多様化する中で、人事部門のあるべき姿とはどのようなものなのか。6月28日に開催された「TECH+フォーラムセミナー 人事テック Day 2022 Jun. 人材の価値を最大限に引き出すために」に、people first 代表取締役で元LIXILグループ 執行役副社長の八木洋介氏が登壇。「人で勝つ ~人起点のデジタル活用~」と題した講演を行った。
管理型マネジメントからオーセンティックマネジメントへ
年功序列、終身雇用――かつて日本企業は独自の“日本的人事”により、成功を収めてきた。しかし、それはもう過去の話である。
今、世界は大きなパラダイムシフトを迎えている。人口が70億人を超え、気候変動をはじめとするさまざまな課題が生まれている。
「だからこそ、いろいろなリーダーが地球の問題を解決する方向に進まねばならないのです」(八木氏)
こうした状況にある現代を、八木氏は「価値観の時代」と呼ぶ。
価値観の時代において企業がグローバルで勝ち残っていくためには、これまでのような「管理」する経営から「任せる」経営へとチェンジすることが重要になるという。
それを象徴するのが、コロナ禍によるリモートワークの定着だ。個々が自由な場所で働くリモートワークでは、これまでのような管理型のマネジメントが通用しない。図らずも、コロナ禍は経営や人事に大きな影響を与える出来事となった。
では、管理型マネジメントメンバーシップに代わって、マネジメントを左右するのは何か。
八木氏が挙げるキーワードが「オーセンティックリーダーシップ」―つまり、“自分らしいリーダーシップ”だ。
「価値観の時代では、オーセンティックリーダーシップにより、自立した個人をエンゲージメントでまとめることが大切です。また、組織内でコラボレーションを生み出すには、情報を共有する必要があり、現場で起きる想定外のリスクを乗り越えるために心理的安全性が重要となります」(八木氏)
しかし、八木氏が話す「あるべき姿」は、そう簡単に実現できるものではない。なぜなら、多くの日本企業はまだまだ多くの課題を抱えているからだ。
人事こそ明確なビジョンを
最大の課題は、「人事におけるビジョンを持たないこと」だと八木氏は指摘する。昭和の時代はそれでも良かった。年功序列や終身雇用の安定感を背景に、全員で1つの方向を見据えて愚直に進めば勝負ができたからだ。
しかし、経済力が高まり、価値観が多様化した今は状況が異なる。多様な人材をまとめるためには、人事にも明確なビジョンが必要なのだ。
「自社の人事について語れる社員は多くありません。そうした状況を、人事は反省しないといけないのです」(八木氏)
ビジョンが曖昧ということは、他社との差別化もできていないということに他ならない。
職場内のバランスを保つための「調整」や、目標がないままの「ベストプラクティス信仰」、個人よりも全体を優先することによる「厳しさの欠如」――日本的人事が抱える課題を、八木氏は次々に炙り出し、「人事のための人事をやっているように見える」と厳しく指摘する。
「一言で言うと、日本の人事には戦略性が欠如しているのです」(八木氏)