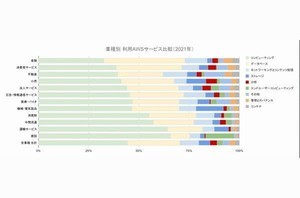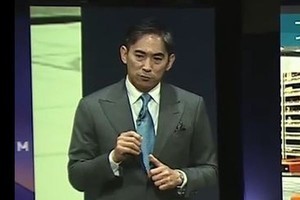Amazon Web Services(AWS)は9月15日、静岡県浜松市と多様性があり、包摂的、持続可能なデジタル・スマートシティの実現に向けて、スタートアップや地域のクラウドエンジニア・コミュニティの発展に連携して取り組んでいくことを発表した。
連携の名称は「デジタル・スマートシティのエコシステム形成に関する連携協定」。目的は、「人口減少・少子高齢化時代において、 市民の幸福感(Well-being)があふれ、 イノベーションが継続的に創発される活力ある地域を目指し官民共創で取り組むデジタル・スマートシティのエコシステム形成に両者で連携して取り組むこと」だ。
締結式において、浜松市長の鈴木康友氏は、「デジタルを活用した都市を作っていくには、官民連携で進めていく必要がある。Amazon Web Servicesのクラウドサービスは定評があり、今後デジタル・スマートシティ構築に向けて、頼りになるパートナーといえる。デジタルを活用して、ウェルビーイングの高い、持続性のある都市を構築していきたい」と、連携に対する意気込みを語った。
AWSジャパン 執行役員 パブリックセクター 統括本部長の宇佐見潮氏も、「浜松市と当社ははインクルーシブで持続性可能なシティを構築していくために連携する。日本政府は自治体とクラウドを通じて、デジタルによって地域経済を活性化させることを目指している。われわれは続可能な真のデジタル・スマートシティに貢献していく」と、デジタル・スマートシティ実現に向けた想いを語った。
デジタル・スマートシティのエコシステム形成に向け活動
浜松市は2019年にデジタルファースト宣言を行い、オープンデータやデジタル技術を生かして地域のコミュニティや産業の活性化を目指すデジタル・スマートシティの実現に向けた取り組みを進めている。
今回の連携は、デジタル実装を通じた地方活性化を推進し、スタートアップエコシステムの確立など、日本政府のデジタル田園都市国家構想と方向性を同じくするものとなる。
両者は、 デジタル・スマートシティのエコシステム形成に向けて、 スタートアップの支援、 シビックテックコミュニティの活性化、 クラウド活用や情報セキュリティ対策に関する人材育成などに協力して取り組んでいく。連携の内容は以下の通りだ。
- スタートアップの支援に関すること
- シビックテックコミュニティの活性化に関すること
- 人材育成に関すること
- インターネットやクラウド活用におけるセキュリティ対策に関すること
- デジタル・スマートシティやスタートアップの推進に係る情報発信に関すること
AWSの支援を通じてスタートアップが市民サービスを開発
今回の連携により、浜松市を拠点に活動するスタートアップは、AWSのスタートアップ支援プログラムを通じて、技術支援・トレーニング、ビジネスメンターシップ、コミュニティ、Go-To-Market支援、AWS無料利用クレジットなどに迅速にアクセスし、ビジネスの立ち上げ・構築を実現できる。
具体的には、スタートアップは浜松市がデータの流通・連携を促進するために導入する都市OS(データ連携基盤)を用いた市民サービスを開発・検証・展開することが可能となる。
GreatValue、Helte、トラストアーキテクチャは、スタートアップを支援するプログラム「AWS Startups Ramp」を通じて支援を受け、浜松市のデータ連携基盤のユースケース創出の取り組みに参画している。この3社は、浜松市とAWSの連携の一環として、浜松市データ連携基盤活用モデル事例創出事業「Hamamatsu ORI-Project」への参加を通じて、地域の住民同士が手軽に助け合うことができる地域住民向けアプリに関する事業検証を行う予定としている。
また、AWSは今後、同市との共催セミナー等を通じて、同市ならびに地域のクラウドエンジニア・コミュニティと、これらの実績を踏まえたオープンガバメントデータ活用のための知見を相互に共有していく。
教科書が存在しないデジタル化を支援していく
昨年、政府は「デジタル実装を通じて地方が抱える課題を解決し、誰一人取り残されずすべての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現する」という「田園都市国家構想」を打ち出したこともあり、地方創生に力を入れる企業が増えている。
上記にデジタルとある通り、テクノロジーに対する期待は大きく、ITベンダーも積極的にさまざまな自治体と連携を始めている。AWSは今月、つくば市と研究開発型スタートアップの成長加速に向けた連携を開始したが、今回の浜松市との連携はつくば市に続くものとなる。
宇佐見氏に、AWSの地方創生に対する戦略を聞いたところ、次のような答えが返ってきた。
「現時点では、地方創生におけるデジタル化はあまりうまくいっていない。デジタル化の具体的な成果を出すには、われわれが責任を持った形で直接現場に乗り込まないとならないと考えている。クラウドはテクノロジーとしてとらえられがちだが、さまざまな変化をもたらす。例えば、クラウドによって、アプリケーションレベル、インフラレベルのサービス化が起こる。ただし、そこには教科書が存在しないため、手探りでやっているのが実情だ。われわれはクラウドの導入に伴うさまざまな面で支援していく」
今回の浜松市との連携内容に、スタートアップの支援が含まれているが、2018年にスタートアップとデベロッパーのための施設「AWS Startup Loft Tokyo」を設立するなど、AWSは以前から精力的にスタートアップを支援してきた。
これまで、自治体のIT導入といえば、日本の大手ベンダーが取り仕切っているケースが多く、スタートアップが入り込む余地はなかったように思う。
しかし、「今、国がスタートアップを支援していることもあり、地方創生でITを活用する流れの中にスタートアップが入ってきている。これにより、自治体とスタートアップのシナジーが生まれている」と、宇佐見氏は語る。
そして、宇佐見氏は「テクノロジーが、地方創生の障害になってはいけない。エンジニアが気軽に質問できる聞けるコミュニティとして、AWS Startup Loft Tokyoを使ってもらいたい」と話す。
浜松市では、エンジニアに対し、「情報提供」「スキル習得の支援」「出会いの場の提供」などを行うことで、クラウドエンジニアのコミュニティを醸成していくという。AWSのエンジニアコミュニティは活発であり、そのノウハウが十分に生かされるのではないだろうか。
今後、地方創生に取り組んでいくにあたり、AWSとしての展望を聞いたところ、「iPhoneで社会変革が起きたように、クラウドによって日本の商慣習を変えていきたい。そして、結果として、市民のデジタル化を実感してもらえるような成果を生んでいきたい。地方創生においては、市民やスタートアップなど、ステークホルダーが多いため、簡単ではないが すべての人が水平な状態で求めているものを享受しあう世界をつくりたい」と宇佐見氏は語っていた。