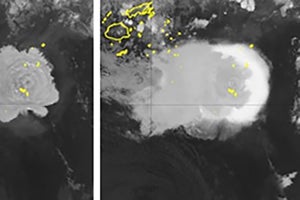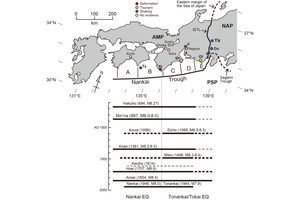海洋研究開発機構(JAMSTEC)と京都大学(京大)は9月12日、2022年1月15日に生じたフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の大規模噴火が、長年にわたって“幻の大気波動”とされてきた「ペケリス波」(研究チームが提唱した研究者にちなんでこの名称を今回提案)を引き起こしていたことを発見したと発表した。
同成果は、JAMSTEC地球環境部門環境変動予測研究センターの渡辺真吾センター長代理、同・中野満寿男研究員、米・ハワイ大学国際太平洋研究センターのケビン・ハミルトン名誉教授、京大大学院理学研究科の坂崎貴俊准教授らの研究チームによるもの。詳細は、地球やほかの惑星の大気に関連する全般を扱う学術誌「Journalofthe Atmospheric Sciences」に掲載された。
地球大気が一定の周波数で共鳴するのかどうかは、気象力学の最も基礎的な問いとされており、その1つである「ラム波」は地面と水平に音速に近い速さで遠方まで伝わる粗密波であり、1883年のクラカタウ火山の大噴火で実際に確認済みだという。
そして1937年、ペケリス博士によってラム波以外に、もう1つ地球大気の固有の共鳴振動であるペケリス波の存在が予想された。ペケリス波は、鉛直方向での位相が変わらないラム波とは異なり、下部成層圏を境に上下で位相が180度変わるという特徴がある。対流圏界面と中間圏界面の2つの温度の極小の間にエネルギーが閉じ込められるため、上部成層圏で大きな振幅を持つと考えられているが、その存在はおよそ85年ほど経った現在まで確認されていなかったという。
そうした中、2022年1月15日にフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山が大規模噴火を起こした際、ラム波に比べて数割ほど遅く伝わる大気波動が存在した可能性が、今回の研究にも参加しているJAMSTECの中野研究員らによって示唆された。
そこで研究チームは今回、気象衛星「ひまわり8号」の観測データに加え、ウェザーニューズが日本各地の約1600地点に設置した気象センサー・ネットワーク「ソラテナ」の気圧計アレイによる1分間間隔計測データを解析することで、ペケリス波の存在を確かめることにしたという。