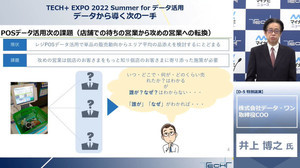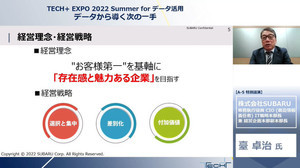コロナ禍、サプライチェーンの崩壊、超円安、気候変動――2022年現在、企業はさまざまな危機に直面している。これまでの経営戦略を押し通すだけでは、この難局を乗り切るのは困難だろう。
そこで、企業が取り組むのがデータ活用によるDXだ。データを収集し、新たなビジネスにつなげるのが理想だが、なかなかうまくいかないことも多い。では、データ活用を成功させるポイントはどこにあるのか。
7月21日に開催された「TECH+セミナー クラウド移行 Day 2022 Jul. クラウド移行でDX推進の基盤を支える」にフロンティアワン 代表取締役の鍋野敬一郎氏が登壇。データ活用によるDXを成功させるポイントについて語った。
製造業がサプライチェーンを再構築するべき理由
鍋野氏はまず、2022年現在において日本企業が直面する7つの脅威を取り上げた。
まず、言うまでもなくコロナ禍の影響である。新型コロナウイルス感染症は国内の感染が初確認されてから2年以上経ってもいまだ収束の兆しを見せず、生産の遅延やサプライチェーンの分断といった事態が発生している。
さらに、グローバルレベルでのインフレと、アジア諸国における経済成長の鈍化、気候変動も見過ごせないリスクだ。
各国の関係性にも歪みが生じている。貿易紛争だけでなく、戦争や武力紛争の影響も受けることになる。
そして、急速に進む超円安もリスクになり得る要因だ。長期的に見れば輸出面ではメリットだが、短期的には輸入に対してマイナスに働く。為替レートの急激な乱高下に耐えられるだけの企業体力が必要になってくる。
これらの危機の中で、鍋野氏が喫緊の課題と見るのが、サプライチェーンの脆弱性だ。自由貿易を前提に構築されたグローバルサプライチェーンは、コロナ禍により世界各地で寸断されており、企業には早急な見直しが求められる。
グローバルに展開する製造業がサプライチェーンを再構築する狙いは3つだ。
まず、生産拠点の役割を明確にすること。例えば、生産技術は国内のR&Dやマザー工場に集約し、生産コントロールは国内外の工場が担う。さらに、市場ニーズを掴みやすく、通関や関税面でも有利になる現地に生産拠点を置く――といった具合である。
次にERP(Enterprise Resources Planning )とMES(Manufacturing Execution System)のデータを一元管理することだ。これまでは、工場のデータは工場で、ERPのデータは本社で管理するといったやり方が一般的だったが、これからの時代はそれでは通用しない。変化が激しい現代では、情報の一元化をしなければ対応が後手に回ってしまうこともある。ERPとMESのデータをクラウド基盤で一元管理する新たなデジタル・サプライチェーンの構築が急務になる。
最後に、データをどう活かすのかという点だ。物を動かすのには時間や手間がかかるが、情報は瞬時にやりとりできる。データを活用して、いち早くビジネスチャンスを創出することが重要なのだ。
データ活用における3つのポイント
では、データ活用において押さえるべきポイントとは何か。
鍋野氏は次の3点を挙げる。
まず、IT系とOT系、すなわち経営側と工場側のデータを一元管理することだ。IT系データとは、組織データや品目データ、業務プロセスなどであり、OT系データとは、製造関係の数値、画像、センサーなどのデータである。さらに、物流関係のデータも加えて、全てのデータを正規化し、管理することが大切だ。
次に、拠点ごとにばらばらになっているデータを揃えること。多くの企業では、工場や倉庫、物流拠点ごとにデータの単位や粒度が異なっている場合がある。ある拠点ではデータがあるのに、別の拠点ではデータそのものを取得していないという問題も存在する。特に物流データは揃えることが難しく、空輸、陸送、鉄道、船便などで単位が違うこともある。しかし、こうしたデータはきちんと単位や粒度を揃えて整えなければ、活用することが難しい。
最後に、データを貯めすぎないことだ。「データは多いほうが良いだろう」と思い込み、何でも貯めているとパンクしてしまう。とある工場では1分ごとにデータを取得し蓄積し続けた結果、必要なデータを呼び出すのに10分以上かかるほどの量に到達してしまったという。不要なデータは随時消去し、“生きたデータ”を高速かつ即時に検索・処理できる仕組みをつくることが不可欠である。