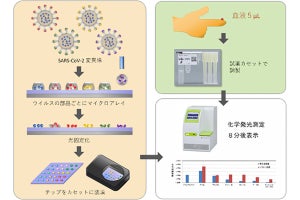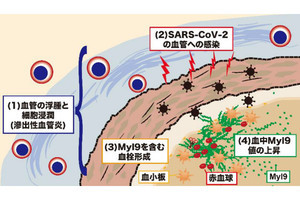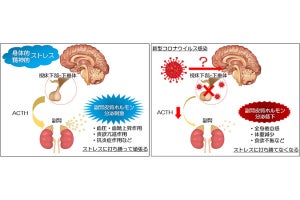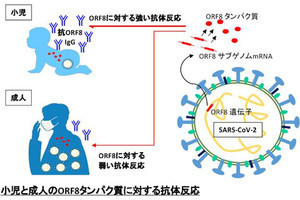慶應義塾大学(慶大)、東京医科歯科大学(TMDU)、大阪大学(阪大)、東京大学、北里大学、京都大学(京大)、科学技術振興機構(JST)の7者は、感染症学、ウイルス学、分子遺伝学、ゲノム医学、計算科学、遺伝統計学を含む、異分野の専門家が集まって結成した「コロナ制圧タスクフォース」が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者検体のゲノム解析を進め、アジアで初めてCOVID-19患者と健常者との遺伝子型を網羅的に比較する大規模ゲノムワイド関連解析を実施し、その結果として免疫機能での重要な役割が知られる遺伝子「Dedicator of cytokinesis 2」(DOCK2)の遺伝子多型が、65歳以下の非高齢者における重症化リスクと関連性を示すことを発見したと発表した。
同成果は、慶大の福永興壱教授、同・金井隆典教授、同・北川雄光常任理事、同・長谷川直樹教授、同・佐藤俊朗教授、同・西原広史教授、同・南宮湖専任講師、同・石井誠准教授(現・名古屋大学大学院 医学系研究科 教授)、TMDU M&Dデータ科学センターの宮野悟センター長、同・小池竜司教授、同・藍真澄教授、同・木村彰方副学長、阪大大学院 医学系研究科の岡田随象教授、同・熊ノ郷淳研究科長・教授、東大 医科学研究所 附属ヒトゲノム解析センターの井元清哉教授、北里大の片山和彦教授、同・高野友美教授、京大大学院 医学研究科の小川誠司教授らが参加するコロナ制圧タスクフォースによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」にオンライン掲載された。
今回、研究チームはCOVID-19に罹患して重篤化し、酸素投与やICU入室が必要となった患者や、死亡した患者の遺伝的背景への関与を調べるため、主に第1~3波で集積された約2400名分のDNAを用いてゲノムワイド関連解析を実施。その結果、日本人のCOVID-19患者では、免疫機能に重要な役割を担うDOCK2の一塩基多型が、65歳以下の非高齢者において、約2倍の重症化リスクを有することを発見したとするほか、第4波・第5波で収集された約2400名分のDNAでも、DOCK2のバリアントが重症化リスクとなることが確認されたという。
また、DOCK2遺伝子から作られるタンパク質「DOCK2」は、リンパ球の遊走や抗ウイルス活性を有するI型インターフェロンの産生に重要な役割を担っていることが知られていたことから、この点を注目。実際のDOCK2発現量を調べるために患者473人の末梢血単核細胞を用いてRNA-seq解析を行ったところ、COVID-19の重症化リスクとなるアリル(塩基配列の型)を持つ患者はそれを持たない患者に比べ、また重症の患者では非重症の患者と比べ、DOCK2の発現量が低下していることが確認されたとする。
加えて、患者61人(健常者31人、重症患者30人)の末梢血単核細胞を用いたシングルセルRNA-seq解析により、DOCK2は単球系の細胞集団で発現が高いことも明らかにされたほか、重症患者では、健常者と比較して、単球系の細胞集団でDOCK2の発現が特に低下していることが判明したとする。
さらに、COVID-19で亡くなられた方の剖検肺を用いて、DOCK2の免疫染色によるタンパク質レベルでの発現解析が行われたところ、COVID-19による肺炎では、一般的な細菌性肺炎に比べて、DOCK2の発現が低下していることが確認されたという。
-

(A)DOCK2リスクアリルを有する65歳未満のCOVID-19患者では、DOCK2発現量が有意に低下していた。(B)重症化するに従い、DOCK2発現量は低下していた。(C)シングルセルRNA-seq解析により、単球と樹状細胞を5つの細胞種に分類された。(D)DOCK2は、CD14+CD16++単球において細胞種特異的に高発現だったとする。(E)COVID-19患者は健常者と比較して、特にCD14+CD16++単球においてDOCK2発現が低下していた。(F)CD14+CD16++単球において、DOCK2リスクアリルを有するCOVID-19患者では、DOCK2発現量が有意に低下していた。一方、健常者においては、同様の傾向が認められなかったという (出所:慶大プレスリリースPDF)
これらの結果は、DOCK2はCOVID-19の疾患感受性遺伝子であるだけでなく、重症化のバイオマーカーとなる可能性を示すものだとする。
研究チームでは、これらの結果を踏まえ、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染動物モデル(シリアンハムスターモデル)を用いて、DOCK2の機能解析を目的に、DOCK2の阻害剤「CPYPP」を感染動物モデルに投与したところ、コントロール群に比べて顕著な体重減少が認められ、肺水腫を呈する重症肺炎が引き起こされることが確かめられたとするほか、CPYPP投与群ではコントロール群に比べて、鼻腔・肺でウイルス量が増加しており、肺内のマクロファージは減少し、抗ウイルス活性に重要な役割を果たすI型インターフェロン応答は低下している一方、炎症性サイトカインが上昇していることも確認されたとしている。
-

(A)DOCK2阻害剤が投与した感染動物モデルは、一般の感染モデルよりも有意に体重が減少していた。(B)DOCK2阻害群は通常群と比較して、6日目以降に肺重量が増加していた。(C)ハムスターの肺病理所見より、DOCK2阻害による炎症細胞における浸潤の増加とマクロファージの遊走障害が認められたという。(D)DOCK2阻害群では鼻腔、肺でSARS-CoV-2ウイルス量が高値だった。(E)DOCK2阻害群ではI型インターフェロン応答の低下、炎症性サイトカインの上昇を認めた (出所:慶大プレスリリースPDF)
なお、研究チームでは今回の研究成果により、今後、DOCK2を活性化する薬剤が新たなCOVID-19の治療薬となることが期待されるとしている。